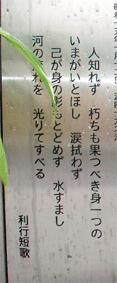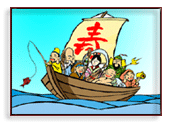 2007年12月3日・小雨、朝からの雨、どうするか迷ってしまいました。どちらかにさいの目を決めかねる時には、尻を重くしてはいけないと何時も思っているので傘をさして出かけて見ることにしました。JR上野駅から日暮里まで小雨と風の中を谷中七福神を回るコースです。雨さえなければ行動範囲をもっと広げられたのですが、結局七福神を回ろうとして二福神を回っただけに終わりました。天候が一因ではありましたが、途中で面白いものに色々引っかかってしまいそれが時間をとることになりました。ホーム・ページ製作の為に電車で出かけることが多くなりました。車では見られなかった多くの事物に出会うことが出来るという思いがけない幸運に恵まれています。 2007年12月3日・小雨、朝からの雨、どうするか迷ってしまいました。どちらかにさいの目を決めかねる時には、尻を重くしてはいけないと何時も思っているので傘をさして出かけて見ることにしました。JR上野駅から日暮里まで小雨と風の中を谷中七福神を回るコースです。雨さえなければ行動範囲をもっと広げられたのですが、結局七福神を回ろうとして二福神を回っただけに終わりました。天候が一因ではありましたが、途中で面白いものに色々引っかかってしまいそれが時間をとることになりました。ホーム・ページ製作の為に電車で出かけることが多くなりました。車では見られなかった多くの事物に出会うことが出来るという思いがけない幸運に恵まれています。 2007.12.03 2007.12.03 |
七福神は各地にありますが中でも谷中の七福神巡りはかなり古いものではないかと言われています。谷中は東京の中で在りし日の町並みが最も残っている地域で、多くの寺院や昔ながらの家並み、路地、坂が今でも生活の場所として活きています。その素晴らしさは観光地の見世物としての建物では無いことです。街は立て替えられながら新しく再生されています。多くの寺院を包み込んでいる東京でも稀有な一帯です。 
この谷中の山の中の通りは車で通っても、退屈な不忍通りや昭和通り・明治通り等に比べると変化に富んだ楽しい道です。道は狭いし坂道が多い上に一方通行があって入ったら出られなくなる恐れもありますので、道に精通した人の通り道になります。
車では殆どの場所が馴染みなのですが(仕事の途中の素通りですが)、歩いて見るといかに見るべきことを失していたことかという思いが強まるばかりです。そしてちょっと前までは人通りの少ない静かな路地を、連なって見物している人々がかなり居ることにも驚かされました。
|
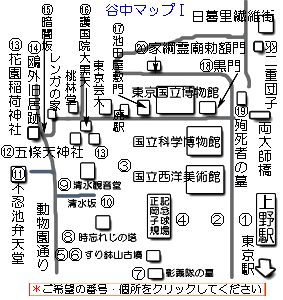 谷中マップⅠ・ *ご希望の場所をクリックしてください
|
|
①冷たい雨が降るJR上野駅公園口、駅舎はこの奥にありま
す。②道路側が公園です右の写真→。
上野の公園口から見ると街路樹がすっかり色づいています、風に舞う葉が少なくありません。一番目の目的地、弁天堂を目指して上野公園を突っ切ることにしました。何時もは駐車場に入れてあわただしく目的地に向かう旅ですが、今回は電車ですので時間がたっぷり有ります。JR上野駅公園口を出ると、公園のイチョウは色づいて風に葉をおとしています。小雨の中をのんびり歩きながら不忍の池を目指して公園を歩いていると今までなんで見落としていたのかと思うような場所が幾つもあるのです。考えられるのは上野に下りたら、動物園、花見、博物館、美術館と目的がハッキリしているのでひたすら目的地を目指して急いでいた為としか思えません。
|
|
③ロダンの銅像が庭に置かれた国立西洋美術館は毎週月曜日休館です。ムンク展が開催されていました。美術館の横を左に曲がると驚くことに野球場がありました。全く今まで気がつかなかった施設です。
|
④正岡子規記念球場:根岸に住んでいた野球好きの正岡子規の名をとって”正岡子規記念球場”と命名されていました。句碑一つ”春風や まりを投げたき 草の原”。子規と言えば、藤沢周平の”白き瓶・長塚節”を思い出しました。節も伊藤左千夫も根岸には頻繁に訪れていたのだという思いが心に沸いて来ました。彼らが立ったであろう同じ場所をこれから歩くことになるのだと、その事を強く意識しました。 |
|
⑤すり鉢山古墳:説明文には、”形状が擂鉢に似ていることから名づけられた約1500年前の前方後円墳と考えられる”とあります。 |
⑥すり鉢山の上にはかって五條天神、清水観音堂が鎮座していたそうです。紅葉と緑の組み合わせがきれいでした。 |
|
⑨清水観音堂:1631年に建立された国の重要文化財、この反対側は能舞台のような重厚な作りです。本堂に安置された子育て観音に願いを込めて叶ったときに人形を奉納します。人形供養の時には沢山の立派な人形が奉納されています、それが表にまで出ているのを見た事があります。 |
|
| ⑦彰義隊の墓:1868年上野の山で起こった”上野戦争”の彰義隊戦死者の火葬場に、1874年に建てられた墓だそうです。戦争は半日で新政府軍が彰義隊を壊滅させたと説明に書かれていました。山岡鉄舟による”戦死之墓”は文字が既に読みにくくなっていました。同志である鉄舟、ここでも清河八郎の痕跡を見ることが出来ました。この右下・階段を下ると西郷さんの銅像があります。 |
|
|
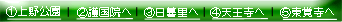
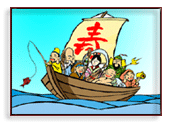 2007年12月3日・小雨、朝からの雨、どうするか迷ってしまいました。どちらかにさいの目を決めかねる時には、尻を重くしてはいけないと何時も思っているので傘をさして出かけて見ることにしました。JR上野駅から日暮里まで小雨と風の中を谷中七福神を回るコースです。雨さえなければ行動範囲をもっと広げられたのですが、結局七福神を回ろうとして二福神を回っただけに終わりました。天候が一因ではありましたが、途中で面白いものに色々引っかかってしまいそれが時間をとることになりました。ホーム・ページ製作の為に電車で出かけることが多くなりました。車では見られなかった多くの事物に出会うことが出来るという思いがけない幸運に恵まれています。
2007年12月3日・小雨、朝からの雨、どうするか迷ってしまいました。どちらかにさいの目を決めかねる時には、尻を重くしてはいけないと何時も思っているので傘をさして出かけて見ることにしました。JR上野駅から日暮里まで小雨と風の中を谷中七福神を回るコースです。雨さえなければ行動範囲をもっと広げられたのですが、結局七福神を回ろうとして二福神を回っただけに終わりました。天候が一因ではありましたが、途中で面白いものに色々引っかかってしまいそれが時間をとることになりました。ホーム・ページ製作の為に電車で出かけることが多くなりました。車では見られなかった多くの事物に出会うことが出来るという思いがけない幸運に恵まれています。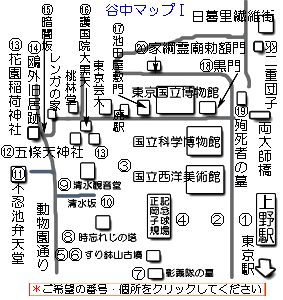 谷中マップⅠ・*ご希望の場所をクリックしてください
谷中マップⅠ・*ご希望の場所をクリックしてください















































 不忍池を琵琶湖に、琵琶湖の竹生島にみたてて弁天島を築きそこにこの弁天堂を建立したものです。現在の建物は昭和33年に再建されたもの。不忍通りから遠望できる竜宮城のような派手な建物、何時もなにかと思っていました。お参りをして線香をあげる。かもめが看板の上で雨の中じっとしています。人に慣れているのか逃げる気配もありません。
不忍池を琵琶湖に、琵琶湖の竹生島にみたてて弁天島を築きそこにこの弁天堂を建立したものです。現在の建物は昭和33年に再建されたもの。不忍通りから遠望できる竜宮城のような派手な建物、何時もなにかと思っていました。お参りをして線香をあげる。かもめが看板の上で雨の中じっとしています。人に慣れているのか逃げる気配もありません。