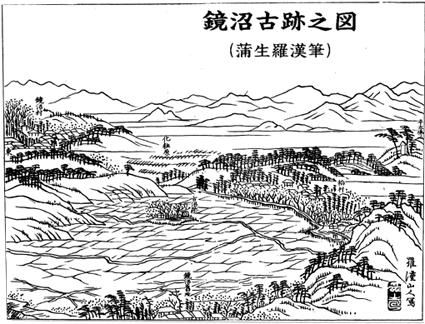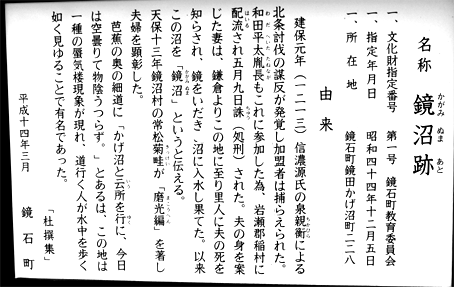私の暮す村をかすめるように芭蕉・曽良は元禄二年(1689年)6月、歌枕の旅を続けていきました。”奥の細道”1冊を持って芭蕉の跡をたどってみます。芭蕉が立ち止まった地で、同じように私も歩みを止めて目にした自然と物との心の交流を試みてみます。既に計7部作の那須の細道と関の細道を掲載しました。東京・深川編6部を加えると合計13部になっています。続いて会津根の細道を掲載します。会津根(磐梯山)を左に見ながら白河の関から須賀川へと向かいます。①かげ沼②相良等窮③十念寺に続いて④石河の滝(乙字ケ滝)を掲載しました。相良等窮差し回しの馬にのって須賀川を出立、石河の滝を経て郡山に向かいます。奥の細道は全17部になります。![]() 2008.5.28
2008.5.28
![]()
![]()
![]()
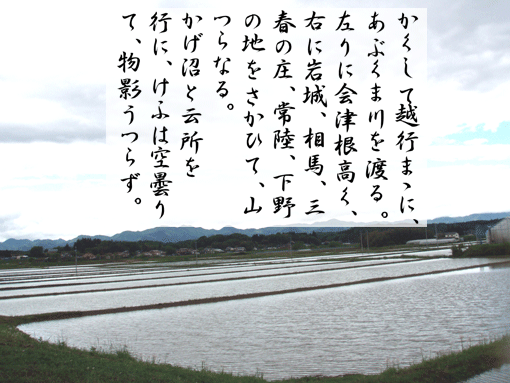 芭蕉と曽良は阿武隈川を越えて矢吹に向かいます。現在の矢吹には当時の面影を残すものはほとんど見られません。これも生きている町の常で、住み暮らす人々が時代に合わせて、壊し建替えていくのですから仕方のないことです。
芭蕉と曽良は阿武隈川を越えて矢吹に向かいます。現在の矢吹には当時の面影を残すものはほとんど見られません。これも生きている町の常で、住み暮らす人々が時代に合わせて、壊し建替えていくのですから仕方のないことです。私は残された道を辿りながら、この同じ道の上を芭蕉と曽良が歩いて行った事を強く意識することで、この旅物語・奥の細道が全く風景の変わってしまった現在に蘇る気がしています。錯覚であってもそう思いながら旅をしてみようと思うのです。単なる物語として読むだけにとどまらず、共に旅する気持ちでいます。今回は、奥の細道の本文”かくして”から”物陰うつらず”までに記述した場所にあたります。この田圃の風景はかげ沼がある一帯で昔は湿地帯であったようです。山なみは会津方面です。かげ沼は左の手前側にあります。普通はこの文章は須賀川に分類されていますが、白河を出て矢吹・鏡石への行程が含まれています。私には幾つかの想像を楽しみたい文章ですので別に取り出して書いてあります。このあとに須賀川の文章が続くことになります。
(本文)かくして越行(こえゆく)まゝに、あぶくま川を渡る。左りに会津根(あいずね・磐梯山)高く、右に岩城(いわき)、相馬、三春の庄、常陸、下野の地をさかひて、山つらなる。かげ沼と云所(いふところ)を行(ゆく)に、けふは空曇りて、物影うつらず。
 現在のかげ沼は周りを田圃にかこまれ、小さくなってしまっています。 一帯で逃げ水(蜃気楼のような)現象が見られたという言い伝えが想像も出来ないほどの可愛らしい大きさです。
現在のかげ沼は周りを田圃にかこまれ、小さくなってしまっています。 一帯で逃げ水(蜃気楼のような)現象が見られたという言い伝えが想像も出来ないほどの可愛らしい大きさです。
村には優れた物語の作者にあふれています。私はこの伝承の真実性をあれこれ検証せずに、物語の一つとして聞いておこうと思っています。
個人的な経験ですが、一帯が強い霧に覆われて高速道路が通行止めとなった事があります。4号線も車がのろのろと走っていました。霧の中で全てが微妙な光に反射していました。山ではたまに出会う現象ですが、平地でであったの北海道以外あまりありません。その時の周りの景色も常ならない不思議な印象でした。一回の経験を全てに当てはめるのは合理的とはいえませんが、私の心の中ではきっとこのような景色の事を(逃げ水とは全く違いますが)指しているのではないかと秘かに思っています。一方、田圃を掘ると温泉が出てくるような地層ですから、もしかして蜃気楼の言い伝えに関係があるのか等と想像を楽しんでいます。かげ沼に来て天気が少し回復してきました、曇り空ながら今日は池の端の木の陰が水面に映っています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
白河から矢吹へ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) Oct. 10,2007 Oozora.All Right Reserved.
|
||

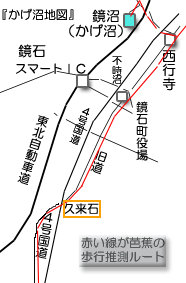
 芭蕉にとって奥州への一つ目の心の垣根が隔てる山なみであり、やっとそれを越えて目にした阿武隈川は奥州への最後の垣根、向こう岸だったのではないでしょうか。利根川(鬼怒川)も那珂川もその記述が奥の細道には見られません。特に、芭蕉が日光から那須野が原へ向かう
芭蕉にとって奥州への一つ目の心の垣根が隔てる山なみであり、やっとそれを越えて目にした阿武隈川は奥州への最後の垣根、向こう岸だったのではないでしょうか。利根川(鬼怒川)も那珂川もその記述が奥の細道には見られません。特に、芭蕉が日光から那須野が原へ向かう



 このような石塔を見ると、人々の願いが宿っていることを感じます。
このような石塔を見ると、人々の願いが宿っていることを感じます。


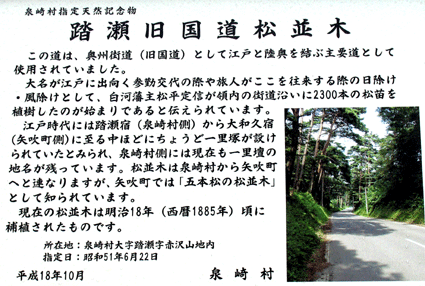



 矢吹の旧道を更に北に進むと4号線に斜め交わる北町の交差点にぶつかります。右・福島方面に進むと芭蕉の言う、左にあいず根・右に三春の庄を隔てる峰々が広がる道になります。鏡石町に入り左に東北道鏡石パーキング・エリア・スマートICの入り口看板がある交差点が出てきます。そこから僅かの距離で小さな信号の有る交差点の左にかげ沼の標識(左角は設備屋さんだったと思います・右側には西行寺の小さな標識)があります。そこを左折して東北道をくぐります。ひろがる田圃の向こうに会津の山なみが広がって居ます。当時はかなり広い湿地帯であったのかもしれません。暫く進むと左にかげ沼入り口の看板があります。田圃の中の道を500~600進むと公園を兼ねたかげ沼が出てきます。案内板にはこの地がかげ沼と称されていた事の一つの歴史的証明の説明板がありました。
矢吹の旧道を更に北に進むと4号線に斜め交わる北町の交差点にぶつかります。右・福島方面に進むと芭蕉の言う、左にあいず根・右に三春の庄を隔てる峰々が広がる道になります。鏡石町に入り左に東北道鏡石パーキング・エリア・スマートICの入り口看板がある交差点が出てきます。そこから僅かの距離で小さな信号の有る交差点の左にかげ沼の標識(左角は設備屋さんだったと思います・右側には西行寺の小さな標識)があります。そこを左折して東北道をくぐります。ひろがる田圃の向こうに会津の山なみが広がって居ます。当時はかなり広い湿地帯であったのかもしれません。暫く進むと左にかげ沼入り口の看板があります。田圃の中の道を500~600進むと公園を兼ねたかげ沼が出てきます。案内板にはこの地がかげ沼と称されていた事の一つの歴史的証明の説明板がありました。