
日本橋堀留町椙森神社狛犬・昭和8年(1933年)
日本橋・東宝シネマズで”スリー・ビルボード”を見た後、日暮里に立ち寄ると言う家人を地下鉄銀座線の駅まで送ってから一人で日本橋近辺の社と狛犬を巡る事にしました。日本橋を出たのが午後3時20分、夕方が近い時間です。約1時間ほどの散策で三光稲荷、末廣神社、椙森神社の3つの中央区の神社を訪ねる事が出来ました。
 |
|
|---|---|
|
|
 |
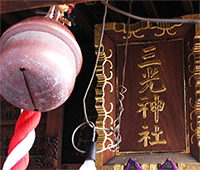 |
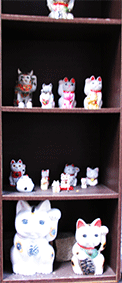 |
|---|---|---|
| この路地を入ると右手に神社がありました。お参りをしてから狛犬を見る事にします。由来によれば、猫の迷子に霊験あらたかと伝えられているようです。猫の置物は猫が見つかったお礼に奉納されたもののようです。 |
||
|
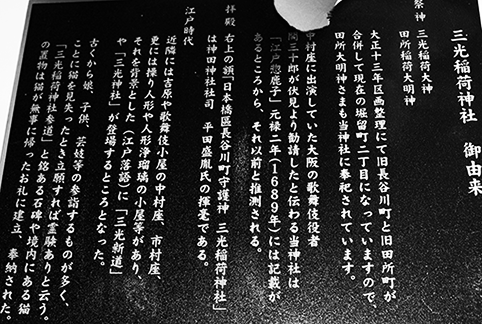 |
|
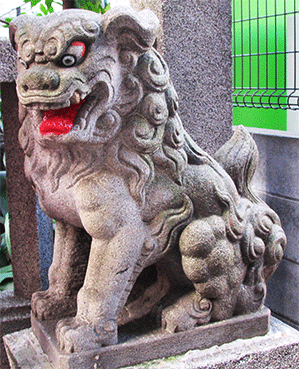 入り口の鳥居の脇に狛犬が奉納されています。新しい狛犬のようです、いわゆる岡崎式といいうタイプかと思われます。
入り口の鳥居の脇に狛犬が奉納されています。新しい狛犬のようです、いわゆる岡崎式といいうタイプかと思われます。
ただこの狛犬は中々表情が良く、彩色も施されていて、通常みられるこの手の狛犬より出来が良いように見えます。
こちらは右に置かれた阿像と思われます。柵と接していて台座を見る事が出来ませんので年代・石工名は見付ける事が出来ませんでした。![]() 2018.02.06
2018.02.06
 阿像から吽像を写しています。阿像の右には鉢植えのボケの花が色を添えています。
阿像から吽像を写しています。阿像の右には鉢植えのボケの花が色を添えています。
吽像は鳥居と旗の間から少しだけ体が見えます。![]() 2018.02.06
2018.02.06
 左に置かれた吽像、こちらも彩色が綺麗に施されているので見て楽しい狛犬です。岡崎式と言われるものでもこのような狛犬が居る事が分かりました。
左に置かれた吽像、こちらも彩色が綺麗に施されているので見て楽しい狛犬です。岡崎式と言われるものでもこのような狛犬が居る事が分かりました。![]() 2018.02.06
2018.02.06
橘稲荷神社
 |
 |
橘稲荷神社住所:中央区日本橋人形町3丁目3 。三光稲荷から人形駅を目指して進んでいると50m程進んだ通りの脇に小さな稲荷神社がありました。大変綺麗に作られています。氏子の人達に大切にされているらしく大変綺麗な社です。ビルも遠慮しているような一等地に鎮座していました。狛犬は居ませんでしたがお参りをさせて貰いました。
2018.02.06
 |
|
|---|---|
|
|
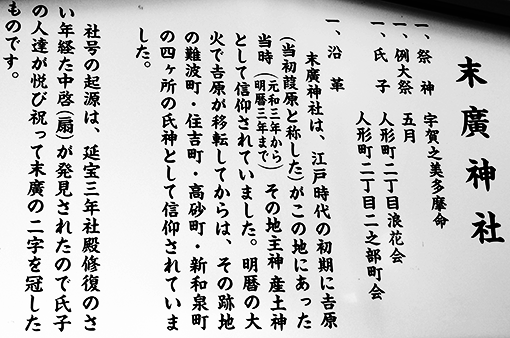
ここに古い吉原・元吉原があったと説明版に書かれて居て驚きました。明暦の大火の後浅草田圃に移った事は江戸の物語にしばしば登場しますが、ここが旧吉原だとは知りませんでした。以前訪ねた事のある新吉原の見返り柳と”生れては苦界死しては浄閑寺”と花又花酔に詠まれた浄閑寺を思い出しました。
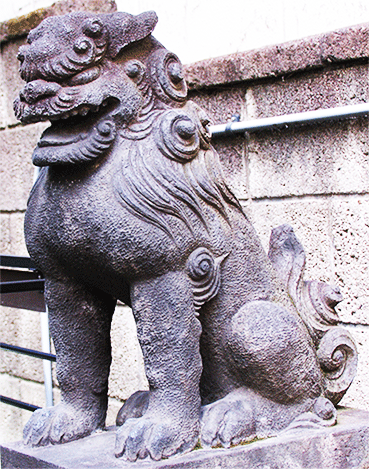 ビルに囲まれた境内はそれほど多くの人が一度に参拝は出来ないようです。二組の参拝の人が入っていったので入り口の狛犬を最初に見させてもらいました。入り口の狛犬はかなり力強い風貌に見えます。
ビルに囲まれた境内はそれほど多くの人が一度に参拝は出来ないようです。二組の参拝の人が入っていったので入り口の狛犬を最初に見させてもらいました。入り口の狛犬はかなり力強い風貌に見えます。
右に置かれた阿像、台座には昭和21年の年号と奉納した人の名前と思われるものが彫られています。石工の名前は下端部が欠落しているのですが”若山(山らしい文字の一部が欠落しています)”ではないかと推測しています。
太平洋戦争が終わった一年後にこれ程の狛犬を奉納したのはさぞかし大変な事だったのでは思いました。![]() 2018.02.06
2018.02.06
 左に置かれた吽像です。このような個性のある狛犬は見ていて楽しいものです。この狛犬は横長の鋭い目付きに特徴があるようです。サイズは普通より少し大きいように見えます。
左に置かれた吽像です。このような個性のある狛犬は見ていて楽しいものです。この狛犬は横長の鋭い目付きに特徴があるようです。サイズは普通より少し大きいように見えます。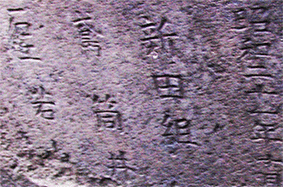 阿吽共台座にこの彫があります。年号の昭和21年と奉納者と思われる名前は判読できますが、石工の名前の上の文字は”若”ですが、下の文字は下端部が欠落しています。多分”山”ではないかと思います。
阿吽共台座にこの彫があります。年号の昭和21年と奉納者と思われる名前は判読できますが、石工の名前の上の文字は”若”ですが、下の文字は下端部が欠落しています。多分”山”ではないかと思います。 |
|
|---|---|
|
|
 境内への入り口は、日本橋方向と清洲通り方向の2か所にありました。こちらは日本橋方向の入り口です。社殿はかなり大きそうに見えます。
境内への入り口は、日本橋方向と清洲通り方向の2か所にありました。こちらは日本橋方向の入り口です。社殿はかなり大きそうに見えます。![]() 2018.02.06
2018.02.06
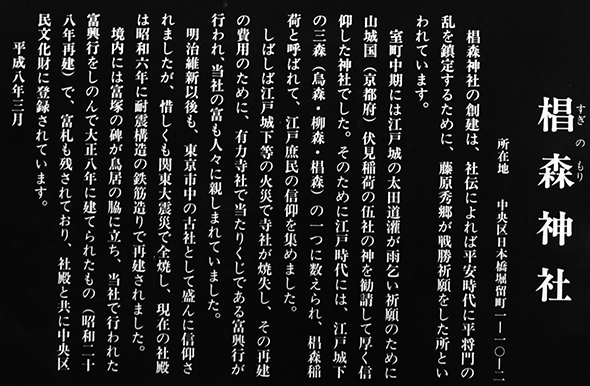
中央区の説明版には、神社の伝えるところによれば創建は平安時代にさかのぼると書かれています。更に富くじが行われた神社の一つであったようです。
2018.02.06
 日本橋方向からの入り口の鳥居の横に置かれている狛犬です。右に置かれた阿像を思われます。
日本橋方向からの入り口の鳥居の横に置かれている狛犬です。右に置かれた阿像を思われます。
逆光ではっきり見えませんが、なかなか表情がリアルな狛犬です。若干顎が長く出たユニークなデザインに見えます。この時代の石工の人の腕はほぼ揃っているのでどの狛犬もバランスが取れていて安心して鑑賞する事ができます。子供の狛犬が添えられています。![]() 2018.02.06
2018.02.06
 狛犬の前面に立つことが難しいので阿像の後ろから吽像の方向を写しました。そろそろ夕方が近くなった時間、一日の仕事の切りを付けるためか通りには人通りが殆どありません。少し日が落ちかけてきた境内で二つの狛犬がこれから生き物に返るような雰囲気を感じさせます。
狛犬の前面に立つことが難しいので阿像の後ろから吽像の方向を写しました。そろそろ夕方が近くなった時間、一日の仕事の切りを付けるためか通りには人通りが殆どありません。少し日が落ちかけてきた境内で二つの狛犬がこれから生き物に返るような雰囲気を感じさせます。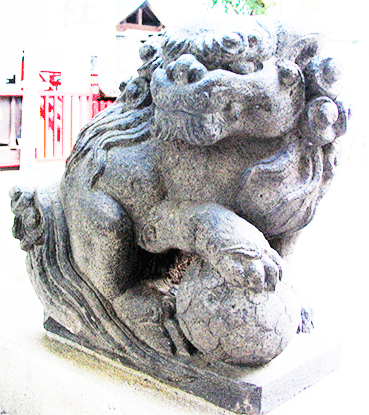 左に置かれた吽像です、足下には大きな玉が彫られています。
左に置かれた吽像です、足下には大きな玉が彫られています。 狛犬の周囲に立ち入れないので台座を調べる事ができません。昭和8年1月の文字だけを見つけました。
狛犬の周囲に立ち入れないので台座を調べる事ができません。昭和8年1月の文字だけを見つけました。 日本橋に戻ってきました、午後4時半です。映画を見終わってから日本橋を出たのは午後3時20分です、1時間ほどの散歩としては随分密度の濃い時間を過ごすことが出来ました。
日本橋に戻ってきました、午後4時半です。映画を見終わってから日本橋を出たのは午後3時20分です、1時間ほどの散歩としては随分密度の濃い時間を過ごすことが出来ました。
江戸時代の商業の中心地の一つであった日本橋と隅田川に挟まれた一帯を見る事が出来た事は、これから読む江戸の物語の理解の深さと楽しさを増してくれるようです。![]() 2018.02.06
2018.02.06
地下鉄銀座線の駅を目指して階段を下りました。
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
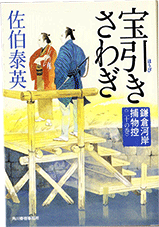 因みに、江戸時代この三光稲荷神社界隈にあった三光新道が佐伯泰英の”鎌倉河岸捕物控・20巻・宝引きさわぎ”の舞台の一つです。江戸の物語にしばしば、江戸っ子らしさを体現する対象として登場する町火消と魚河岸の若い衆達の宴席に呼ばれた柳橋のおちゃぴいな芸者・小夏の暮らした長屋がこの辺りにあったことになります。高層ビルが整然と立ち並ぶ無菌室のような空間から、人々の暮らしが身近に感じられる町並みに入ると緊張が緩やかに溶けてきます。通りに立って、政次・彦四郎・亮吉が活躍する江戸の物語を思い出しています。
因みに、江戸時代この三光稲荷神社界隈にあった三光新道が佐伯泰英の”鎌倉河岸捕物控・20巻・宝引きさわぎ”の舞台の一つです。江戸の物語にしばしば、江戸っ子らしさを体現する対象として登場する町火消と魚河岸の若い衆達の宴席に呼ばれた柳橋のおちゃぴいな芸者・小夏の暮らした長屋がこの辺りにあったことになります。高層ビルが整然と立ち並ぶ無菌室のような空間から、人々の暮らしが身近に感じられる町並みに入ると緊張が緩やかに溶けてきます。通りに立って、政次・彦四郎・亮吉が活躍する江戸の物語を思い出しています。
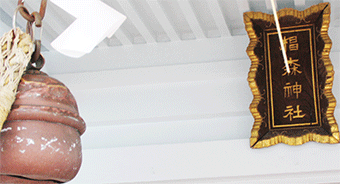 椙森(スギノモリ)神社住所:中央区日本橋堀留町1丁目10−2。人形町駅傍の末廣神社から清洲橋通りに戻り、先程日本橋から歩いて来た道を戻ります。清洲橋通りを渡って二つ目の角を右折、暫く進むと右に神社の鳥居が見えました。かなり大きな神社です。
椙森(スギノモリ)神社住所:中央区日本橋堀留町1丁目10−2。人形町駅傍の末廣神社から清洲橋通りに戻り、先程日本橋から歩いて来た道を戻ります。清洲橋通りを渡って二つ目の角を右折、暫く進むと右に神社の鳥居が見えました。かなり大きな神社です。