⑤美しい塀と路地:長安寺の角を曲がると何とも美しい路地と塀が見えます。この路地の先には何があるのでしょうか、3人連れの若者が話しながら彼方の四辻を曲がって行きました。子供の頃の路地の探検では、路地の角を曲がるたびに馴染みの場所から遠ざかる心細さに引返そうと何度も思います、でもこれから見える新たな世界に心が躍り闇雲に足を進めたものです。路地の先に寺院でしょうか大きな木が見えます。東京にもこれほど美しい場所があったのかと感嘆の声をもらしてしまいました。
この地でこの塀と共に暮らし、守ってきた人々の歴史が奥深い美しさ生みだしているのでしょう。酒が味わいを醸し出すには時間と酵母が欠かせないように、人間の構築物が深みのある美しさを輝かせるためには人々の長い手入れが必要なのではないでしょうか。かっては天秤棒を担いだ物売りが通り、死者をともらう僧侶が通り、子供が歓声を上げながら走り回ったことでしょう。私には人々の思いがこの塀に染み付いているような気がします。上の写真は長安寺の通りから、下は路地の中に入り長安寺の通りに向かって撮影したものです。塀の長さが分かると思います。湯島聖堂の塀の整然とした美しさと谷中の塀の柔らかい温もりを感じる美しさ、共に年月と人々が生み出したものでしょう。共に今でも活きている事が稀有な事に思えます。この塀は赤穂浪士ゆかりの観音寺のものだとの事です。
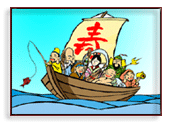 2007年12月4日・快晴。冷たい雨の3日に続き4日も谷中七福神を回る。青
2007年12月4日・快晴。冷たい雨の3日に続き4日も谷中七福神を回る。青 空が広がり心も晴れやか、行程も捗り6箇所を回る。最初の天王寺毘沙門天はこの中で最も印象的なお寺でした。
空が広がり心も晴れやか、行程も捗り6箇所を回る。最初の天王寺毘沙門天はこの中で最も印象的なお寺でした。





 ②東京路地風景:駅の目の前の路地、旅館があり町屋が立て込んだ在りし日の東京が日暮里駅前の崖の上にありました。映画のセットでもなくリアルに存在することに声も出ないほどの大きな喜びを感じます。この細い道を少し進むと天王寺、この界隈が七福神周りの白眉でしょう。
②東京路地風景:駅の目の前の路地、旅館があり町屋が立て込んだ在りし日の東京が日暮里駅前の崖の上にありました。映画のセットでもなくリアルに存在することに声も出ないほどの大きな喜びを感じます。この細い道を少し進むと天王寺、この界隈が七福神周りの白眉でしょう。







 *地図上のご希望の場所や番号をクリックして下さい
*地図上のご希望の場所や番号をクリックして下さい 天王寺のお地蔵さん。立派なお堂にいらっしゃいます。
天王寺のお地蔵さん。立派なお堂にいらっしゃいます。 天王寺境内のお堂、かなり古い建物のようだ。見事な紅葉を愛でながらお参りをする。平日で参拝客もまばら。境内の青空が広い。
天王寺境内のお堂、かなり古い建物のようだ。見事な紅葉を愛でながらお参りをする。平日で参拝客もまばら。境内の青空が広い。 谷中墓地のメイン・ストリート。両側に著名人を含めた多くの墓、後方には日暮里の再開発地域の大きなビルが見える。歴史と未来が見事に融合している。
谷中墓地のメイン・ストリート。両側に著名人を含めた多くの墓、後方には日暮里の再開発地域の大きなビルが見える。歴史と未来が見事に融合している。













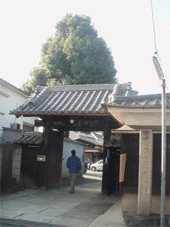


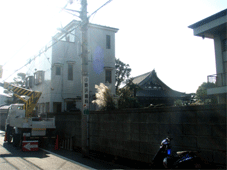 町並みに溶け込んだ観音寺の屋根。谷中はいたるところに寺院があります。俗を排除した寺もよいのですが、世俗に囲まれた精神世界、これが凡人には優しさを感じてしまいます。街の人々と肩肘張らずに共生する姿が私には羨ましく思えます。
町並みに溶け込んだ観音寺の屋根。谷中はいたるところに寺院があります。俗を排除した寺もよいのですが、世俗に囲まれた精神世界、これが凡人には優しさを感じてしまいます。街の人々と肩肘張らずに共生する姿が私には羨ましく思えます。 四十七士慰霊塔として今も信仰を集める観音寺境内のお堂。赤穂浪士を助けていた寺として知られている観音寺ならではです。
四十七士慰霊塔として今も信仰を集める観音寺境内のお堂。赤穂浪士を助けていた寺として知られている観音寺ならではです。



 ⑧大黒天経王寺(だいこくてん・きょうおうじ)
⑧大黒天経王寺(だいこくてん・きょうおうじ)
 た為に、新政府軍の攻撃をうける。山門には今も銃弾の跡が残る。本堂横の大国堂に日蓮作と言い伝えられる大国像がある。(説明文抜粋)立派な寺で広く地域の人々の尊敬を集めるという説明が納得できます。
た為に、新政府軍の攻撃をうける。山門には今も銃弾の跡が残る。本堂横の大国堂に日蓮作と言い伝えられる大国像がある。(説明文抜粋)立派な寺で広く地域の人々の尊敬を集めるという説明が納得できます。









 『御宿かわせみ』ファンの方には思い出すお寺かもしれません。文芸春秋の単行本では13巻の『鬼の面』P245からの『春の寺』に
『御宿かわせみ』ファンの方には思い出すお寺かもしれません。文芸春秋の単行本では13巻の『鬼の面』P245からの『春の寺』に