私の暮す村をかすめるように芭蕉・曽良は元禄二年(1689年)6月、歌枕の旅を続けていきました。”奥の細道”1冊を持って芭蕉の跡をたどってみます。芭蕉が立ち止まった地で、同じように私も歩みを止めて目にした自然と物との心の交流を試みてみます。既に計7部からなる那須の細道と関の細道を掲載しました。東京・深川編6部を加えると合計13部になっています。続いて会津根の細道を掲載します。会津根(磐梯山)を左に見ながら白河の関から須賀川へと向かいます。①かげ沼②相良等窮③十念寺に続いて④石河の滝(乙字ケ滝)を掲載しました。相良等窮差し回しの馬にのって須賀川を出立、石河の滝を経て郡山に向かいます。奥の細道は全17部になります。![]() 2008.3.2
2008.3.2
![]()
![]()
![]()
 |
 |
|
 |
 |
 参考書に辟易したとは言え、それ無しでは奥の細道で迷うのも事実です。これは、5冊ほどの中から私が最終的に選んだ一冊の参考書です。著者は芭蕉の旅を歌枕の地への旅だと述べて、更に”芭蕉の行って見たいのは、文学と歴史と自然とが結合した場所であり物である。見たいのは人間と時間とが結びついた自然であり物である。”と書いています。
参考書に辟易したとは言え、それ無しでは奥の細道で迷うのも事実です。これは、5冊ほどの中から私が最終的に選んだ一冊の参考書です。著者は芭蕉の旅を歌枕の地への旅だと述べて、更に”芭蕉の行って見たいのは、文学と歴史と自然とが結合した場所であり物である。見たいのは人間と時間とが結びついた自然であり物である。”と書いています。
数年前からただ美しい、綺麗な自然や物に感動する事が少なくなっていて、私の精神が硬直したかと案じていました。卑近な例で言えば、雪を頂いた富士山だけでは飽きるのです。そこに富士浅間神社があり、江戸時代の富士講の石碑を添えると俄然私の中で富士山が輝きを増すのです。著者のこの言葉が私の自然観の変化の謎を解き明かしてくれたのです。
奥の細道の原文に立ち入ることを避けて、読む人が自由に心を遊ばせられるようにさりげなく知識を与えてくれる(与えられる知的な事柄は深く興味深いものですが)書き方にも好意を持ちました。新潮社・奥の細道を歩く・井本農一、村松友次・土田ヒロミ著。
|
元禄二年(1689年) 芭蕉・曽良那須滞在表
|
||
|
旧暦
|
新暦
|
場所
|
|
4月16日
|
6月3日
|
黒羽をたって那須町高久の高久覚左衛門宅に宿泊する。 |
|
4月17日
|
6月4日
|
雨の為高久覚左衛門宅に宿泊する。 |
|
4月18日
|
6月5日
|
那須湯本温泉の湯宿・五左衛門に宿泊する。 |
|
4月19日
|
6月6日
|
湯本温泉内の温泉神社、殺生石を見る。 |
|
4月20日
|
6月7日
|
朝8時に湯本を出立。芦野の遊行柳を見、境の明神から白河の関に出る。旗宿に泊まる。 |
 旧4号線と県道17号線とが交差する那須分岐点”手前が那須湯本温泉、右が黒磯駅、直進が遊行柳、左が芭蕉の訪れた二宿の地になります。 旧4号線と県道17号線とが交差する那須分岐点”手前が那須湯本温泉、右が黒磯駅、直進が遊行柳、左が芭蕉の訪れた二宿の地になります。 |
||
 |
||
| スーパーのイオンを左に見て信号を一つ過ぎると右側に高福寺が見えます。境内に芭蕉の句碑があります。 | ||
 |
 |
|
 |
 |
単に面白い物語としての奥の細道を読みたかったのですが、リズム感にあふれた奥の細道の文章と作者芭蕉の姿が遠ざかるばかり、細道は山の森の中にかき消えてしまいそうです。解説書を読めば読むほど、知識の無い私の芭蕉の跡を訪れる気持ちはしぼんできます。それでも、折角なのだから、住む村の近くにある芭蕉の地にたってその心を感じてみたいと言う気持ちは抑えがたく、芭蕉について、奥の細道の物語について考えを巡らして見ました。
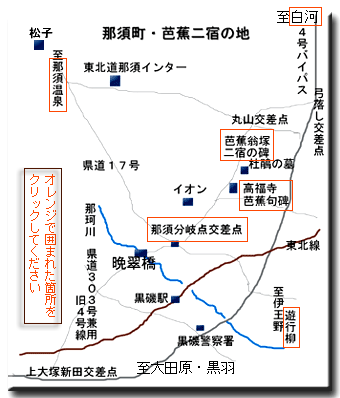 奥の細道を旅した芭蕉(寛永21年・1644年~ 元禄7年・1694年)は、澄んだ精神を内蔵した肉体を、自らの足で一歩ずつ運んで歌枕の地を経巡った事は私でもおぼろげに理解できます。この事実の上に奥の細道の物語をよこたえてみました。
奥の細道を旅した芭蕉(寛永21年・1644年~ 元禄7年・1694年)は、澄んだ精神を内蔵した肉体を、自らの足で一歩ずつ運んで歌枕の地を経巡った事は私でもおぼろげに理解できます。この事実の上に奥の細道の物語をよこたえてみました。
旅する時には、朝、宿をたったら次の宿までたどり着く丈夫な二本の足だけが頼りです。知識やお題目では一歩たりとも坂道を登る事は出来ません。この時芭蕉の第一の関心事は、石を避け緩い傾斜を探しながらとにかくつつがなく歩くことにあったに違いありません。まさに歩を進めている大部分の時間は無我の境地といえるでしょう。だからこそ、やるべきことも考えることも一つだからこそ、精神も自由なのではないでしょうか。一事だけに集中した余裕ある精神と肉体が互いに共鳴しあいながら歌まくらの地にたったからこそ、躍動する魅力的な文章になったと私の貧弱な知恵で感じました。
既に多くの古の言葉を消化して自らのものとしている芭蕉にとって、吐き出された奥の細道の文言こそが芭蕉なのです。後世の人々が、芭蕉の精神を腑分けするがごとく、その言葉は何に由来していると書きますが、たとえそうであっても、既に血肉となった紛れもない芭蕉の言葉なのです。瑣末な事にこだわらず、奥の細道の言葉だけを素直に見つめることで良いのではと思い至りました。
ならば、私の能力で出来ることと言えば、自分の知識の及ぶ範囲で、芭蕉の奥の細道の原本の場所をたどり、芭蕉との心の通い合いを試みてみようということになります。芭蕉の心と曽良の記録、この二つを先達にして歩ける範囲をゆっくりと見てみたいと思っています。
一度で心が感動しないのなら、もう一度、それでも沸き立つ心にならないのなら何度でも、秋に・冬に・夏に・春に訪れれば良いことです。幸い私の住む村をかすめて芭蕉は奥の細道の旅を続けたのです。以上の事から、ここに書かれた印象は全く個人的なもので、奥の細道と言うより”僕の細道”とい言う題があたっています。この歳で僕というのも差しさわりがありまので、私の住む村の奥の細道をたどって、その地の細道と題を付けてみました。
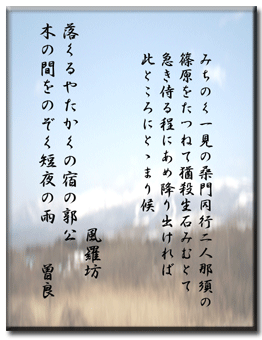 曽良の記録を元に、二人が歩いた道の話は沢山のウエッブ・サイトで見ることが出来ます。これらは私のような付け焼刃の知識の者には及ばないほど専門的で詳細です。これほど多くの人々が自分なりの思いで芭蕉の地を実際に歩いていることには大変勇気付けられました。
曽良の記録を元に、二人が歩いた道の話は沢山のウエッブ・サイトで見ることが出来ます。これらは私のような付け焼刃の知識の者には及ばないほど専門的で詳細です。これほど多くの人々が自分なりの思いで芭蕉の地を実際に歩いていることには大変勇気付けられました。
自分の知識の及ぶ範囲で、何処を歩いたかではなく、芭蕉の跡をたどりながら何を思ったかを出来る限り記したいと思います。理解が誤っているかもしれないことを危惧しますが、それは追々芭蕉の地に何度も立ちながら私の及ぶ範囲で理解を深めていければと思っています。
左写真・芭蕉が高久家滞在の礼として残した自筆の俳句懐紙の文言です。尚、ご存知かと思いますが風羅坊は芭蕉の別称です。

(D)高久家の横に、芭蕉来訪を記念して立てられた石碑。杜鵑の墓とも呼ばれています。屋根が掛けられています。
 黒羽の大関藩城代家老・浄法寺図書の紹介状を持って芭蕉が2泊した高久家が近づいてきます。黒磯駅方面から来た場合、スーパーのイオンが左に出てくると、少しで信号があります(多分那須分岐点の信号から一つ目だと思います)。信号から10メートルほど行った右側に大変格式が高い高久家の菩提寺である高福寺があります。落ち着きがある立派な古刹に見えます。寺の説明に本殿に参ってからと書かれていたので、手をあわせて芭蕉に会いに来たことを祈りました。句碑があると言うことですが、その看板もまったくありません。芭蕉を売り物になどしない、それが私には清清しい気がしてなりません。
黒羽の大関藩城代家老・浄法寺図書の紹介状を持って芭蕉が2泊した高久家が近づいてきます。黒磯駅方面から来た場合、スーパーのイオンが左に出てくると、少しで信号があります(多分那須分岐点の信号から一つ目だと思います)。信号から10メートルほど行った右側に大変格式が高い高久家の菩提寺である高福寺があります。落ち着きがある立派な古刹に見えます。寺の説明に本殿に参ってからと書かれていたので、手をあわせて芭蕉に会いに来たことを祈りました。句碑があると言うことですが、その看板もまったくありません。芭蕉を売り物になどしない、それが私には清清しい気がしてなりません。
|
 高福寺で句碑が分からず、もしや高久家の墓にあるのかと探して見ました。高久覚左衛門信近の文字が偶然目に入ったのです。わざわざ私の目の前に現れてくれたように思えました。 高福寺で句碑が分からず、もしや高久家の墓にあるのかと探して見ました。高久覚左衛門信近の文字が偶然目に入ったのです。わざわざ私の目の前に現れてくれたように思えました。 |
 |

|
| 享保18年(1733年)と読めます。芭蕉が訪れた元禄2年(1689年)と符合するのではないでしょうか。この時より44年存命であったとしたら当時としてはかなり長命な人生であったでしょう。 | 高福寺の句碑は思ったより小さなものでした。まことに良いサイズです。文字も消えかかっています。句碑の芭蕉・曽良の文字を書き出してみました。 | ||
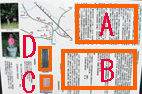 那須町教育委員会がたてた大変詳細な杜鵑(ホトトギス)の墓・石碑の説明です。右側面・表面・左側面の3面の碑文が書きとめられています。長年風雨にさらされていたために今では一部判読不能になっています。A・B・C・D各部を拡大してみました。
那須町教育委員会がたてた大変詳細な杜鵑(ホトトギス)の墓・石碑の説明です。右側面・表面・左側面の3面の碑文が書きとめられています。長年風雨にさらされていたために今では一部判読不能になっています。A・B・C・D各部を拡大してみました。芭蕉来訪を記念して、高久家北側の小高い丘に1754年に立てられた”芭蕉庵桃青君碑”別名杜鵑の墓と呼ばれる右の石碑(D)があります。長年の雨で彫られた文字が薄くなっています。坂道を少し登ります。石碑文面・由来等は案内板B部分に書かれています。地方都市に住む資産家階級の文化的関心の高さは非常に高いものだったでしょう。著名な本物の江戸の俳人・芭蕉の訪問を心から感謝もし歓待もしたのでしょう。もちろん芭蕉の人柄にもひかれ、心の交流があったと推測できます。3代目の孫が立てたと言うこの石碑はその表れだったのでしょうか。

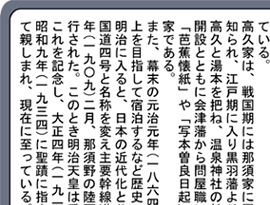 |
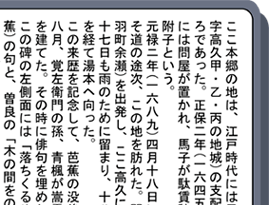 |
|
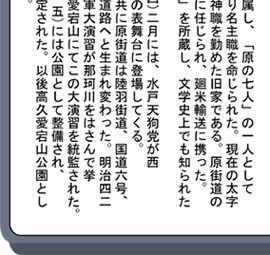 |
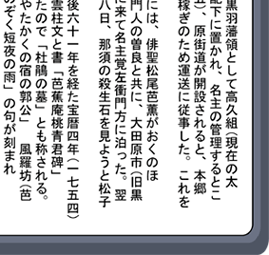 |
この親切な説明文で芭蕉と高久覚左衛門・高久家との関係が分かりました。現在も那須には高久の名前が付いた地名が広大な範囲にありますが、それもなるほどと思える高久家の歴史です。
又、高久家の前の通りが現在は旧4号国道(県道303号線と兼用)であり、昔は会津地方からの米の物資輸送路として栄えた原街道であったことにも驚きました。そうであれば、高久家がその問屋であったことは当然だと思います。
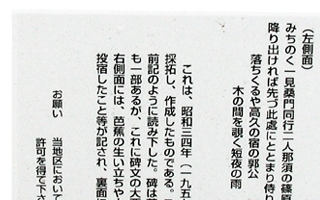 |
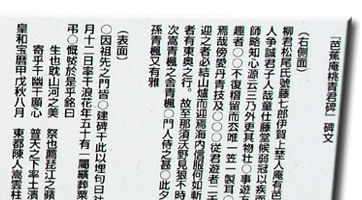 |
|
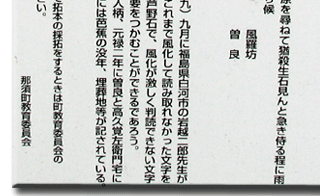 |
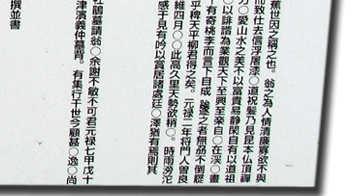 |
 この碑は高久家の敷地の原街道の際に立っています。芭蕉が二夜宿泊したことの印。高久家の歴史については上記那須町教育委員会の看板に詳細に語られています。 この碑は高久家の敷地の原街道の際に立っています。芭蕉が二夜宿泊したことの印。高久家の歴史については上記那須町教育委員会の看板に詳細に語られています。 |
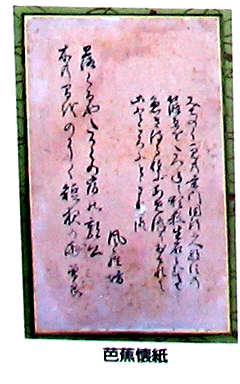 |

|
|
 |
 写真左は芭蕉翁塚から高福寺・黒磯駅方面を望む。右の写真は白河方面を望む。 写真左は芭蕉翁塚から高福寺・黒磯駅方面を望む。右の写真は白河方面を望む。 |
 高福寺を旧4号線から見ます。直ぐ後ろに4号バイパス。 高福寺を旧4号線から見ます。直ぐ後ろに4号バイパス。 |
|


