桜の道を辿る・那須町から須賀川市まで4 桜の道 ①・②・③
|
|
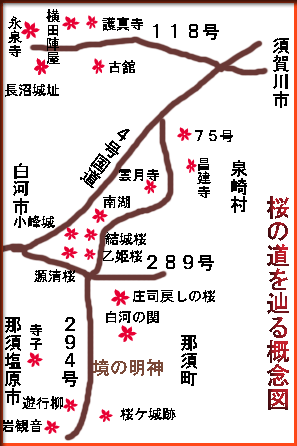 泉崎村の75号線の桜並木を見て4号線に出ます。右折して北上カーナビに導かれて118号線に出ます。結構長く走った印象です。護真寺に車を留めて、歩いて横田陣屋跡の桜を見ます。個人の方が手入れをして見せてくれる美しい枝垂桜に言葉もありません。 泉崎村の75号線の桜並木を見て4号線に出ます。右折して北上カーナビに導かれて118号線に出ます。結構長く走った印象です。護真寺に車を留めて、歩いて横田陣屋跡の桜を見ます。個人の方が手入れをして見せてくれる美しい枝垂桜に言葉もありません。
古舘の桜を訪れて、桜の下で昼食をとります。箸を口に運んでは桜を見上げます。幼い頃のお花見の思い出が懐かしく目に浮かびます。空は晴れ渡っています。
長沼の静かな城下町に入り、長沼城址に車を留めて永泉寺の枝垂桜を見ます。戻って上杉景勝ゆかりの長沼城址の桜を見て今回の桜の道を辿る旅は終わりとしました。 2012.4.24 2012.4.24 |
辿った桜の道の桜 |
| ①岩観音下の桜 |
那須町 |
⑪小峰城 |
白河市 |
| ②桜ケ城跡 |
那須町 |
⑫雲月寺 |
泉崎村 |
| ③寺子の桜 |
那須塩原市 |
⑬昌建寺 |
泉崎村 |
| ④遊行柳 |
那須町 |
⑭75号線 |
泉崎村 |
| ⑤白河の関(カタクリ) |
白河市 |
⑮護真寺 |
須賀川市 |
| ⑥庄司戻しの桜 |
白河市 |
⑯横田陣屋 |
須賀川市 |
| ⑦乙姫桜 |
白河市 |
⑰古館の桜 |
須賀川市 |
| ⑧源清桜 |
白河市 |
⑱永泉寺 |
須賀川市 |
| ⑨結城桜 |
白河市 |
⑲長沼城址 |
須賀川市 |
| ⑩南湖 |
白河市 |
|
|
|
|
|
 電話番号が不明でしたのでおよその場所をカーナビにセットして来ましたがはっきりしません。118号線を行ったり来たりしていると小さな看板が出ていました。道を折れて小山に向かって進むと山一面が桜色に染まっていました。もう間違う事はありません。 電話番号が不明でしたのでおよその場所をカーナビにセットして来ましたがはっきりしません。118号線を行ったり来たりしていると小さな看板が出ていました。道を折れて小山に向かって進むと山一面が桜色に染まっていました。もう間違う事はありません。
この季節だけの手作りの標識に従って山道を進み左折、駐車場がありました。4台程の地元の人々の車が止まっています。この周辺は須賀川市長沼地区の桜の名所のようです。撮影している地元の方にうかがうと地震(この影響が果たして真実かどうかは不明ですが)と寒さで今年の花付はかなり悪いそうです。静かな境内に枝を張った風格のある桜の古木に始めて接する私達には十分美しく、極めて新鮮な桜です。 2012.4.24 2012.4.24 |
|
聞くと横田陣屋跡までは歩いて行けるとの事、石段を下ります。見上げる桜の巨木と眼下の参道の桜並木、私達は桜に全身を包み込まれています。柔らかな春の息吹が体一杯に降り注がれて、何とも心の緊張が解きほごされるのです。私達も桜と一体になっているように思えてきます。長く続く桜の参道、往復する間僅か3人ほどの人と出会っただけでした。
桜に満腹になりました。参道を出て横田陣屋跡の桜に向かいます。
|
|
|
|
|
|
 護真寺の長い桜の参道を出て右折、100メートルほど進むと右手に流れるような桜色の塊が見えてきました。 護真寺の長い桜の参道を出て右折、100メートルほど進むと右手に流れるような桜色の塊が見えてきました。
晴れわたった春の午後、のどかに広がる畑の先にそれはありました。細い路地を進みます。あぜ道を抜けて、多分訪れる人の為にあると思われる耕していない畑から流れる桜の姿に見惚れています。訪れる人はまばらです、私達はかなり長く眺めていたので誰も居なくなる時間が持てるのです。地元の人々は馴染みの桜のようで今年の花の様子を見ると直ぐに居なくなってしまうのです。長居したのは私達だけのようです。
本当に美しい姿です。聞けば個人の方の庭に残っていてその方が手入れを続けているとの事です。訪れる桜に会いに来る人々の為にお世話を頂いているとの事、私は清らかなただ咲いている桜の花に手をあわせてしまいました。商業主義と桜とはどこか不釣り合いだと思っているその気分を、この場所では純粋に桜との心の交流を図る事が出来る幸せな場所です。名残は尽きないのですが、車を止めた護真寺まで戻ります、何度も振り返りながら。 2012.4.24 2012.4.24
|
 古館の桜に向かう途中後ろを振り返ります。護真寺から横田陣屋跡の辺りは一面桜色に染め分けられています。静かなたたずまいの普段の景色です。 古館の桜に向かう途中後ろを振り返ります。護真寺から横田陣屋跡の辺りは一面桜色に染め分けられています。静かなたたずまいの普段の景色です。 |
|
|
|
|
地図から判断すると川沿いにあるようなのでうろうろしながら118号線を見当を探して行きます。むせつして小学校が左に出てきて更に進むと川がありました。川を渡って左折して細い道を進むと右に桜の巨木が見えてきました。車が止められないのでぐるっと回って反対側に出ます。車をどこに止めて良いのか分からにので通りがかりの人に尋ねると、目の前の空地がそうだとの事、何の標識もありません。車が一台も止まっていないので大丈夫かと案じながら車を止めて巨木まで歩きます。
護真寺で撮影していた地元の方が、今年の花はあまり良くないと言われていましたが、未だ早かったようです。4分咲き程度かもしれません。それでも私達は古館の桜との邂逅に手に抱えられないほどの満足感を抱いています。この桜の巨木も静寂、野原の一隅に数百年生きて辺りの景色に溶け込んでいます。時が来て花を咲かせただけ、小さな人間の思惑などお構いなしです。それが私にはとても嬉しい事なのです。数百年続いた景色の中に私もお邪魔させてもらい長命のおすそ分けをもらいました。
|
|
|
| |
 これが説明にある不動尊でしょうか。確かに威厳のある桜の巨木です。辺りに目立つような山もないので一際その大きさが目立ちます。誰も居ない巨木の下で遅い昼食を楽しませてもらいます。箸を口に運んでは桜を見上げます、おかずは極めて粗末ですが空にあるもう一つのおかずが贅沢です。暫くお茶を飲んで桜を見て休憩、突然4台の程の車から人が出てきて桜の方向に歩いてきます。カメラを持って桜を撮影する様子に、邪魔になってはいけないと腰を上げます。次に目指すのは長沼城址です。 これが説明にある不動尊でしょうか。確かに威厳のある桜の巨木です。辺りに目立つような山もないので一際その大きさが目立ちます。誰も居ない巨木の下で遅い昼食を楽しませてもらいます。箸を口に運んでは桜を見上げます、おかずは極めて粗末ですが空にあるもう一つのおかずが贅沢です。暫くお茶を飲んで桜を見て休憩、突然4台の程の車から人が出てきて桜の方向に歩いてきます。カメラを持って桜を撮影する様子に、邪魔になってはいけないと腰を上げます。次に目指すのは長沼城址です。 2012.4.24 2012.4.24 |
|
118号を走って途中からパイパスを離れて右方向・長沼に入ります。長沼城址に車を止めて永泉寺に向かいます。途中の橋が架け替え工事だとの事、歩いて行く事にします。城址を出て左に進むと川の向こうに桜の塊が見えてきました。
この寺では何人かの桜見物の人と出会いました。若いサラリーマン風の人が自動シャッターで写真を撮ろうとしている私達に親切にも撮影を買って出てくれました。おまけにチーズと言われてしまい苦笑してしまいました。良い思い出が出来ました。この赤いシダレザクラは八分咲き程度で綺麗にしだれていました。日が傾いてきた感じがします。向こうに見える長沼城址跡に戻りこの旅の終わりの桜とします。 2012.4.24 2012.4.24
|
|
|
|
|
|
|
 長沼城址は3度ほど訪れた事がありますが、桜の季節は初めてです。隣に小学校がある為父兄の車が止まっています。藤沢修平の『蜜謀』のシーンを思い出しながら坂道を登ります。上杉景勝が陣をひいた会津へ向かう街道の要所にあたります。 長沼城址は3度ほど訪れた事がありますが、桜の季節は初めてです。隣に小学校がある為父兄の車が止まっています。藤沢修平の『蜜謀』のシーンを思い出しながら坂道を登ります。上杉景勝が陣をひいた会津へ向かう街道の要所にあたります。
沢山の桜が咲く場所は、中に入ってしまうと却ってそのまとまりが疎らとなり願う撮影が叶いません。見降ろした場所から桜の斜面の目立つ場所を撮影してみました。
眼下に先ほど訪れた永泉寺のシダレ・ザクラのピンクの塊が望まれます。左に会津街道が走っているのが見えます。 2012.4.24 2012.4.24
|
 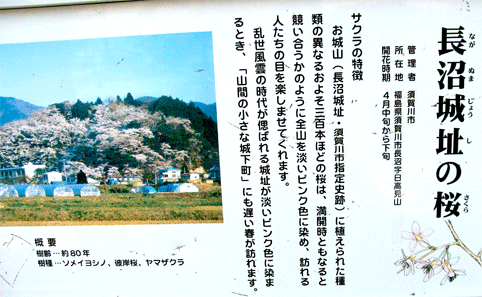 |
 |
 |
 村への帰路118号線から長沼城址の桜を撮影してみました。 村への帰路118号線から長沼城址の桜を撮影してみました。 |
桜の道を辿るの終わり |
長沼城址の桜を見て2日にわたる桜の道を辿る旅は終わりました。春の桜との邂逅でこれ程の数の桜の木と静かに対面した経験が今まで有っただろうかと自問しています。まことに得がたい春の至福の時の連続でした。ただ咲いていてくれた桜の木々と、それを守り我々を迎えてくれた地元の人々に感謝するばかりです。そして各地でいただいた無私のもてなしは私の心を一時ではありましたが素直にしてくれました。
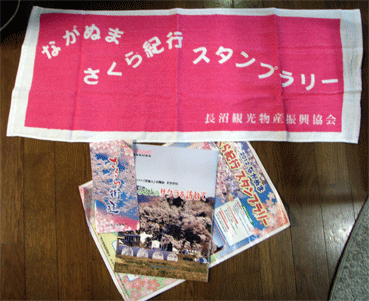 商業主義が感じられない今回の旅の中で、ほほえましい程のサービスがこの長沼のスタンプ・ラリーでした。護真寺の看板の下にプラステイックの箱がありました。そこを開けて紙を引っ張り出してスタンプを押しているのを見て、私も旅の記念にと紙と案内図を出してスタンプを押します。次の横田陣屋から長沼城まで5カ所押してから何気なく紙を見ると記念品贈呈との説明が見られます。どうも地元の人が熱心にそれも数枚の紙に押しているの見て不思議な気がしていたのです。 商業主義が感じられない今回の旅の中で、ほほえましい程のサービスがこの長沼のスタンプ・ラリーでした。護真寺の看板の下にプラステイックの箱がありました。そこを開けて紙を引っ張り出してスタンプを押しているのを見て、私も旅の記念にと紙と案内図を出してスタンプを押します。次の横田陣屋から長沼城まで5カ所押してから何気なく紙を見ると記念品贈呈との説明が見られます。どうも地元の人が熱心にそれも数枚の紙に押しているの見て不思議な気がしていたのです。
私も旅の記念に、説明書に書かれた交換所の一つ『松屋』さんと言うお菓子屋さんを探して町にはいります。村の知り合いのお土産を買う都合もあったのです。落ち着いた城下町ですが、商店街はご多分にもれずさびしい限りです。長沼支庁に車を止めて聞くとすぐ近くとの事、歩いて尋ねます。いかにも由緒ありげなお菓子屋さん、中に入ると珍しいお菓子が並んでいます。景品の交換をお願いすると気分良く応じて頂きました。和菓子屋さんなのですが、工夫した菓子の全てが丁寧に作られているようなのでお土産を箱詰めにしてもらい、私達用にも買い込みました。
|
 |
 |
 松屋さんのお菓子は気が利いて大変抑えた味で美味しかったのです。小ぶりで、観光地のお土産物用のように大げさではなく、普段町の人々が味わっている美味しい菓子に出会えて私達の桜の旅が更に楽しいものになりました。目論見は大当たりだったわけです。 松屋さんのお菓子は気が利いて大変抑えた味で美味しかったのです。小ぶりで、観光地のお土産物用のように大げさではなく、普段町の人々が味わっている美味しい菓子に出会えて私達の桜の旅が更に楽しいものになりました。目論見は大当たりだったわけです。 |
 車を止めた長沼支所への戻り道何の柵もない空地の奥に扉を開けた古い蔵がありました。もしかしたら見物が可能なのかもしれませんが何の看板も無いので遠くから城下町の名残を眺めます。 車を止めた長沼支所への戻り道何の柵もない空地の奥に扉を開けた古い蔵がありました。もしかしたら見物が可能なのかもしれませんが何の看板も無いので遠くから城下町の名残を眺めます。
そろそろ夕暮れがせまってきました。村へ帰るとカーナビをセットして満ち足りた旅を胸に帰路に付きました。 |
|
 村に帰りついて蕎麦を打ちました。今回の旅の想像以上の楽しさの余韻が残っています。庭の梅で作った古い梅酒を飲み、庭のコゴミの天麩羅を食します。冷たく冷えた蕎麦が風呂上がりの火照った体に心地良く、春の夜が更けて行きました。 村に帰りついて蕎麦を打ちました。今回の旅の想像以上の楽しさの余韻が残っています。庭の梅で作った古い梅酒を飲み、庭のコゴミの天麩羅を食します。冷たく冷えた蕎麦が風呂上がりの火照った体に心地良く、春の夜が更けて行きました。 2012.4.24・桜の道を辿る①②③④終わり 2012.4.24・桜の道を辿る①②③④終わり
|
|
09/23/2016
|
|
| 本日カウント数-
|
|
昨日カウント数-
|
Provided: Since Oct.10,2007 |
|

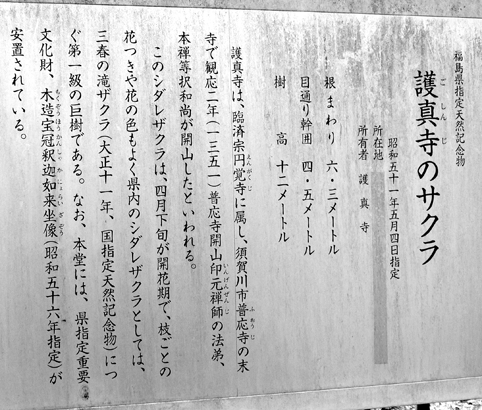



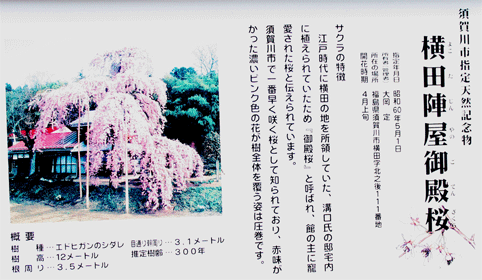

 古館の桜に向かう途中後ろを振り返ります。護真寺から横田陣屋跡の辺りは一面桜色に染め分けられています。静かなたたずまいの普段の景色です。
古館の桜に向かう途中後ろを振り返ります。護真寺から横田陣屋跡の辺りは一面桜色に染め分けられています。静かなたたずまいの普段の景色です。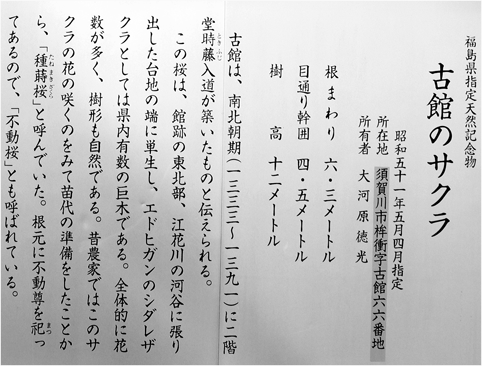
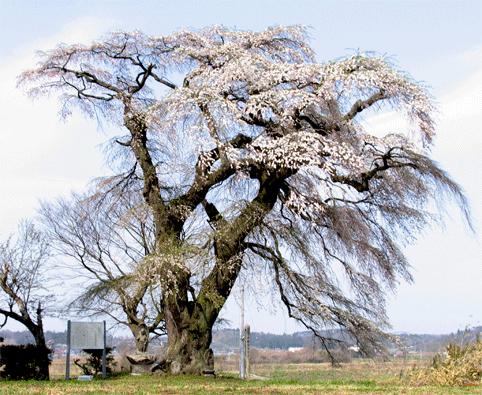


 これが説明にある不動尊でしょうか。確かに威厳のある桜の巨木です。辺りに目立つような山もないので一際その大きさが目立ちます。誰も居ない巨木の下で遅い昼食を楽しませてもらいます。箸を口に運んでは桜を見上げます、おかずは極めて粗末ですが空にあるもう一つのおかずが贅沢です。暫くお茶を飲んで桜を見て休憩、突然4台の程の車から人が出てきて桜の方向に歩いてきます。カメラを持って桜を撮影する様子に、邪魔になってはいけないと腰を上げます。次に目指すのは長沼城址です。
これが説明にある不動尊でしょうか。確かに威厳のある桜の巨木です。辺りに目立つような山もないので一際その大きさが目立ちます。誰も居ない巨木の下で遅い昼食を楽しませてもらいます。箸を口に運んでは桜を見上げます、おかずは極めて粗末ですが空にあるもう一つのおかずが贅沢です。暫くお茶を飲んで桜を見て休憩、突然4台の程の車から人が出てきて桜の方向に歩いてきます。カメラを持って桜を撮影する様子に、邪魔になってはいけないと腰を上げます。次に目指すのは長沼城址です。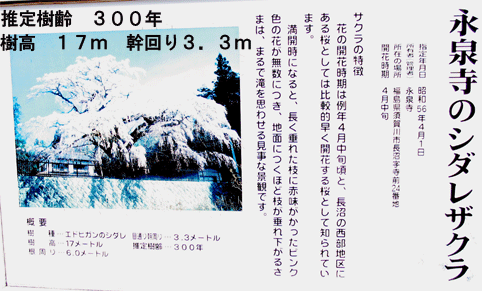


 長沼城址は3度ほど訪れた事がありますが、桜の季節は初めてです。隣に小学校がある為父兄の車が止まっています。藤沢修平の『蜜謀』のシーンを思い出しながら坂道を登ります。上杉景勝が陣をひいた会津へ向かう街道の要所にあたります。
長沼城址は3度ほど訪れた事がありますが、桜の季節は初めてです。隣に小学校がある為父兄の車が止まっています。藤沢修平の『蜜謀』のシーンを思い出しながら坂道を登ります。上杉景勝が陣をひいた会津へ向かう街道の要所にあたります。![]() 2012.4.24
2012.4.24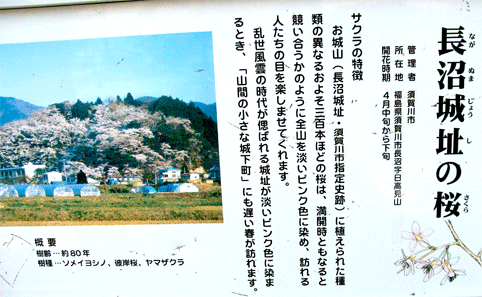


 村への帰路118号線から長沼城址の桜を撮影してみました。
村への帰路118号線から長沼城址の桜を撮影してみました。 村に帰りついて蕎麦を打ちました。今回の旅の想像以上の楽しさの余韻が残っています。庭の梅で作った古い梅酒を飲み、庭のコゴミの天麩羅を食します。冷たく冷えた蕎麦が風呂上がりの火照った体に心地良く、春の夜が更けて行きました。
村に帰りついて蕎麦を打ちました。今回の旅の想像以上の楽しさの余韻が残っています。庭の梅で作った古い梅酒を飲み、庭のコゴミの天麩羅を食します。冷たく冷えた蕎麦が風呂上がりの火照った体に心地良く、春の夜が更けて行きました。![]() 2012.4.24・桜の道を辿る①②③④終わり
2012.4.24・桜の道を辿る①②③④終わり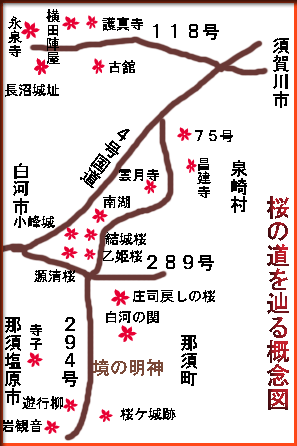 泉崎村の75号線の桜並木を見て4号線に出ます。右折して北上カーナビに導かれて118号線に出ます。結構長く走った印象です。護真寺に車を留めて、歩いて横田陣屋跡の桜を見ます。個人の方が手入れをして見せてくれる美しい枝垂桜に言葉もありません。
泉崎村の75号線の桜並木を見て4号線に出ます。右折して北上カーナビに導かれて118号線に出ます。結構長く走った印象です。護真寺に車を留めて、歩いて横田陣屋跡の桜を見ます。個人の方が手入れをして見せてくれる美しい枝垂桜に言葉もありません。 電話番号が不明でしたのでおよその場所をカーナビにセットして来ましたがはっきりしません。118号線を行ったり来たりしていると小さな看板が出ていました。道を折れて小山に向かって進むと山一面が桜色に染まっていました。もう間違う事はありません。
電話番号が不明でしたのでおよその場所をカーナビにセットして来ましたがはっきりしません。118号線を行ったり来たりしていると小さな看板が出ていました。道を折れて小山に向かって進むと山一面が桜色に染まっていました。もう間違う事はありません。 護真寺の長い桜の参道を出て右折、100メートルほど進むと右手に流れるような桜色の塊が見えてきました。
護真寺の長い桜の参道を出て右折、100メートルほど進むと右手に流れるような桜色の塊が見えてきました。
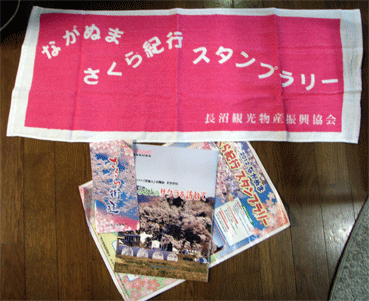 商業主義が感じられない今回の旅の中で、ほほえましい程のサービスがこの長沼のスタンプ・ラリーでした。護真寺の看板の下にプラステイックの箱がありました。そこを開けて紙を引っ張り出してスタンプを押しているのを見て、私も旅の記念にと紙と案内図を出してスタンプを押します。次の横田陣屋から長沼城まで5カ所押してから何気なく紙を見ると記念品贈呈との説明が見られます。どうも地元の人が熱心にそれも数枚の紙に押しているの見て不思議な気がしていたのです。
商業主義が感じられない今回の旅の中で、ほほえましい程のサービスがこの長沼のスタンプ・ラリーでした。護真寺の看板の下にプラステイックの箱がありました。そこを開けて紙を引っ張り出してスタンプを押しているのを見て、私も旅の記念にと紙と案内図を出してスタンプを押します。次の横田陣屋から長沼城まで5カ所押してから何気なく紙を見ると記念品贈呈との説明が見られます。どうも地元の人が熱心にそれも数枚の紙に押しているの見て不思議な気がしていたのです。


