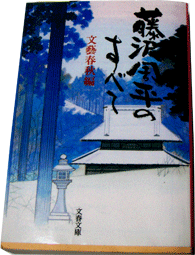 五間川・鶴ケ岡城址を散策したのち郊外の藤沢周平の生家跡地などを回ります。作者の実生活を知る事は小説を読むときいらざる雑音に感じる気がしていま一つ気が乗りません。それでも全ての本を読んでしまい残されていたのは『藤沢周平のすべて(文春文庫)』ただ一つと言う事になってしましました。
五間川・鶴ケ岡城址を散策したのち郊外の藤沢周平の生家跡地などを回ります。作者の実生活を知る事は小説を読むときいらざる雑音に感じる気がしていま一つ気が乗りません。それでも全ての本を読んでしまい残されていたのは『藤沢周平のすべて(文春文庫)』ただ一つと言う事になってしましました。
一つ位は読まない本を残しておきたいと思いずっと手を付けづに居たのですがとうとう我慢が出来ず購入してしまいました。小菅先生と慕われた教員生活、数度にわたる肺結核の手術、夢中で読ませる内容でした。知りたくないと躊躇していたそれらのおおよそを知ってしまいました。ボラインテイアのガイドさんが親切に案内していただくお気持ちに引っ張られて生誕の地を訪れました。
鶴岡市郊外の生家跡への訪問もあたらずさわらずの気分で、作者の生活の痕跡を訪れてみることにしました。それにつけても、どうあがいても新規の作品がないと思いきるのは大変さびしいものです、繰り返し読む以外私に残された道はありません。![]() 2009.09.28
2009.09.28
| 他の藤沢作品の舞台への旅 |
『密謀』をポケットに:1980~81年の新聞連載・当時の会津の太守・上杉景勝、直江兼続の物語
|
深川を訪ねる:沢山の物語の舞台となった隅田川と深川、小名木川・万年橋が特に多い。 |
 |
 |
| 上の写真が現在は小学校となっている旧湯田川中学です。教員室と思われるあたりに人の話し声、今でも子供達と教員達との語り合いが続いているのだと安堵しました。 |
固辞する藤沢周平を説き伏せて平成6年に教え子達が建てた建てた本の形の記念碑です。クリック
|
 |
|
| 上の写真は学校の前から湯田川温泉や藤沢集落方面を望んだものです。藤沢周平がこの道を通って暮らしていたのだとしばし眺めていました。温泉街も掌に入るほどの大きさです、それだけに風景がしっくりと馴染んでけばけばしさが感じられません。湯田川温泉に向かいます。 | |
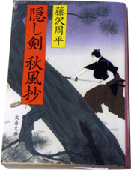
|
|
 |
|
 |
温泉街の外れにある『由豆佐売神社(ゆずさめじんじゃ) 』を案内してもらいまいた。県指定天然記念物の乳イチョウ(瘤となって垂れています)の巨木が 参道右手の空を覆っています。 |
|
 |
|

この茄子が『ただ一撃(文春文庫・「暗殺の年輪」に収録)』に登場して物語をいかにもありそうな話にしています。鶴ケ岡城二の丸、馬見所前広場、藩主・忠勝臨席の剣術試合で清家猪十郎に藩士が負け続け怒気を含んで試合の続行を命じる。兵法指南役・菅沼加賀に再試合を命じる。家老・松平甚三郎が刈谷範兵衛を推挙する。 隠居の範兵衛は嫁の三緒と小茄子の漬物で茶を飲む。歯の欠けた範兵衛が口の中で小茄子を回しながら噛むたびにその表情が可笑しいと三緒がくすくすと笑うのです。ー鶴岡城下から三十丁、民田で栽培される茄子は小ぶりで味が良いー、藤沢周平は植え付け・花の色、漬物の方法まで6行にもわたって生き生きと書いています。私は舅と嫁の微笑ましい情景と作者がこれほどまでに書く茄子に大変興味を持ちました。それがこの民田の小茄子なのです。
|
|
 |
 |
|
|
 |
 ②の道端に看板が建っていました。此処を右に折れて集落の細い道に入ります。空き地にこのような石碑が建っています。藤沢周平が望むと望まざるとに関わらす地元の人々が自らの誇らしげな気持ちを込めたものに思えます。 ②の道端に看板が建っていました。此処を右に折れて集落の細い道に入ります。空き地にこのような石碑が建っています。藤沢周平が望むと望まざるとに関わらす地元の人々が自らの誇らしげな気持ちを込めたものに思えます。 |
 |
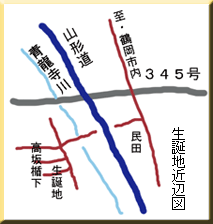 |
|
|
集落の社で、岩上勝之進に家族全員を惨殺された葉津と言う巫女にめぐり合います。春の清流を泳ぎ登る鮠のような娘との会話で窪井信次郎は、人々の期待を裏切って惨めに敗北した心の鬱屈から立ち直るのです。 葉津は、青い槇の生け垣の精、少しもおくしたところのない澄んだ目の娘と書かれています。再会の折りの情景ではー身じろぎもせず、葉津は信次郎を見ている。その姿は紅葉する木木の中で、春先に見た鮠のようにりりしく見えたが、信次郎が近づくと、その目に盛り上がる涙が見えた。-と書かれています。 |
藤沢作品の庄内での物語は、【春秋山伏記】など一部の作品を除いて殆どが侍が主人公です。侍達は多くが鶴ケ岡城をそして五間川が流れる城下を生活の場としています。物語の多くでは鶴岡の城と川がその背景として私達読者に語られます。『暗殺の年輪』の中で海坂藩の町を語っています。
『丘というには幅が膨大な台地が、町の西方にひろがっていて、その緩慢な傾斜の途中が足軽屋敷が密集している町に入り、そこから七万石海坂藩の城下町がひろがっている。城は、町の真中を貫いて流れる五間川の西岸にあって、美しい五層の天守閣が町の四方から眺められる。』
碌高13万8千石(実収21万石)の比較的豊かな海坂藩(庄内藩)の物語は春の桜から始まり冬の雪までの1年の四季おりおりを織り込んで私達を楽しませてくれます。
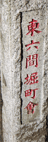 ①海坂藩城下・五間川と深川・五間堀(*番号をクリックすると説明が出てきます)読者である私の想像する楽しみではあるのですが、海坂藩城下を貫通する内川を「五間川」と呼んだのは深川との関連があるのではないのかなどと想像を膨らませています。藤沢作品の殆どの舞台は、侍の物語は鶴岡、市井の人々の物語は江戸・深川です。何かで読んだ記憶が残っているのですが(記憶違いかもしれません)、業界紙の社員の頃深川を頻りに訪れて居たと言うのです。
①海坂藩城下・五間川と深川・五間堀(*番号をクリックすると説明が出てきます)読者である私の想像する楽しみではあるのですが、海坂藩城下を貫通する内川を「五間川」と呼んだのは深川との関連があるのではないのかなどと想像を膨らませています。藤沢作品の殆どの舞台は、侍の物語は鶴岡、市井の人々の物語は江戸・深川です。何かで読んだ記憶が残っているのですが(記憶違いかもしれません)、業界紙の社員の頃深川を頻りに訪れて居たと言うのです。深川での物語は大川に流れ込む小名木川・竪川、それをつなぐ六間堀と五間堀。そこには藤沢作品に登場する市井の人々の暮らす江戸の町が広がっていたのです。五間掘りのへの字の曲りは内川の曲りを思い出させてくれます。そして行き止まりの五間掘りは猿子橋・御籾蔵・御舟蔵で知られた六間掘りより有名ではないので読者に連想されにくいかもしれません。語呂も川を付けたら五間の方がなぜか馴染みます。
②たしか藤沢周平は森川でへの字を描いて行き止まりとなる五間掘りあたりを度々訪れたか、熟知していたと記憶しています。いまでも五間掘りの「への字」の跡は道路に鮮やかに描かれています。後に「彫師伊之助捕物覚え(新潮文庫)」で伊之助が働く「彫藤」は主な舞台の一つですが「五間堀」に沿った三間町にあるのです。私の推理はこの「五間掘」が「五間川」を生み出す一つのヒントになったのではなかろうかと言う想像ーとんでもない勘違いかもしれないと思いながらもーを楽しんでいるのです。藤沢周平は【闇の穴】中「川の辺」で五間川について『実際の川幅は市中で七,八間(それなら七間か八間川となるでしょうが)』と述べているので実際の川幅からだとすると少し無理がありそうです。唯、五間川などと言う名前はどこにでも有りそうな名前でもあります、藤沢作品に出てくるからこれほど気になるのかもしれません。このような空想を楽しむ事は読者に許された特権とお許しください。←写真は深川七福神・深川神明宮(寿老人)六間堀町会の石碑・このすぐ先で五間掘りは東に曲るのです。自分が物語を読む時の参考に、物語の一部と場所の表を作成してみました。申せば、場所を特定することが私にとってそれほど重要でもなくまして目的でもないのです。物語の面白さに根本的な影響を与えるものではありません。とは言ってもそうではなかろうかとその舞台を想像することは、作者と一時共通の経験を味わったような錯覚をいだかせるのです。それは作品を読む私に更なる豊かなプレゼント与えてくれる事になります。鶴岡はたった一度だけの訪問ですので間違いがあるかもしれない事をご理解ください。
| 地図参照 | ||||||||||
主な場所 |
要点 |
|||||||||
| 【霧の朝】中「泣く母」・新潮文庫 | ||||||||||
| 五間川 |  伊庭小四郎は幼き頃寡婦となって家を出た母・美尾に抱かれて頬にその涙を感じます。異母弟の矢口八之丞に代り、五間川の川岸で森雄之助との決闘の場に出向き相打ちとなり大怪我をして暖かい母の膝に抱かれています。いい匂いがした、それは母の匂いでした。母は八之丞の為ですねと言います。いや、違います、母上の為ですと心の中で呟きますが母上と言う言葉が口から出てこないのです。 伊庭小四郎は幼き頃寡婦となって家を出た母・美尾に抱かれて頬にその涙を感じます。異母弟の矢口八之丞に代り、五間川の川岸で森雄之助との決闘の場に出向き相打ちとなり大怪我をして暖かい母の膝に抱かれています。いい匂いがした、それは母の匂いでした。母は八之丞の為ですねと言います。いや、違います、母上の為ですと心の中で呟きますが母上と言う言葉が口から出てこないのです。 |
|||||||||
| 【隠し剣秋風抄】・文春文庫中の短編 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 【隠し剣孤影抄】・文春文庫中の短編 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 【義民が駆ける】講談社文庫 | ||||||||||
| 庄内藩全域 |
庄内の農民たちは移ってくる川越藩の苛烈な年貢をおそれ、領内各地で打ち寄せを開き気勢をあげる。イナゴの群れのごとく江戸に駕籠訴を行う。庄内が農民から武士、商人が一丸となって藩主・忠器(ただかた)のお座りを画する。広範囲にうねりのように突き動かされて動くこれらの人々の一人ひとりを有りそうな話として描き分けた物語。鶴岡を中心とした庄内の各地が物語の場所となっています。 |
|||||||||
| 【闇の穴】中「小川の辺」新潮文庫 | ||||||||||
| 五間川と支流・天神川 |
幼き頃五間川支流の天神川で強情な田鶴は増水に流されそうになった時新蔵の手にすがって助けられた事がある。 |
|||||||||
| 【回天の門】・文春文庫 | ||||||||||
| 鶴ケ岡城下 |
安政6年(1859)江戸の千葉道場で修行した清川八郎は鶴ケ岡に戻り酒井七五三助道場で試合を行う。僅かに早く生まれすぎた天才は幾度か鶴ケ岡にその足跡を残しています。その事を知るだけでこの長大な物語に現実味を与えてくれるのです。 天保義民を題材とした【義民が駆ける】では庄内藩の外交官として辣腕を振るった大山正大夫が、その後藩の中心から遠ざけられて留守居役となって清川八郎と会っている場面が出てきて大変興味をそそられました。江戸・湯島聖堂で感じた清川八郎への親近感が鶴ケ岡城下の町を訪れたことで更に深まった気がします。 |
|||||||||
| 【静かな】中「岡安家の犬」・新潮文庫 | ||||||||||
| 五間川・鶴ケ岡城三の丸 |
八寿は初めて野地金之助の人柄に触れたような気になる。ーアカが帰ってきた。八寿は思いがけなく涙があふれてくる。 |
|||||||||
| 【秘太刀馬の骨】中「秘太刀馬の骨」・文春文庫 | ||||||||||
| 千鳥橋(現・大泉橋)・五間川・染川町 | 
海坂藩の内紛が絡んで近習組頭・浅沼半十郎は江戸から来た石橋銀次郎と共に秘太刀・馬の骨の継承者を探索する。継承されたと思われる矢野道場の門弟を訪ねて立ち合いを続ける。 五間川下流・杉沢新田の堤防の修復を差配する内藤半左衛門の醜聞を、銀次郎は染川町で杵七に酒を飲ませて語らせる。半左衛門は五間川上流の馬場で銀次郎と立ち合う。 長坂権平は旧碌を戻すよう小出帯刀が尽力することで五間川の馬場で銀次郎と立ち合う。寡婦となった美しい兄嫁の家を訪ねる北爪平八郎の姿をあやめ橋(現・千歳橋か,三雪橋では遠すぎる気がする)をわたりしばらく北に歩いた千鳥橋(現・大泉橋)近くの商家で見る。 矢野藤蔵が五間川の千鳥橋で秘太刀を使って赤松を屠ふる。 |
|||||||||
藤沢周平の物語の町鶴岡市を訪ねて①②はいったん終わらせていただきます。初めて訪れた町でいきなり五間川を目にして地に足がつきませんでした。親切なボランテイア・ガイドの方は出来るだけ多く見せようと努めてくれたので雲の上を歩んでいるが如き感覚でした。
酒井家が幕末まで統治したこと、酒田と合わせた経済力、それが培った文化、日本の良かった時代の町がここに残っているように感じたのです。町の暮らしに加えて月山があり、湯殿山があり、羽黒山もあるのです。おおよそ陳腐な観光化をなんとか逃れた自然と町の暮らしーそれこそ見てみたいと思う人は少なくないと思うのですがーを目にする事が出来ます。
小京都・小江戸などとーそれなら本物の京都へ、江戸へと足を向けますー矮小化した町として売り出す必要がない奥深い町に思えました。聞けば、映画『おくりびと』の舞台になった風呂屋さんは鶴岡にあるそうです。日本の良い町に映画の人々が目を付けて撮影に多く来ると聞きました。冬が過ぎ春が来て、月山の残雪が未だ消えない時、再度訪れて藤沢周平の物語の場所を訪ねてみるつもりでおります。
| 本日カウント数- |
昨日カウント数-
|

 この前でボランテイア・ガイドの方にお話をうかがっていると、集落の奥から足を引きずるようにして男の人が歩いてきました。村の家々の事情に詳しいように見えましたので、私は内容が聞こえない場所に移動しました。畑から出てきたというような風情、どこからと聞きます。そんな遠くからと話しかけるその言葉は風貌から想像も出来ない柔らかな庄内弁です。緩やかなリズムと抑えたまろやかな声音でした。
この前でボランテイア・ガイドの方にお話をうかがっていると、集落の奥から足を引きずるようにして男の人が歩いてきました。村の家々の事情に詳しいように見えましたので、私は内容が聞こえない場所に移動しました。畑から出てきたというような風情、どこからと聞きます。そんな遠くからと話しかけるその言葉は風貌から想像も出来ない柔らかな庄内弁です。緩やかなリズムと抑えたまろやかな声音でした。 【玄鳥(文春文庫)】中、大好きな
【玄鳥(文春文庫)】中、大好きな
 天保11年(1840)水野忠邦が主導して発令した三方国替えにより庄内藩は碌高が半減、長岡への転封されることになる。江戸では留守居役の大山正大夫を中心盛んな外交を繰り広げる。
天保11年(1840)水野忠邦が主導して発令した三方国替えにより庄内藩は碌高が半減、長岡への転封されることになる。江戸では留守居役の大山正大夫を中心盛んな外交を繰り広げる。 五間川の桜が散った頃、犬井朔之助は藩主に諫言して脱藩した作間森衛と妹で妻の田鶴の討手を命じられる。幼い頃から兄弟のように育った若党・新蔵が同行を願う。
五間川の桜が散った頃、犬井朔之助は藩主に諫言して脱藩した作間森衛と妹で妻の田鶴の討手を命じられる。幼い頃から兄弟のように育った若党・新蔵が同行を願う。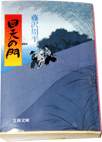 清川八郎を題材にした歴史小説ですので海坂藩の地名は出てきません。10歳で鶴ケ岡城下の手習い所や学塾に通い3年間を過ごす。破門されて家に戻ったのち弘化4年(1847)斉藤元司(後の清川八郎)は鶴ケ岡城下の師・細田安右エ門を訪ね江戸への同行を依頼する。細田の江戸行きが中止となり待ちぼうけを喰った元司は一人江戸へ出奔する。
清川八郎を題材にした歴史小説ですので海坂藩の地名は出てきません。10歳で鶴ケ岡城下の手習い所や学塾に通い3年間を過ごす。破門されて家に戻ったのち弘化4年(1847)斉藤元司(後の清川八郎)は鶴ケ岡城下の師・細田安右エ門を訪ね江戸への同行を依頼する。細田の江戸行きが中止となり待ちぼうけを喰った元司は一人江戸へ出奔する。 近習組の岡安甚之丞は道場仲間と五間川の河原で野良犬を食べた事がある。愛犬のアカが妹・八寿の許婚・野地金之助と仲間の悪ふざけで知らずに一緒に食べる羽目になる。後日三の丸で岡安兵蔵から金之助がアカの代りを探している事を知らされる。
近習組の岡安甚之丞は道場仲間と五間川の河原で野良犬を食べた事がある。愛犬のアカが妹・八寿の許婚・野地金之助と仲間の悪ふざけで知らずに一緒に食べる羽目になる。後日三の丸で岡安兵蔵から金之助がアカの代りを探している事を知らされる。