
 11月12日、所用の為に御殿場市に出かける事にしました。何時もの通り、若干遠回りになりますが、小田原のJA直売所・朝ドレファームで野菜と果物を買いながら向かうことにしました。首都高速に乗ると小雨が車のウインドー・ガラスを濡らす嫌な出立です。東名高速に出ると雨が止んで薄日が差すようになりました。冠雪の富士山との対面が叶うかもしれません、陽の光がこれから始まる旅の楽しさを引き出してくれたようです。
11月12日、所用の為に御殿場市に出かける事にしました。何時もの通り、若干遠回りになりますが、小田原のJA直売所・朝ドレファームで野菜と果物を買いながら向かうことにしました。首都高速に乗ると小雨が車のウインドー・ガラスを濡らす嫌な出立です。東名高速に出ると雨が止んで薄日が差すようになりました。冠雪の富士山との対面が叶うかもしれません、陽の光がこれから始まる旅の楽しさを引き出してくれたようです。
小田原のJA直売所・朝ドレファーム(小田原市成田650-1)には開店20分前に到着、食堂ではその気になりませんが農産物直売所では列に並ぶのを厭いません。箱根の山はうっすらと見えますがお目当ての富士山は雲の中のようです。![]() 2018.11.12
2018.11.12
 |
|
|
|
 由緒のありそうな拝殿でお参りをしてから狛犬を見させてもらいました。台座の文字が殆ど読めなかったので年代や石工名は分かりませんでした。
由緒のありそうな拝殿でお参りをしてから狛犬を見させてもらいました。台座の文字が殆ど読めなかったので年代や石工名は分かりませんでした。
普通の大きさの中々古そうな狛犬です。下目がちにこちらを見つめています。右の狛犬は口の開きが若干大きめなので阿像と思われます。![]() 2018.11.12
2018.11.12
 阿像から吽像を写しました。神社は何度かの手入れがなされたようですが、狛犬の台座は元のままで残っているようにみえます。経年による摩耗で文字を読み取る事が出来ませんでした。バランスの取れた美しい造形に見えます。
阿像から吽像を写しました。神社は何度かの手入れがなされたようですが、狛犬の台座は元のままで残っているようにみえます。経年による摩耗で文字を読み取る事が出来ませんでした。バランスの取れた美しい造形に見えます。 左に置かれた吽像と思われる狛犬、阿吽像共に玉や子供が添えられていないさっぱりした狛犬です。近頃、このような意匠が氏子の人々の希望なのか石工の気持ちなのかは分かりませんが、このような飾りを省いた狛犬が好きになってきています。出だしから良い狛犬と美しい社に出会うことが出来ました。
左に置かれた吽像と思われる狛犬、阿吽像共に玉や子供が添えられていないさっぱりした狛犬です。近頃、このような意匠が氏子の人々の希望なのか石工の気持ちなのかは分かりませんが、このような飾りを省いた狛犬が好きになってきています。出だしから良い狛犬と美しい社に出会うことが出来ました。 |
 |
お神輿が収められていました。小田原の朝ドレファームの9:30分の開店時間に間に合うように急いで大磯ICに向かいました。 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
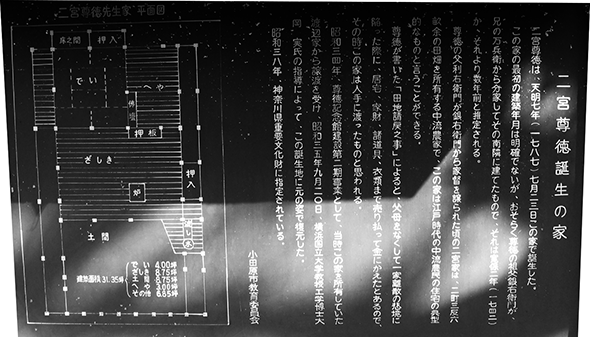
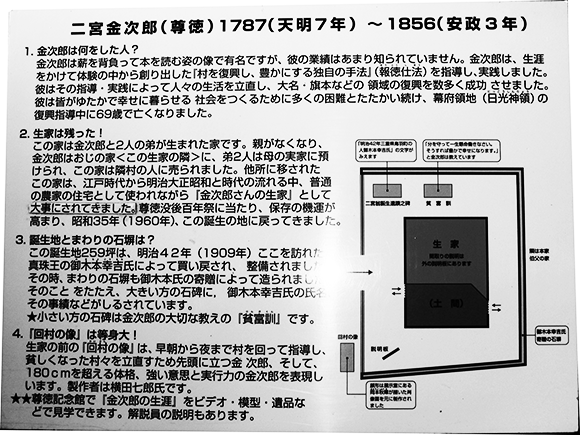
 |
|
|
|
 |
 |
  鳥居を潜って狛犬がすぐ目に入りました、一安心です。お参りをしようと社に近づくと、拝殿の前の梁の両側に木鼻狛犬が飾られています。正面には竜が彫られています。狛犬に加えて木鼻の彫刻を見られてラッキーです。 鳥居を潜って狛犬がすぐ目に入りました、一安心です。お参りをしようと社に近づくと、拝殿の前の梁の両側に木鼻狛犬が飾られています。正面には竜が彫られています。狛犬に加えて木鼻の彫刻を見られてラッキーです。 |
|
 優しい眼差しが印象的な狛犬です、境内に静かに佇んでいる様子が感じられます。神域を騒がせない狛犬に見えます。”昭和3年”と”大嘗祭(推測)”らしい文字が見られますが、石工名は見つけられませんでした。
優しい眼差しが印象的な狛犬です、境内に静かに佇んでいる様子が感じられます。神域を騒がせない狛犬に見えます。”昭和3年”と”大嘗祭(推測)”らしい文字が見られますが、石工名は見つけられませんでした。
右に置かれた狛犬は玉を足下に収めています、阿吽像の区別がはっきり分かりませんでした。![]() 2018.11.12
2018.11.12
 左に置かれた狛犬は子供が添えられています、一層優し気に見えます。左が阿像で、一般的な阿吽像の位置が逆になっているかもしれません。
左に置かれた狛犬は子供が添えられています、一層優し気に見えます。左が阿像で、一般的な阿吽像の位置が逆になっているかもしれません。
 11月の昭和天皇即位の礼(大嘗祭)を記念した狛犬と推測されます。左の狛犬から右の狛犬を見ています。
11月の昭和天皇即位の礼(大嘗祭)を記念した狛犬と推測されます。左の狛犬から右の狛犬を見ています。 |
|
グーグル・マップで狛犬が見られないのは分かっていましたが素晴らしい木彫の社殿を見たいと思い訪れました。 カーナビに従って2車線の車道から集落の中の細い道に入った途端、本当に神社まで行けるのかと不安になりました。地元の方が家の入口に居たので尋ねたところこのまま神社まで行けるとの事で安堵しました。戻る事は不可 木彫が施された素晴らしい佇まいの社は、細い坂道を登ってきた甲斐があったと思わせてくれます。出来れば御殿場へは神社の前から続く旧足柄街道を行こうと思ったのですが、社への細い登り道で意欲が失せてしまいました。 |
|
 説明版に足柄神社に因んで艦名が付けられたと書かれています。
説明版に足柄神社に因んで艦名が付けられたと書かれています。
非合理とは無縁と考えられるイージス護衛艦”あしがら”に足柄神社のお札が祀られていると書かれていました。神社のお札には万が一の状況に臨んで、理屈を超えた力があると思われているようです。
![]() 2018.11.12
2018.11.12
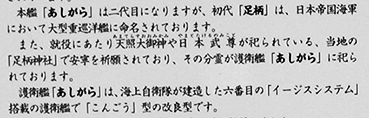
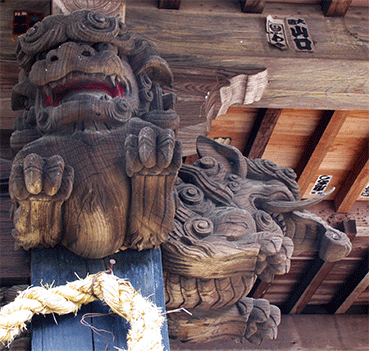 右の木鼻(柱の端の付きだした部分)に飾られた木彫の狛犬は精緻な上に横には獏と思われる像が合わせて彫られています。形も若干大き目です。暫し見上げていました。
右の木鼻(柱の端の付きだした部分)に飾られた木彫の狛犬は精緻な上に横には獏と思われる像が合わせて彫られています。形も若干大き目です。暫し見上げていました。
![]() 2018.11.12
2018.11.12
 左の木鼻狛犬、口の開け方は右とそれ程違いませんので阿吽の別は無いのかもしれません。
左の木鼻狛犬、口の開け方は右とそれ程違いませんので阿吽の別は無いのかもしれません。 正面の龍の彫も見事だなと見惚れてしまいました。
正面の龍の彫も見事だなと見惚れてしまいました。 拝殿でお参りを済ませて後ろの本殿の方に回ってみました。その精緻で豪胆な作りに驚かさされました。
拝殿でお参りを済ませて後ろの本殿の方に回ってみました。その精緻で豪胆な作りに驚かさされました。
これだけの細工をする職人の人々が存在したのだとその事に驚きました。そしてこれだけの社を氏子の人々の力で作った事にも驚かされました。![]() 2018.11.12
2018.11.12
 美しく曲がった形状の梁で紅梁(こうりょう)と呼ばれているようですが、美しく彫刻された3~4本の虹梁が見られます。虹梁と柱との交点に龍や狛犬のような木彫が飾られています。
美しく曲がった形状の梁で紅梁(こうりょう)と呼ばれているようですが、美しく彫刻された3~4本の虹梁が見られます。虹梁と柱との交点に龍や狛犬のような木彫が飾られています。 本殿の左から見ていますが、木彫の複雑な組み合わせに眩暈がしそうです。
本殿の左から見ていますが、木彫の複雑な組み合わせに眩暈がしそうです。 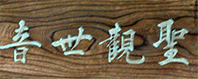 足柄神社の左下に観音堂が見えました。見晴らしの良い台地にあります、訪ねてみました。仏聖観音菩薩(ぶっしょうかんのんぼさつ)を祀ったお堂と書かれていました。 足柄神社の左下に観音堂が見えました。見晴らしの良い台地にあります、訪ねてみました。仏聖観音菩薩(ぶっしょうかんのんぼさつ)を祀ったお堂と書かれていました。 |
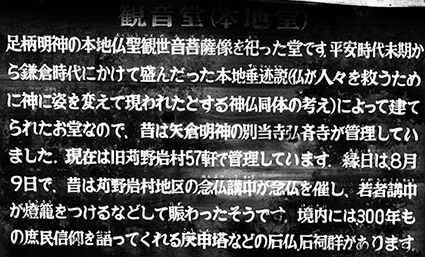 昔読んだ歴史の教科書に出ていた本地垂迹説のサンプルを目にしている事になります。 昔読んだ歴史の教科書に出ていた本地垂迹説のサンプルを目にしている事になります。 |
 観音堂ながら大型の見応えのある木鼻狛犬がありました。こちらは右に彫られた阿像の狛犬と思われます。精緻な彫は本体の足柄神社と同じほどの出来栄えです。
観音堂ながら大型の見応えのある木鼻狛犬がありました。こちらは右に彫られた阿像の狛犬と思われます。精緻な彫は本体の足柄神社と同じほどの出来栄えです。 左の彫られている吽形の木鼻狛犬と思われます。毛をなびかせている様子が大変リアルな木彫です。
左の彫られている吽形の木鼻狛犬と思われます。毛をなびかせている様子が大変リアルな木彫です。 中心部の彫です。下部は柱に直接彫り込んだように見えます。
中心部の彫です。下部は柱に直接彫り込んだように見えます。 |
 |
 |
| 赤い寒椿が咲いています。 |
|
道路からかなり登ってきました。斜面はミカン畑が続きます。富士山は見えないようです。 |
 足柄神社から北に向かうと東名高速とそれに並行して走る246号線に出ました。山間の快適な道路を御殿場に向かって進みます。左の山のかげに富士山が見えてきました。雲がきれたようです。
足柄神社から北に向かうと東名高速とそれに並行して走る246号線に出ました。山間の快適な道路を御殿場に向かって進みます。左の山のかげに富士山が見えてきました。雲がきれたようです。 御殿場市の虎屋の羊羹に立ち寄りました。虎屋の前の道路から目の前に冠雪の富士山が聳えていました。
御殿場市の虎屋の羊羹に立ち寄りました。虎屋の前の道路から目の前に冠雪の富士山が聳えていました。
太宰治の富嶽百景でも書かれているように、非の打ち所のない程整った姿の富士山。私には湖面に写る姿等の絵葉書的な装飾は不要なように思えます。
個人的な好みは生活の中から見る富士山と、山の上から見る富士山の姿です。そしてそこに冠雪があれば申し分ありません。今回は生活の中の富士山を見る事が出来そうです。![]() 2018.11.12
2018.11.12
 御殿場市内の農協の蕎麦屋さんで昼食をとる事にします。車を走らせればどこからも富士山が見られるなど贅沢な事です。
御殿場市内の農協の蕎麦屋さんで昼食をとる事にします。車を走らせればどこからも富士山が見られるなど贅沢な事です。
但し、雲の流れが山を覆えば富士山が姿を消してしまいます。![]() 2018.11.12
2018.11.12
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
 相模国総社 六所神社住所:神奈川県中郡大磯町国府本郷935。首都高速の渋滞を避ける為に、家を早めに出てきました。思ったより都心を抜けるのがスムースでお目当ての小田原のJA特売所・朝ドレファームに早く着きそうなので、大磯の六国神社に寄る事にしました。
相模国総社 六所神社住所:神奈川県中郡大磯町国府本郷935。首都高速の渋滞を避ける為に、家を早めに出てきました。思ったより都心を抜けるのがスムースでお目当ての小田原のJA特売所・朝ドレファームに早く着きそうなので、大磯の六国神社に寄る事にしました。 神社の入り口まで歩いてきました。池には鯉が泳いでいます。後ろは東海道線の下を潜るトンネルを抜けて1号国道方面、駐車場の入り口は右にあります。
神社の入り口まで歩いてきました。池には鯉が泳いでいます。後ろは東海道線の下を潜るトンネルを抜けて1号国道方面、駐車場の入り口は右にあります。 栢山神社:神奈川県小田原市栢山859。住宅街の奥まった場所に神社は鎮座しています。森で囲まれた一帯住宅街の中でも目立つの二宮金次郎の生家から続く道の右手に見えました。車は神社裏手の川の脇のスペースに止めさせてもらいました。のんびりは出来ません。
栢山神社:神奈川県小田原市栢山859。住宅街の奥まった場所に神社は鎮座しています。森で囲まれた一帯住宅街の中でも目立つの二宮金次郎の生家から続く道の右手に見えました。車は神社裏手の川の脇のスペースに止めさせてもらいました。のんびりは出来ません。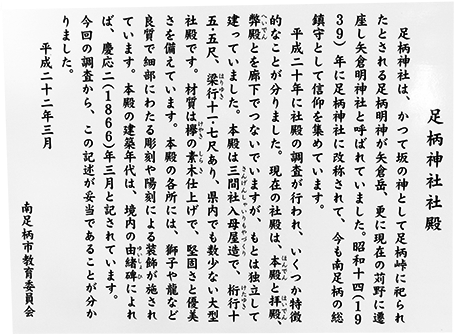 足柄神社住所:神奈川県南足柄市苅野274。
足柄神社住所:神奈川県南足柄市苅野274。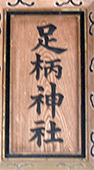 能で先に進む以外ない細い道です。神社の建物が見えるまで、距離は僅かだったと思いますが、その時間の長かった事を思い出すとぞっとします。何度か神社巡りで車をぶつけているので恐怖心が蘇ってきます。境内は車がゆっくりと置ける広さがありました。
能で先に進む以外ない細い道です。神社の建物が見えるまで、距離は僅かだったと思いますが、その時間の長かった事を思い出すとぞっとします。何度か神社巡りで車をぶつけているので恐怖心が蘇ってきます。境内は車がゆっくりと置ける広さがありました。