↑延享二年(乙丑)1745年作の三囲(みめぐり)神社狛犬阿像・石工 和泉屋太郎介
秋葉原のヨドバシカメラに用が出来たので、少し早めに出て映画を見るか狛犬を見るかと思案しました。映画は格別見たいものが無かったので狛犬を訪ねる事にしました。数年前、江戸の七福神に興味を持って、谷中、向島、深川と回りましたが生憎その時は狛犬には興味が無く、果たして有ったのかどうかの記憶も定かではありません。
また、江戸の風情が残る町を歩くことが出来てそれはそれで大変楽しい事になりそうです。時間がそれ程ないので向島と上野を回ってみました。
2015.08.31
 |
|
|
|
三囲神社は江戸の人々に馴染の神社であったようで、江戸の物語にもしばしば登場します。 隅田川をはさんで、対岸には浅草、吉原と江戸の人々の人気の場所がありました。 |
|
竹屋の渡しの名は、浅草山谷堀側にあった船宿「竹屋」に由来しています。昭和五年(1930)、言問橋(ことといばし)の開通によりこの渡しは廃止されました。*墨田区教育委員会の看板より抜粋。 |
|
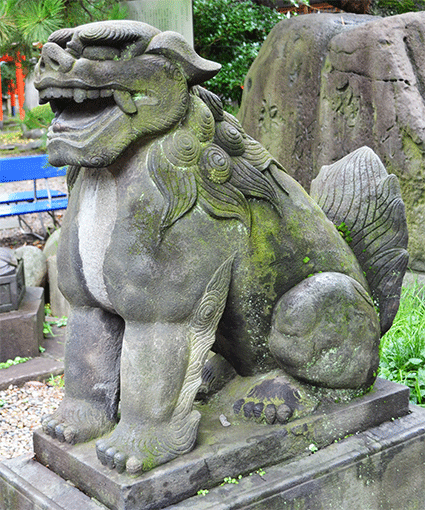 境内にはかなり多くの石像があるのですが、最初に出迎えてくれる狛犬です。表情・体の表現に力の漲る狛犬に見えます。素人の印象ですが違和感なく観賞が出来る狛犬に出会ったようです。
境内にはかなり多くの石像があるのですが、最初に出迎えてくれる狛犬です。表情・体の表現に力の漲る狛犬に見えます。素人の印象ですが違和感なく観賞が出来る狛犬に出会ったようです。
牙をむきだしにして境内を睥睨しいます。
 尻尾が団扇を立てたような意匠が特徴的です。明治以降の作品の多い村の狛犬とは明らかに違います。
尻尾が団扇を立てたような意匠が特徴的です。明治以降の作品の多い村の狛犬とは明らかに違います。
団扇のような尻尾に彫り込みが施されています、江戸らしい派手さと粋が感じられます。どこかすっきりしているようです。
 かなり大きな狛犬です、更に高い台座の上の乗っているので見上げるようです。力を感じる造形に見えました。
かなり大きな狛犬です、更に高い台座の上の乗っているので見上げるようです。力を感じる造形に見えました。
狛犬の知識がないので、村の狛犬とは明らかに異質な形をしていると言うのが第一印象です。どこか洒落れているようにも見えます。![]() 2015.08.31
2015.08.31
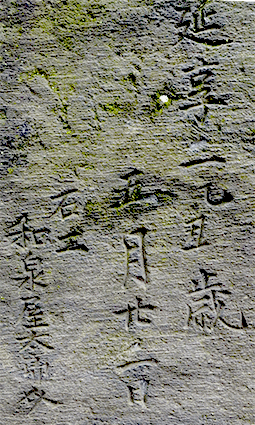 狛犬彫られた文字によれば延享二年(乙丑)1745年作の狛犬のようです。
狛犬彫られた文字によれば延享二年(乙丑)1745年作の狛犬のようです。
石工の”太”以下の名前がはっきり判読できなかったので、”石工 和泉屋”と入れてウイキペデイアで調べたところ、大阪・泉南地方を本拠に全国で活躍した石工集団・泉州石工の事が書かれていました。江戸に移住した人々は八丁堀の石工の組合にも属していたようです。彼等は和泉屋と名乗る者が多かったとも書かれてもいました。その中に”和泉屋太郎介”と言う特定の名前が書かれていました、はっきり判読できませんが、多分この名前はその”和泉屋太郎介”のような気もします(正確ではありませんが)。
村の狛犬とは全く異なる270年前の江戸の狛犬に対面できて幸運でした。![]() 2015.08.31
2015.08.31
 小雨の降る中、赤い前垂れを首から下げた、狐の像が咲き出した芙蓉の花の前に置かれています。江戸の風景らしい印象を受けました。
小雨の降る中、赤い前垂れを首から下げた、狐の像が咲き出した芙蓉の花の前に置かれています。江戸の風景らしい印象を受けました。![]() 2015.08.31
2015.08.31
 |
|
|
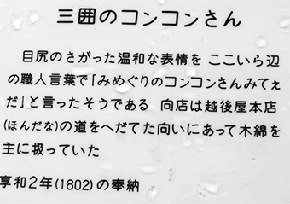 尾篭な話ですが、その多さから”犬の糞”に例えられるほど江戸の町では多量の稲荷があったようです。この”こんこんさん”と呼ばれる優しい感じの狐の像は享和二年(壬戌)・西暦1802年の作品と説明板に書かれています。
尾篭な話ですが、その多さから”犬の糞”に例えられるほど江戸の町では多量の稲荷があったようです。この”こんこんさん”と呼ばれる優しい感じの狐の像は享和二年(壬戌)・西暦1802年の作品と説明板に書かれています。
三囲神社の境内には確か2か所か3か所の稲荷の社があったと思います。![]() 2015.08.31
2015.08.31
 三囲神社のの本殿で参拝の後左手の恵比寿神と大国神の扁額の掛かる鳥居をくぐり参拝をしました。
三囲神社のの本殿で参拝の後左手の恵比寿神と大国神の扁額の掛かる鳥居をくぐり参拝をしました。
入口に小さな狛犬が一対据えられています。
 |
 |
| 文化8年は辛午の年、随分昔の狛犬が残っていたものだと感心しました。胸が大きく強調されています。阿像の顔の左側は経年の為に欠落しているようです。 | |
|
|
 小さな狛犬ですが牙が強調されて迫力があります。
小さな狛犬ですが牙が強調されて迫力があります。 |
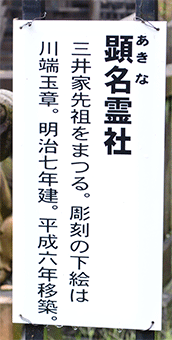 |
| 三囲神社境内を本殿の裏手、隅田川に向かって進むと小さな社があります。小さな社ですがかなり贅を凝らした作りに見えます。 |
 中国製の陶器の狛犬のようです。彼我の文化の違いなのか、余りにも特異すぎてどうも私には馴染めません。 中国製の陶器の狛犬のようです。彼我の文化の違いなのか、余りにも特異すぎてどうも私には馴染めません。 |
 |
 鳥居が三本で立っています。洒落ているのかもしれませんが、個人的な好みからいえば神社には簡素が似合うように思うのです。 鳥居が三本で立っています。洒落ているのかもしれませんが、個人的な好みからいえば神社には簡素が似合うように思うのです。 |
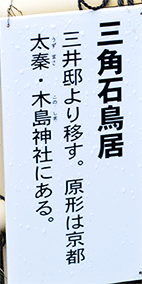 |
小さな稲荷 |
|
江戸の人の稲荷好きを見た気がします。 |
|
隅田川左岸、スカイツリーの傍を通って吾妻橋を渡ることにします。途中の町を散策することにしました。 |
|
佐多稲子旧居跡 |
 街の空を覆うスカイツリーがますます大きく迫ってきます。先端は雲が覆っていました。上ばかり見上げて歩いていたら吾妻橋への道が分からなくなりました。 街の空を覆うスカイツリーがますます大きく迫ってきます。先端は雲が覆っていました。上ばかり見上げて歩いていたら吾妻橋への道が分からなくなりました。 |
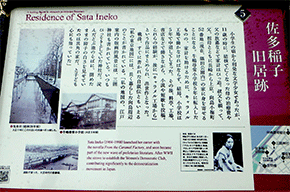 |
|
|
 |
 |
| 通りがかりの人に浅草への道を尋ねると、俺もそっちに向かっているから途中まで一緒に行こうと親切に誘ってくれました。源森橋まで連れて行ってくれました。 |
江戸の物語に確か出てくる、大横川、とか横十間川、とか源森橋とか、嬉しくなってしまいました。後で調べると今の枕橋が元の源森橋のようです。今の新しい源森橋が架かる北十間川です。 |
 |
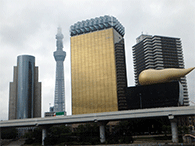 吾妻橋で隅田川を渡ります。振り返ると今歩いてきた向島の風景が見えます。スカイツリーに朝日ビールの金の雲のモニュメント。 吾妻橋で隅田川を渡ります。振り返ると今歩いてきた向島の風景が見えます。スカイツリーに朝日ビールの金の雲のモニュメント。 |
| 途中の路地で道を間違って聞くと、親切丁寧に教えてくれて、お気を付けてっと見送ってくれました。所謂、隅田川の川向うは江戸の雰囲気が強く残っている町です。吾妻橋にやってきました。 |
 浅草に戻ってきました。神谷バーの看板に電気が付いています。昼間からやっているのでしょうか。地下鉄銀座線の浅草駅に向かいました。 浅草に戻ってきました。神谷バーの看板に電気が付いています。昼間からやっているのでしょうか。地下鉄銀座線の浅草駅に向かいました。 |
 |
喧騒の公園内でも、昔はこの辺りは静かな神社でしたが様変わりです。上野東照宮住所:東京都台東区 上野公園9−88 |
|
|
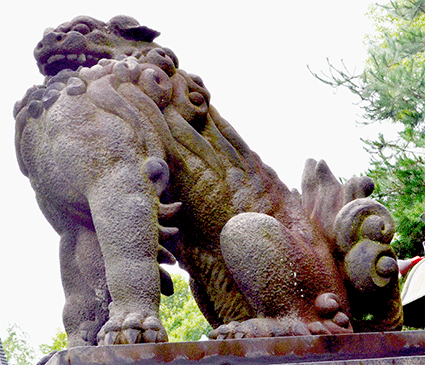 かなり大きな迫力ある狛犬の阿像です。狛犬も大型なのですが台座もかなり高く狛犬は見上げる感じになります。
かなり大きな迫力ある狛犬の阿像です。狛犬も大型なのですが台座もかなり高く狛犬は見上げる感じになります。
更に威風堂々とした印象を高めています。![]() 2015.08.31
2015.08.31
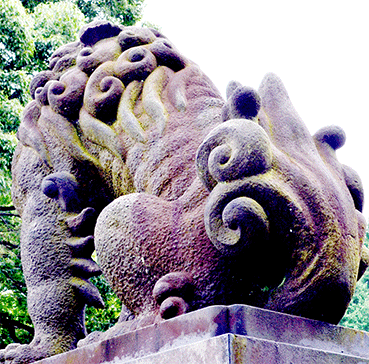 尾は江戸時代の狛犬のように団扇のような形ではありませんがやはり立っています。阿像の後ろ姿です。
尾は江戸時代の狛犬のように団扇のような形ではありませんがやはり立っています。阿像の後ろ姿です。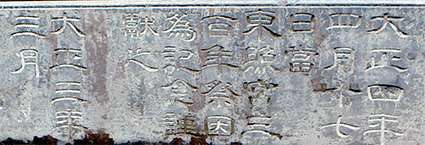 私の理解が正しければ大正3年の作品だと思います。大正4年の東照宮300年を記念して奉納されたようです。
私の理解が正しければ大正3年の作品だと思います。大正4年の東照宮300年を記念して奉納されたようです。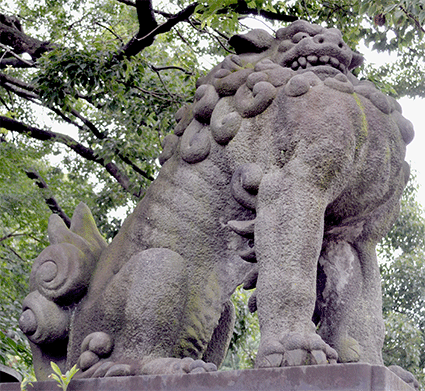 吽像も胸を大きく膨らませて力強い狛犬の姿です。徳川幕府の往時の力を示そうとするような狛犬に見えました。
吽像も胸を大きく膨らませて力強い狛犬の姿です。徳川幕府の往時の力を示そうとするような狛犬に見えました。 東照宮の本殿です。外国の人が途絶えた時を待ってシャッターを押しました。 東照宮の本殿です。外国の人が途絶えた時を待ってシャッターを押しました。 |
 |
|
|
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
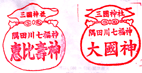 三囲神社住所:墨田区向島2丁目5−17。三囲神社は江戸の古い七福神・
三囲神社住所:墨田区向島2丁目5−17。三囲神社は江戸の古い七福神・ こちらは隅田川に面した鳥居です。たけやの渡しの説明は
こちらは隅田川に面した鳥居です。たけやの渡しの説明は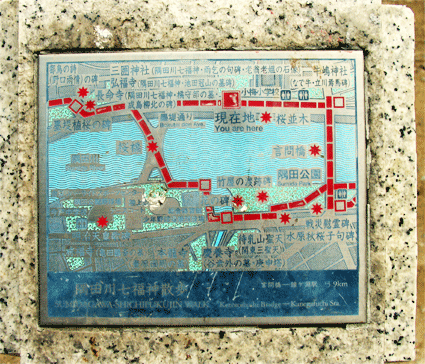 江戸時代浅草から向島へ行くには吾妻橋を通るかこの竹屋の渡しを使うかの方法がありました。竹屋の渡しは、浅草の待乳山(まつちやま・”まっちやま”と聞こえるのですが)聖天宮と、向島の三囲(みめぐり)神社の間を結んでいました。三囲神社の鳥居(*左の説明版で現在地と表示されている)は、堤下の大鳥居と言われて浅草からも見えたそうです。その見事な景色が浮世絵などにも描かれています。
江戸時代浅草から向島へ行くには吾妻橋を通るかこの竹屋の渡しを使うかの方法がありました。竹屋の渡しは、浅草の待乳山(まつちやま・”まっちやま”と聞こえるのですが)聖天宮と、向島の三囲(みめぐり)神社の間を結んでいました。三囲神社の鳥居(*左の説明版で現在地と表示されている)は、堤下の大鳥居と言われて浅草からも見えたそうです。その見事な景色が浮世絵などにも描かれています。 
 境内の裏に小さな稲荷の社がありました。良く見るとこの後ろにも複数の稲荷があるようにも見えます。
境内の裏に小さな稲荷の社がありました。良く見るとこの後ろにも複数の稲荷があるようにも見えます。 三囲神社の境内では沢山の石像や社を見る事ができます。それだけ江戸時代から信仰を集める社だったのかもしれません。上野に向かうことにして、地下鉄の浅草駅に戻ります。
三囲神社の境内では沢山の石像や社を見る事ができます。それだけ江戸時代から信仰を集める社だったのかもしれません。上野に向かうことにして、地下鉄の浅草駅に戻ります。 三囲神社から隅田川方向に進むと、作家・佐多稲子の旧居跡の看板がありました、現在は”すみだ郷土文化資料館”になっています。
三囲神社から隅田川方向に進むと、作家・佐多稲子の旧居跡の看板がありました、現在は”すみだ郷土文化資料館”になっています。 上野公園の動物園の左側にある上野東照宮にやってきました。外国人がかなり多く写真に映り込まないように撮るのはかなり困難でした。
上野公園の動物園の左側にある上野東照宮にやってきました。外国人がかなり多く写真に映り込まないように撮るのはかなり困難でした。 参道には寄進された大きな石灯籠が本殿まで並んでいます。灯篭の左は春の季節になるとボタンの展示場になります。時折雨が落ちてきます。
参道には寄進された大きな石灯籠が本殿まで並んでいます。灯篭の左は春の季節になるとボタンの展示場になります。時折雨が落ちてきます。