2019年の春の寒暖の差が激しい変動が影響したのかツツジの開花が少し遅れているようです。高原の県境の村の一帯は美しいツツジが沢山見られる得難い場所ですが、タイミング訪ねるタイミングが悪く今年は幸運に巡り合っていません。
北国の高原の冷気が影響するのではと思われる透明感のある花弁の色には魅了されてます。
2019.04.23
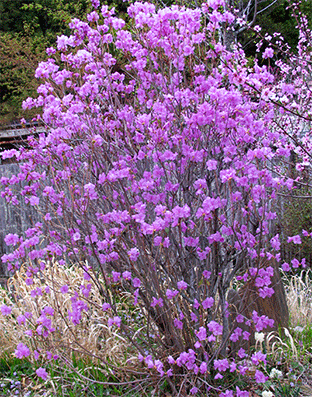 ①サクラゲンカイツツジ:花木に関心を持った最初の頃とは違って今では自分の好みがハッキリとしてきました。ツツジなら、買ってまで植えたいと思うのは女王の如きヤシオツツジ、次いではサクラゲンカイツツジそしてミツバツツジ位になります。このツツジはそれから考えるとサクラゲンカイツツジと言って植木屋さんで買ったに違いないのですが毎年大量の赤紫の花を付けます。どうも違うのではないかと今では不安に思っています。今年もいまでは樹高が2mを超えた枝一杯に花弁を付けてくれました。
①サクラゲンカイツツジ:花木に関心を持った最初の頃とは違って今では自分の好みがハッキリとしてきました。ツツジなら、買ってまで植えたいと思うのは女王の如きヤシオツツジ、次いではサクラゲンカイツツジそしてミツバツツジ位になります。このツツジはそれから考えるとサクラゲンカイツツジと言って植木屋さんで買ったに違いないのですが毎年大量の赤紫の花を付けます。どうも違うのではないかと今では不安に思っています。今年もいまでは樹高が2mを超えた枝一杯に花弁を付けてくれました。
贅沢なのですが、そうなるともう少し抑えた咲き方が出来ないかと言ったくなります。
一応サクラゲンカイツツジと思いますが、違っているのかもしれません。
 ひらひらと風に揺れる大きな花弁はまさにサクラゲンカイツツジです。
ひらひらと風に揺れる大きな花弁はまさにサクラゲンカイツツジです。 ②ヨシノデンドロン:吉野ツツジの一種だと思われます。ひらひらとした花弁が良くて買いましたがこちらも少し花付が良すぎる気がしています。それでも春先の庭の彩に無くてはならないツツジです。
②ヨシノデンドロン:吉野ツツジの一種だと思われます。ひらひらとした花弁が良くて買いましたがこちらも少し花付が良すぎる気がしています。それでも春先の庭の彩に無くてはならないツツジです。
 ③ミツバツツジ:これは多分3代目になるかと思います。やはり赤紫の品の良い花弁を好ましく思っています。街に帰る朝まで開花を待ったのですがほとんどが高原に蕾冷気から身を護るために閉じた蕾を開く事はありませんでした。
③ミツバツツジ:これは多分3代目になるかと思います。やはり赤紫の品の良い花弁を好ましく思っています。街に帰る朝まで開花を待ったのですがほとんどが高原に蕾冷気から身を護るために閉じた蕾を開く事はありませんでした。
次回見る事が出来そうもないので幾つかの枝を切り取って街に持ち帰りました。


4月24日の朝高原の村で切り取ったミツバツツジの蕾は28日街の花瓶の中で綺麗に開きました。
 |
 |
2週間前・4月8日に村を訪れた折の様子をご紹介したツツジの様子です。蕾の付いた枝を切り取って街に持ち帰ったので寂しい開花です。 左・ヤシオツツジ、右・サクラゲンカイツツジ |
|
県境の高原の村はツツジが多く見られる場所です。今では奥山にしか見られないヤシオツツジをはじめとした美しいツツジ類は見事です。今年のツツジの咲き具合の総合ページです。

モクレン下のサクラゲンガイ・ツツジ:何処か咲き方や色合いが、大好きなヤシオツツジに似ているで、街の植木屋さんで花の咲いている時期に目に入るとつい買い込んでしまいます。
何本かを枯らして、現在3本が残っています。全て花の色が赤紫で花びらがひらひら高原の村の風にそよぐものを植えています。
これは木蓮の木の下に植えてあるもので、現在最も気にいっているサクラゲンガイ・ツツジです。
満開の時から少し経って花びらが数枚根元に散らばっていました。![]() 2018.04.11
2018.04.11
 花弁の色と咲き方に風情を感じる木です。最も大好きだったヤシオツツジを枯らしてしまった今では最も気にいっている花です。
花弁の色と咲き方に風情を感じる木です。最も大好きだったヤシオツツジを枯らしてしまった今では最も気にいっている花です。 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 サクラゲンガイ・ツツジによく似たヨシノ・デンドロンが咲き出していました。未だ蕾がかなり多いのですが、それでも極めて艶やかな咲き方です。何故か大変丈夫な木で毎年大量の花を咲かせてくれます。
サクラゲンガイ・ツツジによく似たヨシノ・デンドロンが咲き出していました。未だ蕾がかなり多いのですが、それでも極めて艶やかな咲き方です。何故か大変丈夫な木で毎年大量の花を咲かせてくれます。
![]() 2018.04.11
2018.04.11
寒暖差が大きく動いた今年の気候のせいか県境の高原の村のツツジの開花が遅れているようです。ヤシオツツジと共に最も私の好みに合う3本のサクラゲンカイツツジもやっと花弁が開きだした処です。
2014.04.10
 石際のサクラゲンカイツツジ、冬は多くの時間雪に埋もれていたのではと思われます。
石際のサクラゲンカイツツジ、冬は多くの時間雪に埋もれていたのではと思われます。
元気に優雅な紫色の花を咲かせてくれました。大きな花弁は風に揺れます。3本のサクラゲンカイツツジの中では最も高原の村に似合う花だと思っています。![]() 2014.04.10
2014.04.10
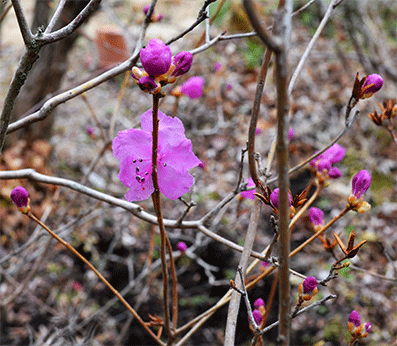 モクレンの古木の下に植え付けたサクラゲンカイツツジはやっと春に目覚めた様子です。花数もまだまだでこれから10日程で満開になるかもしれません。
モクレンの古木の下に植え付けたサクラゲンカイツツジはやっと春に目覚めた様子です。花数もまだまだでこれから10日程で満開になるかもしれません。
咲き出したばかりの澄んだ色合いの花の美しさにはため息が出てきます。![]() 2014.04.10
2014.04.10

モクレン下のサクラゲンガイ・ツツジ:何処か咲き方や色合いが、大好きなヤシオツツジに似ているで、街の植木屋さんで花の咲いている時期に目に入るとつい買い込んでしまいます。
何本かを枯らして、現在3本が残っています。全て花の色が赤紫で花びらがひらひら高原の村の風にそよぐものを植えています。
これは木蓮の木の下に植えてあるもので、現在最も気にいっているサクラゲンガイ・ツツジです。
満開の時から少し経って花びらが数枚根元に散らばっていました。![]() 2018.04.11
2018.04.11
| 06/12/2022 |
| 本日カウント数- |
昨日カウント数-
|