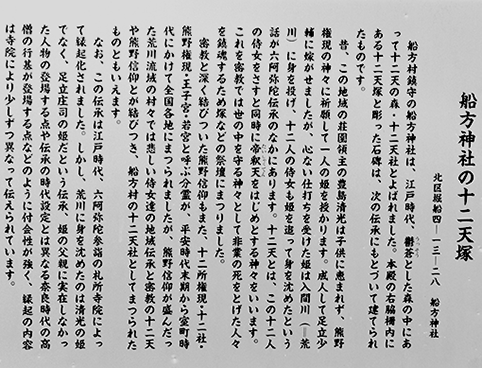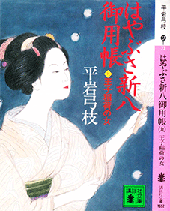明治の狛犬・北区船方神社
暑い一日になりそうで随分迷ったのですが、前から尋ねたかった今戸神社に行くには丁度良いと覚悟を決めて出かけました。浅草から少し離れているのでずっと迷っていたのですが、沖田総司終焉の地であること文政5年の江戸の狛犬が居る事で何時かは思っていました。
仕事のついでなので車で出かけて、今戸神社から仕事先に車を止めさせて貰い都電の一日乗車券を買ってちんちん電車で荒川線沿いの社を回ってみる事にしました。都電の一日乗車券は¥400、乗車時に買うことが出来ます。因みに、通常は距離に関係なく一回の乗車が¥170、私は5回乗り降りしたのでかなりお得でした。
2016.09.06
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
 木陰が広がる社の前に大きな狛犬が奉納されていました。近づいてみると中々良い狛犬に見えました。これは右に置かれた阿像、目に色を入れて修復しているせいか表情が活き活きとしています。
木陰が広がる社の前に大きな狛犬が奉納されていました。近づいてみると中々良い狛犬に見えました。これは右に置かれた阿像、目に色を入れて修復しているせいか表情が活き活きとしています。
流れるような毛の彫や立体的なバランスがとても美しいと思いました。台座の周りを回って年代等を調べようとしたのですが、手掛かりが見つけられませんでした。
どうも台座の一部が破損して修復したようにも見えます。私の記憶では明治の狛犬だったと思います(記憶違いかもしれませんが)。江戸の雰囲気が残っている個性的な造形だと感心しました。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 左に置かれた吽像、狛犬がかなり大型なので存在感がそれだけでも十分な圧力なのに、表情が活き活きとしているので更に圧倒されました。目に色を入れて修復されていることもあるかもしれません。
左に置かれた吽像、狛犬がかなり大型なので存在感がそれだけでも十分な圧力なのに、表情が活き活きとしているので更に圧倒されました。目に色を入れて修復されていることもあるかもしれません。
木陰で覆われた狛犬がこちらを睨んでいるようです。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 |
 |
| 明暗のコントラストの中に狛犬が静かに佇んでいました。その前に野良猫が一匹こちらを見ていました。 |
|
|
|
隅田川 |
|
 今年、平成28年4月5日と4月11日、墨田川の左岸を中仙道から海までジョギングをしました。この写真は4月5日、桜が満開の時、左岸から船方神社と荒川遊園のある右岸を写したものです。その時の様子が思い出されます。 今年、平成28年4月5日と4月11日、墨田川の左岸を中仙道から海までジョギングをしました。この写真は4月5日、桜が満開の時、左岸から船方神社と荒川遊園のある右岸を写したものです。その時の様子が思い出されます。 |
|
|
 |
|
今年の春は隅田川の対岸を左から右の海の方向に向かって走りました。右に薄緑色の小台橋が見えます。 |
 |
 |
| 左は王子方面になります。 |
荒川遊園は定休日、観覧車が止まったままです。 |
 |
 |
|
私はこちらのやってきた早稲田行に乗ります。 |
 |
|
|---|---|
|
|
 |
 |
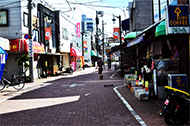 |
|
梶原駅で降りました。都電と交差する道はお馴染みの明治通りで、これが通りがかりに目にする駅だと気付きました。 |
|
 鳥居の先の境内は雑草の原っぱが広がっています。何か懐かしい風景です、私の原体験にもこのような広場でカクレンボをしたりして遊んだ事がありました。
鳥居の先の境内は雑草の原っぱが広がっています。何か懐かしい風景です、私の原体験にもこのような広場でカクレンボをしたりして遊んだ事がありました。
心が束縛から解放される懐かしい社に巡り合いました。本殿の前に置かれた狛犬が小型ながらとても見応えのある姿で迎えてくれました。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 |
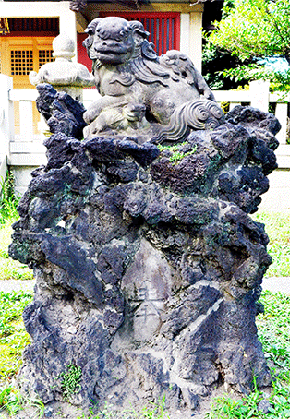 |
|---|---|
|
|
 |
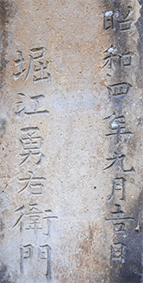 |
|
昭和4年に堀江さんと言う方が奉納したようです。 |
 |
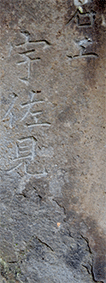 |
|
石工の人の名前ですが”宇佐見”は見えるのですが下の方は欠落しているようです。 |
懐かしさを感じると同時に、せわしない日常と一味違う穏やかな時間を楽しむ事が出きるのかもしれません。 |
|
都電王子駅から王子稲荷
 |
 |
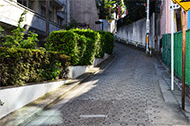 |
|---|---|---|
| 都電早稲田行に乗り王子で降りました。王子稲荷に向かいます。高い横断歩道の上から早稲田に向かう都電を見ています。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
|---|---|
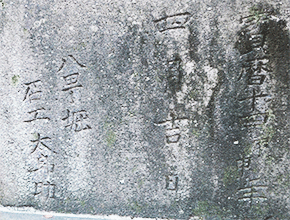
関八州の稲荷神社の総本山、随分古い狐の石像が残っていました。優雅で品のある姿の狐に見えます。 ”宝暦14年(甲申・1764年)・八丁堀 石工 太郎助”のような気がします(郎が正確には判読できませんので確かではありません)。もしそうだとすると向島・三囲神社の素晴らしい狛犬を延享二年(乙丑)1745年に彫った和泉屋太郎介に関係しているのでしょうか。 そういえば優し気な表情の狐で有名な三囲神社の”こんこん”さん・享和二年(壬戌)・西暦1802年を思い出してしまいました。この王子稲荷の狐も優しい表情で大きさも一般的な狐より大きい様な気がします。余り知識の獲得に深入りすると石像の美しさを鑑賞する気分がそがれる気がするので、知識の浅い素人の推測をちょっとだけ楽しみました。 |
|
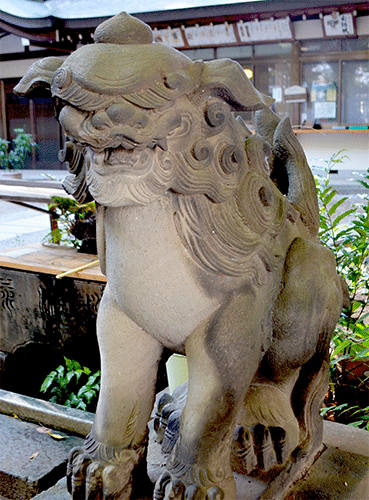 平日は正面から石段を登ることが出来ないようです。狛犬の前面に柵があるため正面から写真を撮る事が出来ません。年代や石工の人の名前も見る事が出来ませんでした。
平日は正面から石段を登ることが出来ないようです。狛犬の前面に柵があるため正面から写真を撮る事が出来ません。年代や石工の人の名前も見る事が出来ませんでした。
大変見応えのある素晴らしい狛犬に見えます。こちらは口を大きく開けて居る事や頭に擬宝珠を載せて居る事から江戸時代の作りで阿像ではないかと思いました。写真は阿像の体の向かって右側から撮っています。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 阿像を向かって左側から撮っています。素晴らしい彫りだと思いました。鋭利な彫りが毛の流れるような躍動感をうみだしていて、更に下半身がしっかりとして安定感を感じさせます。
阿像を向かって左側から撮っています。素晴らしい彫りだと思いました。鋭利な彫りが毛の流れるような躍動感をうみだしていて、更に下半身がしっかりとして安定感を感じさせます。 頭に角状の突起が見られるので吽像ではないかと思いました。流れるような毛の線の彫りは見事だと目を近づけてしみじみと楽しみました。
頭に角状の突起が見られるので吽像ではないかと思いました。流れるような毛の線の彫りは見事だと目を近づけてしみじみと楽しみました。
柵があるので丁度良い距離から写すことが出来ませんでした。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 吽像と思われる左側の狛犬の左側面から撮りました。頭の角状の突起がはっきりと確認できます。
吽像と思われる左側の狛犬の左側面から撮りました。頭の角状の突起がはっきりと確認できます。 社殿側・狛犬の吽像の後ろから阿像を望んでいます。尻尾の炎が足り登るような造形に感心してしまいました。
社殿側・狛犬の吽像の後ろから阿像を望んでいます。尻尾の炎が足り登るような造形に感心してしまいました。 |
 |
|---|---|
| 石組の下の彫りも中々見事です。 | 社側から入り口の門の方向を写しました。 |
 |
 |
 |
|---|---|---|
| 社の右の看板 | 願掛けの石の祀られた末社 | お稲荷さんの本場の沢山の鳥居 |
 |
 |
 |
| これが狐の穴の跡でした | 狐の穴跡から下を見ると洗濯物がぶら下がったマンションが見えます。神の場所と俗の場所が混在していて良いなと思いました。 |
狛犬まで戻って装束榎のあった方向を見てもその面影はありませんでした。 |
 社殿は11代将軍・徳川家斉(在位1787年~- 1837年)が寄進したものだそうですが、日光東照宮を思わせる豪華な作りです。お参りをさせてもらいました。
社殿は11代将軍・徳川家斉(在位1787年~- 1837年)が寄進したものだそうですが、日光東照宮を思わせる豪華な作りです。お参りをさせてもらいました。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 登ってきたいなり坂を下りて正面の門から狛犬を遠望しようとしましたが、幼稚園が終わって子供たちが出てきたので私も次の装束稲荷に向かいました。
登ってきたいなり坂を下りて正面の門から狛犬を遠望しようとしましたが、幼稚園が終わって子供たちが出てきたので私も次の装束稲荷に向かいました。 |
|
|---|---|
|
|
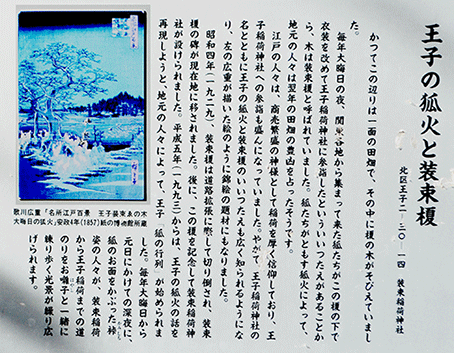 毎年大晦日の夜、関東各地から集まった狐が装束榎の下で衣装を改めて王子稲荷に参拝をするという伝承が江戸時代からありました。平岩弓枝の”王子稲荷の女”の物語の発端となる話です。
毎年大晦日の夜、関東各地から集まった狐が装束榎の下で衣装を改めて王子稲荷に参拝をするという伝承が江戸時代からありました。平岩弓枝の”王子稲荷の女”の物語の発端となる話です。
この稲荷はその装束榎が道路拡張で切り倒された(多分少し線路よりの北本通りにあったのではないでしょうか)為に建てられた記念碑が移された場所だと書かれていました。 ![]() 2016.09.06
2016.09.06
 |
 |
|
|
 小さな社でお参りをしました。仕事の合間に都電に乗って狛犬を巡る散歩は結構楽しいものでした。その感謝を込めて頭を垂れました。
小さな社でお参りをしました。仕事の合間に都電に乗って狛犬を巡る散歩は結構楽しいものでした。その感謝を込めて頭を垂れました。
王子駅に戻り都電に乗って車を止めた仕事先に戻ることにします。![]() 2016.09.06
2016.09.06
 |
 |
|---|---|
私は王子駅から三ノ輪行きに乗って車を止めた場所に戻ります。丁度一番前の座席に座れたので運転手さんの目線で景色を眺める事が出来ました。早稲田行の都電とすれ違いました。 |
|
暑い一日だったので神社まで歩くのは大汗をかいていしまいましたが、冷房の効いた都電の中で一息つきました。ゆっくりと走る都電の景色は景色の流れが遅いのでじっくりと楽
しむことが出来ました。軒先をかすめるような感覚もとても心地よい思い出となりました。都電・梶原駅の前というか駅の中というか、本屋さんとタバコ屋さんだと思いますが、お店です。手前の駅の柵から手が届きそうな距離です。懐かしい昔の東京がありました。
もし機会が有れば又利用したと思いました。因みに都バス・都営地下鉄とこの都電が一日乗り放題と言いうチケットがるそうです。次はそれを利用するのも楽しそうです。
都電にのって狛犬を巡る ① ② 終わり
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|