
志木市・羽根倉浅間神社・獅子山 明治13年(1880年)推定*(禁)転用
2019年2月12日・19日、週一回の土手のジョギングからの帰路、川の反対側から分岐して流れる新河岸川沿いの街の狛犬を訪ねて見る事にしました。そして2月25日又その先を訪ねる事にしました。
日光御成街道沿いの川口市で思いもしない素晴らしい江戸の狛犬を沢山見る事が出来た事がそう思ったきっかけです。江戸時代、江戸の隅田川・箱崎河岸から川越までの物資や人を運んだ(人は上流の浅草・花川戸河岸)川越舟運(しゅうん)の道筋である新河岸川沿いの街ならもしかしたらと思ったのです。明治の作ながら迫力のある素
晴らしい彫りの下鶴間氷川神社獅子山と村社・針ヶ谷氷川神社の江戸の狛犬(共に新河岸川沿いの富士見市の神社)の印象が強く残っていた事もあります。
因みに、川越舟運の話は私の愛読する本の一つ佐伯泰英の鎌倉河岸捕物控の中の第4巻”暴れ彦四郎”にも出てきます。川越を訪れる為に船に乗った主人公の一人”しほ”の描いた不思議な人物の姿から事件が解決に向かいます。”しほ”が川越藩に関係することからこの物語にはしばしば川越舟運が舞台に登場します。
2019.02.25
2019年2月25日の新河岸川沿いの狛犬巡り掲載分順路
①志木市・下の宮氷川神社⇒天神社⇒宿氷川神社 ②志木市・羽根倉浅間神社⇒館氷川神社⇒水子氷川神社⇒敷島神社 ③富士見市・上水子ノ氷川神社(貝塚公園)⇒諏訪神⇒氷川神社 ④富士見市・上南畑神社⇒阿蘇神社 ⑤富士見市・榛名神社⇒ふじみ野市・八幡神社 ⑥川越市・羽根倉浅間神社(志木市・2回目)⇒川越八幡神社⇒愛宕神社 ⑦川越市・仙波氷川神社⇒川越氷川神社
2019.02.25
|
日光御成街道やその脇街道の街には嬉しい事に江戸の狛犬がかなり残っています。無駄な飾りを省いた粋な江戸の職人らしい(地元の石工を含めて)狛犬が多く見られるのも大変嬉しい事です。◉ 埼玉県の狛犬マップ |
2019年2月25日、週一度の土手のジョギングに出かけました。帰路は走りながら良さそうな花を見つけると土手を降りて菜の花と枯れた野草の茎を摘みました。春のような陽気です。ナップザックに丈の長い菜の花を背負って走るので人目に付かないかと気が気ではありませんでした。
走り終えて駐車場に戻ってから、ここまで来たのだからと橋を渡って先週訪ねた川向こうの羽根倉浅間神社を再度見て見たいと思いました。 前回見落とした獅子山の年号を探してみたいと思ったのです。天気予報では雨と言われていましたが日差しが差す日和です。車で10分も走れば羽根倉浅間神社まで行けるのです。2回目の羽根倉浅間神社になります。
2回目の羽根倉浅間神社は天気も良い事もありゆっくりと狛犬の年号を探しそれらしいものが見つかりました。すっかり気を良くして余りも遠いのと、観光地だという事で躊躇していた川越市の神社に行って見る事にしました。
2019.02.25
 富士塚には登ってはいけないようなので道路の斜面を登ってみました。菜の花が咲く土手からは眼下に富士塚、社殿も見えます。神社の後方が土手になります(画像の左方向)。
富士塚には登ってはいけないようなので道路の斜面を登ってみました。菜の花が咲く土手からは眼下に富士塚、社殿も見えます。神社の後方が土手になります(画像の左方向)。
この神社は新河岸川ではなく本流の隅田川上流部になります(江戸時代には戸田川とか荒川とか呼ばれていたようです)。富士塚作りの資材の運搬には新河岸川より恵まれていたと思われます。
明治13年に最初に富士塚を作ったのがこの土手の向こうの河川敷になります。![]() 2019.02.25
2019.02.25
 |
一番上の二文字が確かではありませんが、崩し字で”明治”と書かれているのではないかと思われます。全ては推測ですので間違っている場合もあります。 |
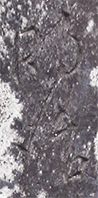 上の2文字を拡大してみました。崩し字辞典で見ると明”と推定した文字の右側部分はかなり”明”に近いようです。そして明治一三年だとすると、説明板によれば最初の富士塚を河川敷に作った年になります。素人の推定ですが狛犬の作られたのも富士塚と同じ明治13年と推定しました。間違いが判明次第訂正いたします。 |
| 獅子山に嵌め込まれた石に刻まれた奉納者の名前の左端に年号らしき文字が見えました。草の隙間から見て見ると”xx一三年四月”らしき文字ではではと推定しました。最後の四月はかなりの可能性で合っていると思いますが他の文字は確かではありません。 |
余り細事に拘ると狛犬を見たり神社を参拝する楽しみが減じるので一応これで納得しようと思っています。それはそれとして推理する楽しみをたっぷりと堪能しました(事実は推定と違っている可能性が高いと危惧していますが)。
 |
 |
|
|
阿像吽像共に下の位置に子供が彫られています。阿像は分かるかもしれませんが、手前の吽像の子供は保護色になってしまって判別できないかもしれません。 |
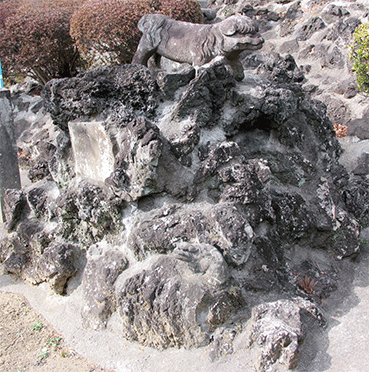 |
 |
| 驚いたことに左に置かれた吽像にも子供が添えられていました。阿吽像共に子供が添えられている獅子山は余り目にしたことがありません。2回目はゆっくりと見られたので、思いもしないおまけがついてきました。 |
東京ドーナッツ工場でドーナッツを買う |
|
 川越に向かうには国道254号線を通る事になります。 川越に向かうには国道254号線を通る事になります。 |
 |
|
|
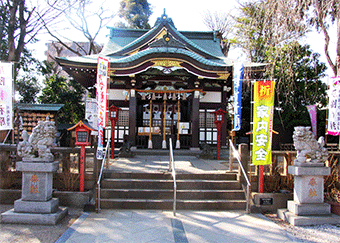 |
|
| 八幡神社住所:川越市南通町19−3 |

![]() グーグル・マップでは駐車場の存在が不明だったのですが町中の太い道に神社入り口の看板がありました。すれ違いが少し窮屈ですが境内の鳥居への道を進むと参詣者用の駐車場がありました。
グーグル・マップでは駐車場の存在が不明だったのですが町中の太い道に神社入り口の看板がありました。すれ違いが少し窮屈ですが境内の鳥居への道を進むと参詣者用の駐車場がありました。
川越市の町中の神社です、参詣の人が途切れません。狛犬を見るのも写すのも参詣の人を写さないようにしなくてはなりません。神社は非常に豪華な作りです。![]() 2019.02.25
2019.02.25
 拝殿の前に古そうな狛犬が奉納されています。右の阿像と思われます、通常の大きさの狛犬です。
拝殿の前に古そうな狛犬が奉納されています。右の阿像と思われます、通常の大きさの狛犬です。
経年の為にかなり摩耗が進んでいるようで顔の様子などははっきり見る事が出来ません。![]() 2019.02.25
2019.02.25
 参拝の人の途切れた時を待って阿像から吽像を写しました。位置関係や台座なども最初の状態と少し違っているかもしれません。
参拝の人の途切れた時を待って阿像から吽像を写しました。位置関係や台座なども最初の状態と少し違っているかもしれません。
全体の姿に違和感がありませんがかなり簡素な彫です。![]() 2019.02.25
2019.02.25
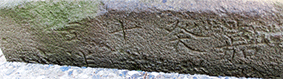 左の吽像の台座の下の一部の文字が見えます。半分ほどは石畳に隠されて見る事が出来ません。細事に拘ると神社を巡り狛犬を見る楽しみがなくなるので極力避けているのですが、このような事を推理する楽しみは捨てがたいと思っています。自分の楽しみに文字を推理してみました。
左の吽像の台座の下の一部の文字が見えます。半分ほどは石畳に隠されて見る事が出来ません。細事に拘ると神社を巡り狛犬を見る楽しみがなくなるので極力避けているのですが、このような事を推理する楽しみは捨てがたいと思っています。自分の楽しみに文字を推理してみました。
”嘉癸十”の3文字ははっきりと読めます。江戸時代”嘉”の付く年号は嘉永だけだと思います。そして干支の癸丑(ミズノトウシ)の癸だけを書いたとすると嘉永六年ではないかと推測しました。嘉永年間は嘉永七年(1855年)で終わりとなるので”十”は月ではないかと推理しました。狛犬を見られただけでも楽しい事なのにクイズを楽しむおまけまで付いています。間違っている可能性が高い事をお許しください。
2019.02.25
 左に置かれた吽像と思われる狛犬です。こちらも経年でかなり摩耗していますが優し気な顔の表情は見て取れます。江戸の狛犬らしいことは素人の感で推測できますが果たして事実はどうでしょうか。
左に置かれた吽像と思われる狛犬です。こちらも経年でかなり摩耗していますが優し気な顔の表情は見て取れます。江戸の狛犬らしいことは素人の感で推測できますが果たして事実はどうでしょうか。 |
 |
|
|
 |
|
| 仙波愛宕神社:川越市富士見町33−1 | |
 |
 |
|
|
|
|
| 街中の神社では少し忙しい感じでお参りをしたので、やっと馴染んだ静かな境内に来て少しほっとしました。時間にも駐車にも他人にも気遣いをする事は無用です。神社への坂道から仙波河岸公園を見下ろしています、池が春の光を受けて輝いています。 |  |
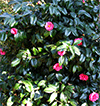 坂道にはツバキが咲き水仙の花が芳香を放っていました。春が近い事を実感します。 坂道にはツバキが咲き水仙の花が芳香を放っていました。春が近い事を実感します。 |
 |
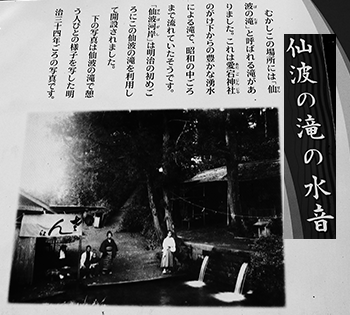 |
 |
 |
|
|
|

 愛宕神社の鳥居の下に極めて特異な意匠の小型の狛犬が置かれていました。台座に年代等が彫られていないか探してみました、辛うじて七らしき文字が見えましたがそれ以外は判然としません。
愛宕神社の鳥居の下に極めて特異な意匠の小型の狛犬が置かれていました。台座に年代等が彫られていないか探してみました、辛うじて七らしき文字が見えましたがそれ以外は判然としません。
石を抱いたような意匠に見えます。彫りはかなり簡素です。これは右に置かれた吽像と思われます。風変りの狛犬を見て福島県境の神社時折見かける鉄砲玉のような狛犬を思い出しました。風変りな形という点では甲乙つけがたしかもしれません。![]() 2019.02.25
2019.02.25

 右の吽像から阿像を写しています、日差しが西に傾いて来て影が出てしまいました。台座には”當””別当(?)””先達(?)””坊賢海”など推測を交えて判じ物のような文字が刻まれています(読み違っているかもしれませんが)。別当寺の事が書かれているかもしれませんが、ハッキリと分かりません。余り、細事に拘ると神社の狛犬を見る楽しさが減じるので、今、目の前にある素晴らしい社を見回す事にしました。
右の吽像から阿像を写しています、日差しが西に傾いて来て影が出てしまいました。台座には”當””別当(?)””先達(?)””坊賢海”など推測を交えて判じ物のような文字が刻まれています(読み違っているかもしれませんが)。別当寺の事が書かれているかもしれませんが、ハッキリと分かりません。余り、細事に拘ると神社の狛犬を見る楽しさが減じるので、今、目の前にある素晴らしい社を見回す事にしました。 左に置かれた阿像と思われます。一般的な阿吽の位置が逆に置かれているのかもしれません。何故か、この組み合わせも福島県南地方でしばしば目にする意匠です(全く関係の無い事ですが)。
左に置かれた阿像と思われます。一般的な阿吽の位置が逆に置かれているのかもしれません。何故か、この組み合わせも福島県南地方でしばしば目にする意匠です(全く関係の無い事ですが)。
自然石と思われますが、こちらの石はあたかも玉のごとく丸い形状をしています(もしかすると若干の加工が加えられているのかもしれません)。石工の人はどこからこのような特異な意匠を産み出したのか(伝聞なのか独創なのか)、極めて不思議な狛犬に出会って楽しい時間を過ごせました。もしかしてこの地域で再度類似の狛犬に出会えるのでしょうか。![]() 2019.02.25
2019.02.25
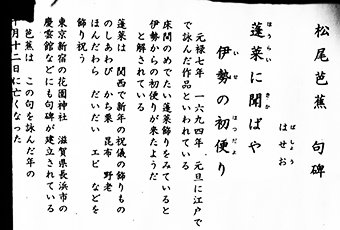
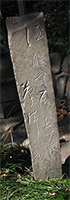 鳥居の横には流れるような美しい彫りで刻まれた芭蕉の句碑が奉納されていました。特異な容貌の狛犬で白河の鉄砲玉のような狛犬を思い出したのですが、彼の地の狛犬を巡る旅はまさに芭蕉の奥の細道の足跡をたどる道でもあります。脈絡もなく白河の狛犬と芭蕉の足跡を思い出させてくれました。まさに犬も歩けば棒に当たるの感がしました。
鳥居の横には流れるような美しい彫りで刻まれた芭蕉の句碑が奉納されていました。特異な容貌の狛犬で白河の鉄砲玉のような狛犬を思い出したのですが、彼の地の狛犬を巡る旅はまさに芭蕉の奥の細道の足跡をたどる道でもあります。脈絡もなく白河の狛犬と芭蕉の足跡を思い出させてくれました。まさに犬も歩けば棒に当たるの感がしました。![]() 2019.02.25
2019.02.25

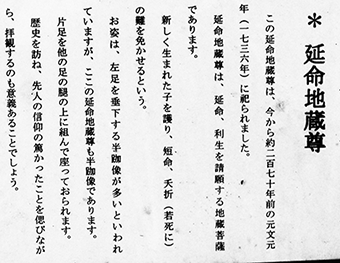 神社から戻る道を左に回り込むと高い石像の延命地蔵尊が祀られていました。元文元年(1736年)に祀られたと書かれています、天文学的な数の祈りや願いを御聞き届けになった事でしょう。
神社から戻る道を左に回り込むと高い石像の延命地蔵尊が祀られていました。元文元年(1736年)に祀られたと書かれています、天文学的な数の祈りや願いを御聞き届けになった事でしょう。 愛宕神社に向かうときは気が付きませんでしたが、神社への登り口に早咲きの桜が蕾を開かせていました。心が緩んで来るような暖かい陽気と桜の花びら、春の入り口に立ったような気分です。
愛宕神社に向かうときは気が付きませんでしたが、神社への登り口に早咲きの桜が蕾を開かせていました。心が緩んで来るような暖かい陽気と桜の花びら、春の入り口に立ったような気分です。
多分まだまだ春の訪れるまでには幾夜かの冬を過ごすことになるでしょう。
桜の花に後ろ髪を引かれますが、直ぐ隣り合う氷川神社まで歩きます。![]() 2019.02.25
2019.02.25
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
 埼玉県の狛犬スライド
埼玉県の狛犬スライド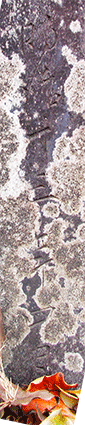 左の年号らしく部分だけを別に画像から切り取ってみました。
左の年号らしく部分だけを別に画像から切り取ってみました。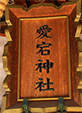
 愛宕神社は鳥居まで緩やかな坂を登ります。鳥居の下に狛犬が置かれています。
愛宕神社は鳥居まで緩やかな坂を登ります。鳥居の下に狛犬が置かれています。