那須神社(金丸八幡宮)昭和9年(1934年)・石工 笹沼周(?)大・ *禁・無断転載

2018年12月28日の夜から県境の村へ向かう予定でしたが仕事が忙しく31日の朝出発することになってしまいました。午後3時頃までに村に到着すれば良いので、途中東北道の矢板ICで降りて那須の神社を訪ねて見る事にしました。
宇都宮インターを過ぎて矢板インターに向かって東北道を進んで行くと鬼怒川を渡ります。上流の左右に雪の山が見えます。左は男体山等の日光連山かもしれませんそうすると、右は会津の山でしょうか。大晦日とは思えない長閑で静かな風景です。平成最後の年の大晦日、那須の狛犬を訪ねる旅は青空の下の雪山が道連れとなりました。
初詣の準備で氏子の人々が集まっている場合があるので、その様子を見るのも楽しみの一つです。集落の共同体の人々の護る静かな神社も大晦日・正月は一時の賑わいとなります。社を浄める和気あいあいとした人々の姿を見ると、暮らしと一緒にある神社の佇まいが生き生きとして見えてきます。
今回の狛犬巡りはグーグル・マップで探した、白河の石工・野田平業の狛犬を訪ねる旅になります。4つの平業の狛犬を見て大きな満足感を感じながら、県境の村へ向かう帰路に尋ねた最後の神社は更に思いがけない石像を見る事になります。平成最後の大晦日の狛犬巡りは私に大きな喜びを与えてくれました。
2018.12.31
◉その1記載分 ①加茂神社⇒②大田原市蛭田・温泉神社⇒ ◉その2記載分①笠石神社⇒②狭原・温泉神社 ◉その3記載分①薄葉温泉神社⇒②西郷神社
2018.12.31
 |
|
| 笠石神社:大田原市湯津上430。 | |
大田原市観光協会の説明から、奈良時代の西暦700年頃那須国(範囲が狭く郡程度の範囲)支配していた国造の遺徳を称えた石碑が祀られているようで、観光施設になっているようです。石碑を祀るお堂と思われる前に(推測ですが)狛犬が奉納されています。 |
|
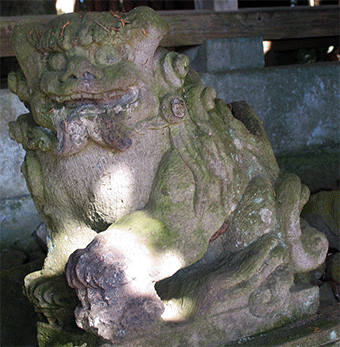 一見してかなり古い狛犬かと思ったのですが所謂紀元2600年を記念した昭和15年の奉納でした。右に置かれた阿像と思われるこの狛犬は若干小型です。
一見してかなり古い狛犬かと思ったのですが所謂紀元2600年を記念した昭和15年の奉納でした。右に置かれた阿像と思われるこの狛犬は若干小型です。
白河市等の狛犬とは異なるかなりユニークな意匠です。素人の印象ですが那須地方の狛犬は概して円らな目が目立つように感じます。2016年5月31日に訪れた那須町の住吉神社、健武山湯泉神社の狛犬でも同じ印象を持った事を思い出しました。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 スペースの関係で左に置かれた吽像から阿像を写しました。まるで稲荷神社の狐像のような大変興味深い尻尾です。このような独特の意匠を目にする事は大きな楽しみに一つです。
スペースの関係で左に置かれた吽像から阿像を写しました。まるで稲荷神社の狐像のような大変興味深い尻尾です。このような独特の意匠を目にする事は大きな楽しみに一つです。
![]() 2018.12.31
2018.12.31
 左に置かれた吽像、吽像も円らなと言う印象は似つかわしくないでしょうが、丸い目をしています。地元の石工の人の作品ではないかと推測します。
左に置かれた吽像、吽像も円らなと言う印象は似つかわしくないでしょうが、丸い目をしています。地元の石工の人の作品ではないかと推測します。
|
 |
|
| 温泉神社住所:大田原市狭原786 | |
|
|

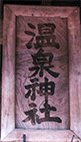 杉木立が辺りを覆う境内は誰一人居ません。静かな佇まいの境内では、石造りの狛犬だけがあたかも血の通った生物のように感じてしまいます。
杉木立が辺りを覆う境内は誰一人居ません。静かな佇まいの境内では、石造りの狛犬だけがあたかも血の通った生物のように感じてしまいます。
参道の入り口方向を見ています。。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 |
 |
| 参道の入り口の鳥居まで歩いてきました。鳥居の前面には広大な田圃が広がっています。軽トラック等ではこちらからも入れるのかもしれません。 |
|
 右に置かれた阿像、通常のサイズより僅かに小さな狛犬。那須の狛犬らしくやはり大きな丸い目をしています。牙が狛犬の形相を険しいものに感じさせるようです。
右に置かれた阿像、通常のサイズより僅かに小さな狛犬。那須の狛犬らしくやはり大きな丸い目をしています。牙が狛犬の形相を険しいものに感じさせるようです。
![]() 2018.12.31
2018.12.31

 石工の名前は見つけられませんでしたが、奉納されたのが大正15年10月と刻まれています。大正15年の12月25日から昭和が始まります、大正時代の終わりを告げる狛犬になります。冬寒の薄暗い木漏れ日の中に居るのは私達だけです、無機物の狛犬さえ私達生物の仲間に思えてきます。
石工の名前は見つけられませんでしたが、奉納されたのが大正15年10月と刻まれています。大正15年の12月25日から昭和が始まります、大正時代の終わりを告げる狛犬になります。冬寒の薄暗い木漏れ日の中に居るのは私達だけです、無機物の狛犬さえ私達生物の仲間に思えてきます。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 左に置かれた吽像、日が差さない境内に置かれている為か全体にかなり苔が生えています。
左に置かれた吽像、日が差さない境内に置かれている為か全体にかなり苔が生えています。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 次の神社に向かって西に車を走らせていくと、広く広がった道路の先に雪の山並みと青空に浮かぶ沢山の雲の塊の美しい風景が続きます。
次の神社に向かって西に車を走らせていくと、広く広がった道路の先に雪の山並みと青空に浮かぶ沢山の雲の塊の美しい風景が続きます。
車を降りてカメラのシャッターを押しました。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 |
|
| 那須神社住所:大田原市南金丸 | |
|
|
”それより八幡宮に詣づ。「与一扇の的射し時、別しては我が国の氏神正八まんと、ちかひしも此の神社にて侍る」と聞けば、観応殊にしきりに覚えらる。” |
|
 私達は道の駅の駐車場から歩いて神社の横から入ったようです。美しい玉砂利の長い参道が2の鳥居まで続いています。その先に神社らしきもの見えています。
私達は道の駅の駐車場から歩いて神社の横から入ったようです。美しい玉砂利の長い参道が2の鳥居まで続いています。その先に神社らしきもの見えています。 後を振り返ると車から見た大きな一の鳥居が遥か彼方の玉砂利の参道の先に見えます。夜中から始まる初詣の準備は全て整ったようです。
後を振り返ると車から見た大きな一の鳥居が遥か彼方の玉砂利の参道の先に見えます。夜中から始まる初詣の準備は全て整ったようです。
今は境内に居るのは私達二人だけです(後から地元の方は二人連れでお詣りに訪れていました)。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 今夜からの初詣の十分が整ったらしくテントの前はしっかりと閉じられていました。大きな台座の上にかなり大型の狛犬が奉納されていました。
今夜からの初詣の十分が整ったらしくテントの前はしっかりと閉じられていました。大きな台座の上にかなり大型の狛犬が奉納されていました。
那須の狛犬にしてはかなり厳しい目付きの狛犬です。彫りはそれ程精密ではありませんが大きく口を開けた狛犬には動きを感じさせるものがあります。地元の狛犬の特徴が表れているのかもしれません。![]() 2018.12.31
2018.12.31
 |
 |
|
| 左の吽像から阿像を写しました。広い参道が二つの狛犬を引き裂いているようです。今夜の喧騒は狛犬にとって久しぶりに目にする光景になるでしょう。 | ||
|
||
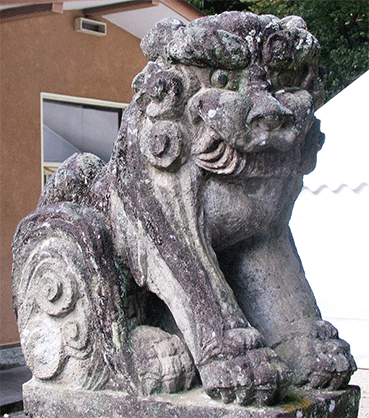 左に置かれた吽像、こちらは険しい表情の阿像に比べて丸い目が優し気に見えます。地元の石工の人の狛犬と分かると独特の意匠が個性に見えてきます。
左に置かれた吽像、こちらは険しい表情の阿像に比べて丸い目が優し気に見えます。地元の石工の人の狛犬と分かると独特の意匠が個性に見えてきます。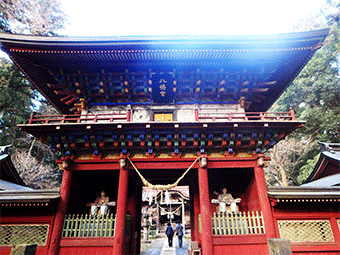 随身門も大変豪華な作りで、私が普段訪ねている神社とは異質の空間が広がっています。地元の人が二人でお参りに来ていました。初めて神社の境内で人に会いました。
随身門も大変豪華な作りで、私が普段訪ねている神社とは異質の空間が広がっています。地元の人が二人でお参りに来ていました。初めて神社の境内で人に会いました。
 随身門には左右に美しい守護神像が祀られていました。
随身門には左右に美しい守護神像が祀られていました。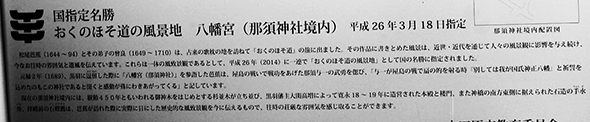
 |
|
|



最後の那須神社では狛犬と併せて芭蕉の足跡に触れる事が出来るという思いもしない幸運に巡り合いました。車を止めた道の駅の農産物売り場に立ち寄りました。通常道の駅は観光施設で、値段が高く野菜の姿は良くても味がいまいちの場所が多く、そこには地元の人の姿が見られません。たいして期待もせずにこの道の駅に入って雰囲気が違うのでこれはと思いました。地元の方が多く買い物をしていました。値段と品質を見て納得しました。
何時も野菜を買い込む白河市の”り菜庵”が年末年始休みなので困っていました。トマトが青いのですが5個程入って¥100とか、信じられない程太い大根が¥100とか・・・、かなり大量に買い込む事が出来てこれも今回の神社巡りのご利益かもしれません。
2018.12.31
これから最後の行程になる二つの神社に向かって進むことになります。
2018.12.31
| 2022年7月10日 |
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
|
Provided: Since Oct.10,2007 |
||


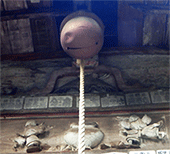 461号線を大田原市内に向かって進んでいると信号に引っ掛かり停止します。何気なく右に目をやると大きな鳥居が見えます。急いで信号が青になると右手に曲がります。曲がると左に広い駐車場、何気なく入っていくと”道の駅那須与一の郷”( 栃木県大田原市南金丸1584番地6)という施設でした。後で農産物を買うので道の駅に止めて神社を訪ねる事にしました。
461号線を大田原市内に向かって進んでいると信号に引っ掛かり停止します。何気なく右に目をやると大きな鳥居が見えます。急いで信号が青になると右手に曲がります。曲がると左に広い駐車場、何気なく入っていくと”道の駅那須与一の郷”( 栃木県大田原市南金丸1584番地6)という施設でした。後で農産物を買うので道の駅に止めて神社を訪ねる事にしました。 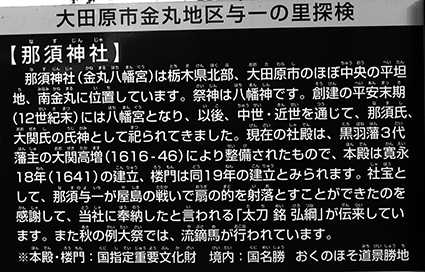 那須与一の伝承はここを訪れた芭蕉のおくの細道にも書かれています。
那須与一の伝承はここを訪れた芭蕉のおくの細道にも書かれています。