
| グーグル・マップ訪問地点明細(地図のポイント表示マークは色分けされています) | ||||||
| 各回のホーム・ページ見出し名一覧 | 実施期間 | |||||
| 第1回 | ①関の城下町 | ②小峰城と金毘羅神社 | ③借宿・羽黒神社 | 2015.6.29~30 | ||
| 第2回 | ①中島村周辺 | ③白河の関周辺 | ③浅川町周辺 | 2015.7.13~14 | ||
| 第3回 | ①西郷村~白河市 | ②国津神社・羽黒神社 | ③鐘鋳神社と貫秀寺 | 2015.7.27~28 |
||
| 第4回 | ①白河市大信 | ②白河市近津神社他 | ③二つの角折神社 | 2015.8.17~18 |
||
| 第5回 | ①西郷村4つの社 | ②石川町八幡神社他 | ③小松布孝と小林和平 | 2015.9.7~8 | ||
| 第6回 | ①西郷村から白河市 | ②白河大信から天栄村 | ③浅川町 | ④棚倉町 | 2015.9.28~9 | |
石都都古和気神社・小林和平狛犬吽像 |
|||||||||||||||||||||
周りには人家が迫っています。それも良いと思いました。人々の普通の暮らしの中にある和平の狛犬は幸せだと思ったのです。製作者にとって見てくれる人の絶えない事ほど嬉しい事は無いのではないかと思いました。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
 川向うを見ると白い壁の家をバックに狛犬が見えました。道路を横断して短い橋を渡ります。川の両岸は桜の並木のようです。桜の季節に訪れてみたいものだと思いました。 川向うを見ると白い壁の家をバックに狛犬が見えました。道路を横断して短い橋を渡ります。川の両岸は桜の並木のようです。桜の季節に訪れてみたいものだと思いました。 |
|||||||||||||||||||||
小林和平・狛犬阿蔵 |
|||||||||||||||||||||
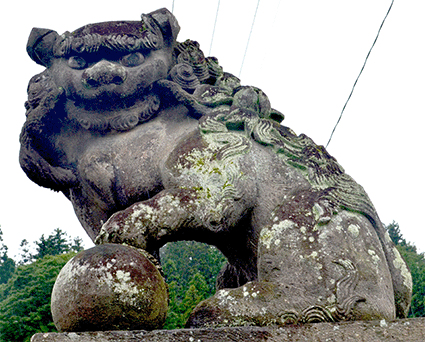 阿像を見上げています。台座がかなり大きく狛犬も大きめです。見上げるようになります。素人の私でも、活き活きとしたつぶらな目の形を見て和平の狛犬だと分かりました。 阿像を見上げています。台座がかなり大きく狛犬も大きめです。見上げるようになります。素人の私でも、活き活きとしたつぶらな目の形を見て和平の狛犬だと分かりました。 |
|||||||||||||||||||||
小林和平・狛犬吽像 |
|||||||||||||||||||||
 和平の子供の狛犬の姿はどれも愛らしく童話の世界を見ているようです。 和平の子供の狛犬の姿はどれも愛らしく童話の世界を見ているようです。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
石川町の観光パンフレットをお願いして居たら、4ページの狛犬の小冊子と桜マップを持って帰ってきてくれました。中々良く出来た内容です。暗くなる前に煙草神社、宝海寺と村社八幡神社に向かう事にします。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
宝海寺 |
|||||||||||||||||||||
宝海寺の入口の石灯籠風門柱に”献納・小林和平”の名前が刻まれていました。 高さ2m程の簡素ながら良いデザインの門柱です。確か和平はこの墓地に眠っていると思うのですが大騒ぎで探すことも憚りがあるのでそっと墓地を一周してみました。 それらしいものが見当たりません。八幡神社の印も見当たりませんでした。諦めて帰ろうと思いながら境内にある石像類の写真だけ後日の為に撮りました。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
村社八幡神社 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
 石段を上ると左手に草生した境内と社が見えてきました。狛犬とお目当ての兎の石像が森の木陰の中に見えました。雨は降り止みません。 石段を上ると左手に草生した境内と社が見えてきました。狛犬とお目当ての兎の石像が森の木陰の中に見えました。雨は降り止みません。 |
|||||||||||||||||||||
狛犬阿像・慶應元年・1865年 |
|||||||||||||||||||||
彫り込みは慶應元年と”願主 石工 宮(官?)田庄七”ではないかと推測されますが確かではありません。多分、”宮田庄七”ではないかとも思いますが、確認は出来ませんでした。全て、知識の浅い私の目からの推測なので間違っている可能性が高いと思います。
|
|||||||||||||||||||||
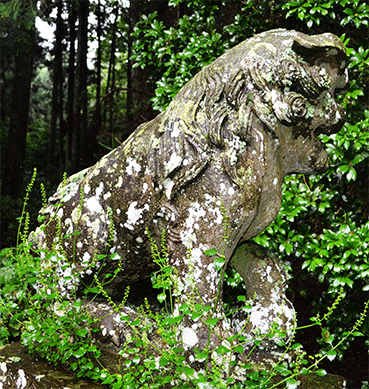 社側から阿像を見ています。全体の姿は違和感がありません。総じて近辺の石工の人達の技量がかなり高いものであったように思いました。 社側から阿像を見ています。全体の姿は違和感がありません。総じて近辺の石工の人達の技量がかなり高いものであったように思いました。 |
|||||||||||||||||||||
狛犬吽像・慶應元年・1865年 |
|||||||||||||||||||||
 子供の狛犬と一緒の吽像はどこか表情が柔らかい印象です。阿像と同じく少し顔が大きい目のように感じました。 子供の狛犬と一緒の吽像はどこか表情が柔らかい印象です。阿像と同じく少し顔が大きい目のように感じました。 |
|||||||||||||||||||||
 多くの狛犬の子供と同じく、この像の子供の表情は悪くありません。石工の人も子供の狛犬を彫るときは童心を取り戻すのかもしれないと思いました。 多くの狛犬の子供と同じく、この像の子供の表情は悪くありません。石工の人も子供の狛犬を彫るときは童心を取り戻すのかもしれないと思いました。 |
|||||||||||||||||||||
撮影の記録を残していなかったのでこれは狛犬の彫り込みの写真だとは思うのですが、違っている場合もあります。 |
|||||||||||||||||||||
社に向かって右の兎石像 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
兎の像一対・右の像・天保14年・1843年 |
|||||||||||||||||||||
どこか遠い未来を見つめているような茫洋とした目も印象的です。まるで雲にでも乗った来世からの使いにも感じました(全くの個人的な印象ですが)。 石像に彫られた文字は天保十四年(癸卯)1843年、願主 角田定右までは読めるのですが、それから下は正確には分かりません。多分ここまでくると一般的には定右衛門だと思うのですが、正確には分かりません。天保14年が”癸卯”の年なので年代はあっていると思います。 |
|||||||||||||||||||||
 右の兎の石像を社側から見ています。一面に青苔が密生して一層生き物らしさが増しているようです。 右の兎の石像を社側から見ています。一面に青苔が密生して一層生き物らしさが増しているようです。 |
|||||||||||||||||||||
兎の像一対・左の像・天保14年・1843年 |
|||||||||||||||||||||
 社に向かって左に位置する兎の石像です。こちらは少し白い苔が付いているようです。 社に向かって左に位置する兎の石像です。こちらは少し白い苔が付いているようです。 |
|||||||||||||||||||||
鎮守の森に夕暮れが迫ってきました。いつまでも見ていたいのですが帰路に就くことにします。 |
|||||||||||||||||||||
 11号線を白河方面に向かっていると鹿島神社の近くを通りました。同行の村の知り合いに寅吉の傑作と呼ばれる狛犬を見せてやろうと立ち寄ることにしました。
11号線を白河方面に向かっていると鹿島神社の近くを通りました。同行の村の知り合いに寅吉の傑作と呼ばれる狛犬を見せてやろうと立ち寄ることにしました。
神社の境内は既に夕暮れ時です。正面の写真は殆ど暗くてダメでした。肉眼では、まがまがしい姿が迫ってくるように見えました。
 後ろからは順光線なので撮影が出来ました。やはり小松布孝は”北斎”で、小林和平は”広重”の例えは結構二人の石像の理解に有益に思えてきました。
後ろからは順光線なので撮影が出来ました。やはり小松布孝は”北斎”で、小林和平は”広重”の例えは結構二人の石像の理解に有益に思えてきました。
これは愛読する藤沢周平の「溟い海」に出てくる北斎、広重の二人の姿からの自分勝手な推測です。浮世絵の専門家の方には笑われそうな例えかもしれません。 ![]() 2015.09.08
2015.09.08
 吽像の方が幾らか夕方の光の残りが当たるようで写りが良いようです。同行の村の知り合いの人も雨を忘れたように熱心に見ています。
吽像の方が幾らか夕方の光の残りが当たるようで写りが良いようです。同行の村の知り合いの人も雨を忘れたように熱心に見ています。 ![]() 2015.09.08
2015.09.08
 吽像の後ろです。やはり燃える炎に見えてなりません。布孝の止めようもない激しいエネルギーが噴出しているように思えます。見る人の心を動かし感動を与えるのは当然の結果だと思いました。
吽像の後ろです。やはり燃える炎に見えてなりません。布孝の止めようもない激しいエネルギーが噴出しているように思えます。見る人の心を動かし感動を与えるのは当然の結果だと思いました。
大急ぎで近くの坂本観音に向かいます。車で5分程です。 ![]() 2015.09.08
2015.09.08
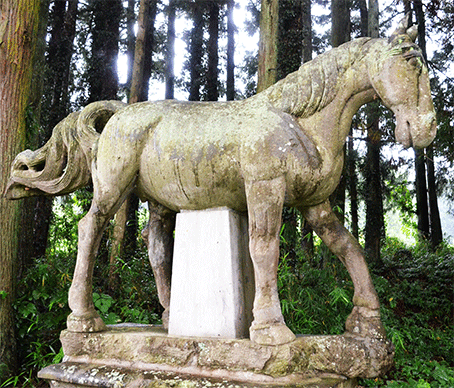 夕闇の迫る森の牧場で小松布孝(寅吉)の牝馬は静かに立っていました。私には生きているように見えてなりません。ほぼ実際の馬の大きさに匹敵します。
夕闇の迫る森の牧場で小松布孝(寅吉)の牝馬は静かに立っていました。私には生きているように見えてなりません。ほぼ実際の馬の大きさに匹敵します。
同行の村の知り合いの人もしばし見とれていました。 ![]() 2015.09.08
2015.09.08
 寅吉の牝馬の石像の隣の畑では菊が満開です。夏が過ぎていきます。雨に黄色の菊が生き返ったようです。
寅吉の牝馬の石像の隣の畑では菊が満開です。夏が過ぎていきます。雨に黄色の菊が生き返ったようです。
長い一日が終わりました。いよいよ帰路に就くことにします。
県境の村に帰りついたのは夜の6時を過ぎていました。私達は随分恵まれた場所に暮らしていることになります。街の暮らしでは手に入れる事のできない新鮮な野菜を買いながら、この地の石工達の石像を心行くまで堪能できるのです。狛犬を訪ねて(そのⅤの③)終わり。 ![]() 2015.09.08
2015.09.08
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
|
Provided: Since Oct.10,2007 |
||
 小林和平の狛犬があるのが、参道入口の二つの鳥居の間です。一の鳥居の先にある案内図に若干加筆・修正して掲載しました。
小林和平の狛犬があるのが、参道入口の二つの鳥居の間です。一の鳥居の先にある案内図に若干加筆・修正して掲載しました。

 阿像を後ろ、社側から見ています。尻尾が前に戻ってきている様子、後ろ足のけり上げた姿など動きのある石像です。そして全体にシャープな肢体が表現されているように見えます。
阿像を後ろ、社側から見ています。尻尾が前に戻ってきている様子、後ろ足のけり上げた姿など動きのある石像です。そして全体にシャープな肢体が表現されているように見えます。 吽像も逆立ちをしそうな程後脚が上にあります。雲の彫も綺麗に残っています。子供達と一緒に此方を見つめられて一瞬目のやり場に困りました。
吽像も逆立ちをしそうな程後脚が上にあります。雲の彫も綺麗に残っています。子供達と一緒に此方を見つめられて一瞬目のやり場に困りました。

 和平の狛犬から登りだす最初の階段です。狛犬は平らになった辺りに置かれています。緑の横の線は川があります、その対岸にもう一対の和平の狛犬が奉納されています。
和平の狛犬から登りだす最初の階段です。狛犬は平らになった辺りに置かれています。緑の横の線は川があります、その対岸にもう一対の和平の狛犬が奉納されています。
 アザミの花の色が綺麗です。素直な花が目を休めてくれます。
アザミの花の色が綺麗です。素直な花が目を休めてくれます。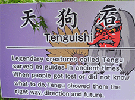 参道の脇に岩があって色々な名前が付けれています。少し説明に無理があるものも見られました。
参道の脇に岩があって色々な名前が付けれています。少し説明に無理があるものも見られました。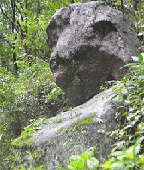 これが天狗岩と言う岩のようです。比較的説明が納得できる岩の形でした。
これが天狗岩と言う岩のようです。比較的説明が納得できる岩の形でした。
 石川城址の跡らしくその関連の遺跡があるようです。
石川城址の跡らしくその関連の遺跡があるようです。 荘厳な本殿でお参りをしました。雨がカメラのレンズに掛かるために水滴が写りこんでしまいます。
荘厳な本殿でお参りをしました。雨がカメラのレンズに掛かるために水滴が写りこんでしまいます。 石都都古和気神社の本殿は奥の院まで備えた格式の高い神社のようです。
石都都古和気神社の本殿は奥の院まで備えた格式の高い神社のようです。
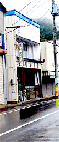 御仮屋の通りの向こうを見ると大竹石材店の看板。石工の名前で時々目にするあの大竹石材店の事なのかも知れないと思いました。
御仮屋の通りの向こうを見ると大竹石材店の看板。石工の名前で時々目にするあの大竹石材店の事なのかも知れないと思いました。 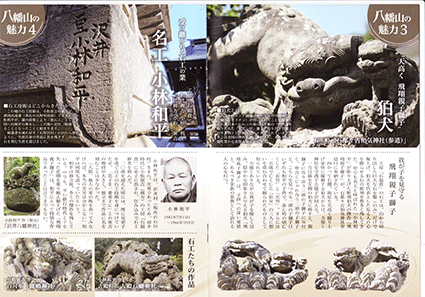 余りにも遅いので家人が役場まで様子を見に行きました。何か手間取っている様子でしたがやがて連れ立って戻ってきました。
余りにも遅いので家人が役場まで様子を見に行きました。何か手間取っている様子でしたがやがて連れ立って戻ってきました。
 石都都古和気神社から僅か、町の繁華街にありました。表通りから同行の地元の人が神社を見つけてくれました。福島銀行の路地の先に鳥居が見えます。銀行は既に閉まっていましたので止めさせてもらいました。左は境内から福島銀行の有る繁華街の通りを見ています。狛犬が見えますが新しいタイプの狛犬ようです。
石都都古和気神社から僅か、町の繁華街にありました。表通りから同行の地元の人が神社を見つけてくれました。福島銀行の路地の先に鳥居が見えます。銀行は既に閉まっていましたので止めさせてもらいました。左は境内から福島銀行の有る繁華街の通りを見ています。狛犬が見えますが新しいタイプの狛犬ようです。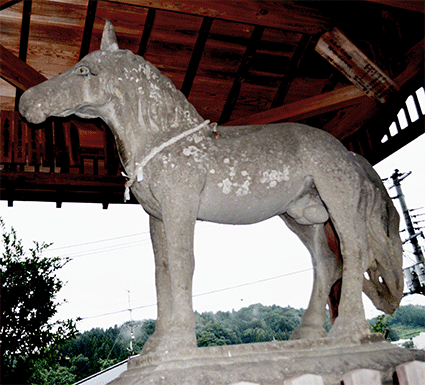 神社の石段を登って境内の左、屋根を被った馬が見えます
神社の石段を登って境内の左、屋根を被った馬が見えます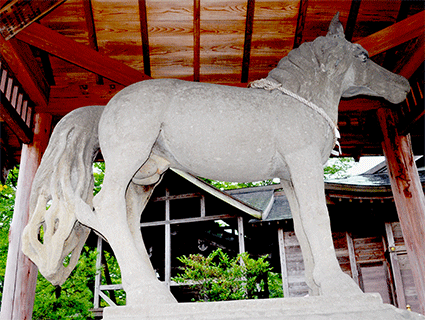 尻尾のが下に下がっているのが大人しい印象を与えるのかもしれません。10年後に製作された坂本観音の馬は尻尾を振り上げて全体に力強い姿に見えます。
尻尾のが下に下がっているのが大人しい印象を与えるのかもしれません。10年後に製作された坂本観音の馬は尻尾を振り上げて全体に力強い姿に見えます。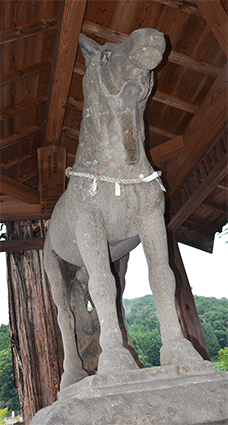

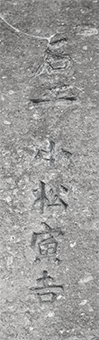


 お地蔵様のほぼ対面の白い壁の家とトタン壁の家の間の細い道を入っていきます。お寺までは緩やかな登り道です。多分、入口の両端の道路に赤いパイロンの道路標識が置かれていると思います。
お地蔵様のほぼ対面の白い壁の家とトタン壁の家の間の細い道を入っていきます。お寺までは緩やかな登り道です。多分、入口の両端の道路に赤いパイロンの道路標識が置かれていると思います。
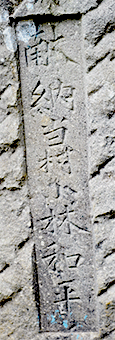 もうすぐ日暮れが迫っているので大急ぎで見る事にします。
もうすぐ日暮れが迫っているので大急ぎで見る事にします。

 諦めて寺の入口に向かうと水子地蔵が立っていました。その後ろを見ると斜面を登る細い道が見えます。一応境内を出て小松和平の灯篭の左の道を登ってみました。20mも登ると左に石段が現れ、鳥居も見えてきました。
諦めて寺の入口に向かうと水子地蔵が立っていました。その後ろを見ると斜面を登る細い道が見えます。一応境内を出て小松和平の灯篭の左の道を登ってみました。20mも登ると左に石段が現れ、鳥居も見えてきました。 枯れ枝が道にたくさん落ちています。余り人が訪れていないようです。期待がたかまります。
枯れ枝が道にたくさん落ちています。余り人が訪れていないようです。期待がたかまります。 顔が少し大きめな狛犬です。彫り込まれた年号が正しければかなり古い時代の石工の作と思われます。
顔が少し大きめな狛犬です。彫り込まれた年号が正しければかなり古い時代の石工の作と思われます。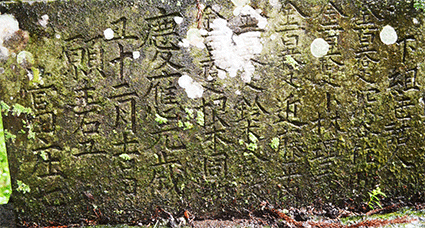 120とか130とか、単位は分かりませんが、氏子の人々はかなりの負担をしているのだと思いました。
120とか130とか、単位は分かりませんが、氏子の人々はかなりの負担をしているのだと思いました。

 小松布孝の師匠である小松利平の作と推定されている兎の石像一対です。これは社に向かって右にあります。動物の俊敏な筋肉を包み込んだ柔らかな体が正確に表現されているように感じました。
小松布孝の師匠である小松利平の作と推定されている兎の石像一対です。これは社に向かって右にあります。動物の俊敏な筋肉を包み込んだ柔らかな体が正確に表現されているように感じました。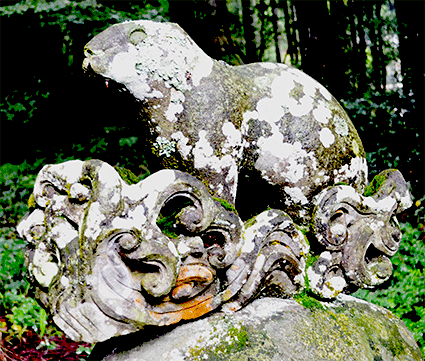 右の石像を社側から見ています。こちらの石像の方が日当たりが良いせいか、かなりの白い苔が付いています。少し薄暗い森の中にあるのですが、作品に動きが感じられるようです。
右の石像を社側から見ています。こちらの石像の方が日当たりが良いせいか、かなりの白い苔が付いています。少し薄暗い森の中にあるのですが、作品に動きが感じられるようです。