

那須朝日岳から三本槍岳までは見晴らしを楽しみながらの快適な尾根歩きが続きます
2011年・紅葉の朝日岳から三本槍岳をご参照ください
10月14日夜、テレビで那須高原の紅葉が最盛期と伝えているのを信じて久し振りに県境の村に出掛けて見る事にしました。私の経験では9月下旬頃が見頃だと思っていたので、今年の天候不順の影響で贈れているのかと推測していました。高原の村の夜気は身震いする程でセーターを羽織りました。
峯の茶屋から牛ヶ首を経由して姥が平に下り登り直して、朝日岳・三本槍岳を往復する予定です。
2018.10.15。*禁・無断転載
| 那須連山のページ | |
|---|---|
| 2020年晩夏の三本槍岳の野の花① ② | 2020年10月12日紅葉する雨の姥ケ平 ① ② |
| 2019年姥平の紅葉①・②、観音沼の紅葉③ | 朝日岳登山道に咲くイワシャジン |
| 2017年ミネザクラとムラサキヤシオ① ② ③ | 2018年朝日岳から三本槍岳の紅葉 ① |
| 台風18号の朝日岳・朝日に輝く朝日岳) | 紅葉の那須・日の出平から姥ケ平①日の出平登り・②下り姥ケ平 |
| 残雪の朝日岳1896メートルと那須岳1915メートル | 濃霧の那須・朝日岳のイワシャジン |
| 赤面山から三本槍岳1916m往復 | 朝日岳1896から三本槍岳1916mの紅葉① ② |
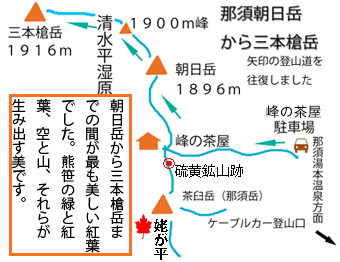 ◎往路①掲載分・峰の茶屋駐車場発7:20⇒峰の茶屋8:02⇒硫黄鉱山跡・引き返し地点8:07⇒朝日岳頂上8:51~8:58
◎往路①掲載分・峰の茶屋駐車場発7:20⇒峰の茶屋8:02⇒硫黄鉱山跡・引き返し地点8:07⇒朝日岳頂上8:51~8:58
◉往路②掲載分・朝日岳8:58⇒熊見曽根9:12⇒1900m峰9:19⇒清水平9:33⇒三本槍岳10:12~10:20⇒復路・清水平・昼食10:53~11:05⇒朝日岳肩11:37峯の茶屋12:02⇒峰の茶屋駐車場12:27(時間は若干実際と異なっている場合もあります)![]() 2018.10
2018.10
朝日岳から清水平 |
|
|
 |

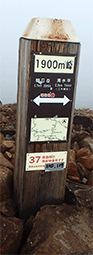 9:19、緩やかな登りで1900m峰に到着、ここからは清水平までの下りとなります。霧が酷く先の道を見通す事が出来ません。
9:19、緩やかな登りで1900m峰に到着、ここからは清水平までの下りとなります。霧が酷く先の道を見通す事が出来ません。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 9:13、清水平の下りから振り返ると霧の中に朝日岳と思われる特異な山が見えます。山の斜面の彩りの組み合わせの妙に感嘆しています。
9:13、清水平の下りから振り返ると霧の中に朝日岳と思われる特異な山が見えます。山の斜面の彩りの組み合わせの妙に感嘆しています。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 9:22、霧の晴れ間から眼下に清水平の湿原が見えてきました。
9:22、霧の晴れ間から眼下に清水平の湿原が見えてきました。
登山道は一旦清水平に降りて木道を歩く事になります。三本槍岳へは左方向に登ります。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 登山道の左下に紅葉に取り囲まれた小さな池塘が光っています。水があれば小さな生き物の暮らす世界が存在している事でしょう。その場は冬になると深い雪の下になります。
登山道の左下に紅葉に取り囲まれた小さな池塘が光っています。水があれば小さな生き物の暮らす世界が存在している事でしょう。その場は冬になると深い雪の下になります。![]() 2018.10.15
2018.10.15

 9:33、清水平に着きました。小さな湿地帯が広がっています。通り過ぎてきた方向を振り返っています。朝日岳と思われる山が霧にの中に浮かんでいます。
9:33、清水平に着きました。小さな湿地帯が広がっています。通り過ぎてきた方向を振り返っています。朝日岳と思われる山が霧にの中に浮かんでいます。
![]() 2018.10.15
2018.10.15
 9:54、北温泉との分岐点に着きました。随分昔になりますが、、2011年8月29日に福島県側の赤面山から辿った道との合流点だと気付きました。熊の気配が感じられたその時の恐怖を思い出しました。 9:54、北温泉との分岐点に着きました。随分昔になりますが、、2011年8月29日に福島県側の赤面山から辿った道との合流点だと気付きました。熊の気配が感じられたその時の恐怖を思い出しました。 |
 |
| 湿原のほぼ北端になります。三本槍岳の方向は霧の中です。これから小灌木の中の小さなアップ・ダウンの登山道が続きます。登山者の人が休んでいました。 |
|
||||
 |
|
 |
既に葉っぱを落として冬支度を始めた白い木肌が美しい灌木の群生が緑の笹の絨毯の中に見えます。見せようとする意志とは無縁の、静寂が基本の自然の造形には見るものの緊張を和らげてくれる様子が感じられます。 |

草紅葉の広がる清水平が目の前です、これから登り返す1900m峰は霧の中に沈んでいます。 |
|
 |
 |
| 10:53~11:05、清水平の湿地帯を抜けた所で昼食を摂る事にしました。ポットの暖かいお茶が滅法甘露です。三本槍岳で写真を撮った夫婦連れの登山者の人が挨拶をして通り過ぎて行きました。 |
|
 |
 11:37、酷い霧が視界を塞ぐ1900m峰から少し下って朝日岳の肩まで戻ってきました。ここからは出発点の峰の茶屋駐車場まで下りが続きます。足を急がせればかなり早く県境の村に戻れそうです。 11:37、酷い霧が視界を塞ぐ1900m峰から少し下って朝日岳の肩まで戻ってきました。ここからは出発点の峰の茶屋駐車場まで下りが続きます。足を急がせればかなり早く県境の村に戻れそうです。 |
|
 11:54、この先の山の鼻を回り込むと峰の茶屋の避難小屋です。左には駐車場への道が左下がりで真っすぐと伸びています。
11:54、この先の山の鼻を回り込むと峰の茶屋の避難小屋です。左には駐車場への道が左下がりで真っすぐと伸びています。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 11:57、峯の茶屋避難小屋が見えてきました。12:02、避難小屋を通過、結構この時間でも登って来る人が多いようです。
11:57、峯の茶屋避難小屋が見えてきました。12:02、避難小屋を通過、結構この時間でも登って来る人が多いようです。
![]() 2018.10.15
2018.10.15
 12:27、峯の茶屋駐車場に戻ってきました。急いで下ってきたので汗びっしょり、トイレでタオルを濡らして汗を拭きました。白河農協の直売所・り菜庵に行けそうです。姥が平の紅葉が無駄足だったので、途中、北温泉の駒止めの滝と八幡温泉のドウダン・ツツジの紅葉を見ようと思います。
12:27、峯の茶屋駐車場に戻ってきました。急いで下ってきたので汗びっしょり、トイレでタオルを濡らして汗を拭きました。白河農協の直売所・り菜庵に行けそうです。姥が平の紅葉が無駄足だったので、途中、北温泉の駒止めの滝と八幡温泉のドウダン・ツツジの紅葉を見ようと思います。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 平日だというのに見学者用の駐車場にはかなりの車が止まって居ました。近頃有名になったのかもしれません。
平日だというのに見学者用の駐車場にはかなりの車が止まって居ました。近頃有名になったのかもしれません。
紅葉は全山真っ赤と言うほどの状態ではありませんでしたが、それなりに紅葉を見る事が出来ました。急いで八幡温泉に向かいます。![]() 2018.10.15
2018.10.15
 那須岳に来た折にはしばしば立ち寄る私にはなじみの場所です。
那須岳に来た折にはしばしば立ち寄る私にはなじみの場所です。
ツツジの季節以外は静かな場所です。わき道からツツジの林の中に足を踏み入れました。山ツツジの林が真っ赤に紅葉していました。この季節は環境客も居ないので静寂です。![]() 2018.10.15
2018.10.15
今回はテレビの情報を鵜呑みにして出かけた事が仇となり、姥が平の紅葉は見る事が叶いませんでした。それでも久し振りに三本槍まで往復できたことは十分満足な山旅でした。那須・朝日岳から三本槍岳①②終わり。
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
 9:12:熊見曽根の突起に到着。霧が視界を塞ぎます。景色は見えにくくなりますが静寂は増します。
9:12:熊見曽根の突起に到着。霧が視界を塞ぎます。景色は見えにくくなりますが静寂は増します。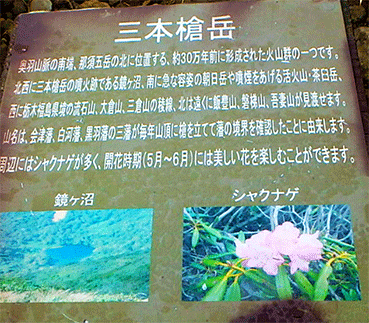
 10:12.三本槍岳に到着。平らな頂上には誰も居ません。霧に取り囲まれて景色はほとんど見る事が出来ません。
10:12.三本槍岳に到着。平らな頂上には誰も居ません。霧に取り囲まれて景色はほとんど見る事が出来ません。 一人で写真を撮っていると夫婦連れの登山者の人が登ってきました。私は自動シャッターで既に自分の写真は撮り終わっていたので、撮影しましょうかと声を掛けました。
一人で写真を撮っていると夫婦連れの登山者の人が登ってきました。私は自動シャッターで既に自分の写真は撮り終わっていたので、撮影しましょうかと声を掛けました。 朝日岳の肩からの最初の下りはぐんぐんと高度が下がっていく快適な道です。
朝日岳の肩からの最初の下りはぐんぐんと高度が下がっていく快適な道です。