泉崎村・熊野神社狛犬・野田平業作33歳(推定)・昭和6年(1931年)と
文久3年 (1863年)癸亥・白河市双石 伊右衛門 *禁・無断転載
2019.05.27、那須のミネザクラを見るために県境の村にやって来ました。那須山の稜線に咲く桜は若干早かったようですが、那須岳の噴煙を背景にして静かに咲く清楚な桜が作り出す自然の風景を堪能しました。
翌日、28日は県境の村を訪れる大きな楽しみの一つ、野菜の買い出しに出かけました。早めに県境の村を出て、町の神社とは異なる神域を持つ村の神社を訪ねる事にしました。
2019.05.28
◉その2記載分 ②矢吹町・御霊神社⇒玉川村・大雷神社⇒玉川村・鹿島神社
◉その3記載分 ③玉川村・若宮八幡神社⇒須賀川市・神明神社・八幡神社
◉その4記載分 ④須賀川市・羽黒神社⇒白河市・日吉神社⇒白河市・名知らずのお堂
 泉崎村北平山入山にある熊野神社を目指してカーナビに従って走っていると集落の狭いに道に入ってしまいました。気が付けば辺りが丘で囲まれた場所で道を失っていました。偶然左手に神社が見えたので立ち寄ってみました。 泉崎村北平山入山にある熊野神社を目指してカーナビに従って走っていると集落の狭いに道に入ってしまいました。気が付けば辺りが丘で囲まれた場所で道を失っていました。偶然左手に神社が見えたので立ち寄ってみました。 |
|
| 薬師堂住所: 西白河郡泉崎村北平山。 | |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 明るい境内の参道を進み二の鳥居まで来るとお目当ての狛犬が奉納されていました。 明るい境内の参道を進み二の鳥居まで来るとお目当ての狛犬が奉納されていました。 |
|
 |
 氏子の人々の願いを込めて奉納された石の社が祀られています。集落の方が教えてくれた通り、沢の水なのか湧き水なのかは判然としませんが水が流れていました。口に含むと柔らかく甘みのある口当たりでした。 氏子の人々の願いを込めて奉納された石の社が祀られています。集落の方が教えてくれた通り、沢の水なのか湧き水なのかは判然としませんが水が流れていました。口に含むと柔らかく甘みのある口当たりでした。 |
泉崎村・熊野神社狛犬・野田平業作33歳(推定)・昭和6年(1931年)・石工 平右衛門
 保存状態が極めて良好な野田平業の狛犬が出迎えてくれました。彫もかなり良好な石像です。台座には石工・平右衛門と彫られていますが、狛犬を平業が彫り台座などをこの石工の人が製造したと推定されます。
保存状態が極めて良好な野田平業の狛犬が出迎えてくれました。彫もかなり良好な石像です。台座には石工・平右衛門と彫られていますが、狛犬を平業が彫り台座などをこの石工の人が製造したと推定されます。
大きさは通常より僅かに小さいような印象を受けます。玉は籠彫りではありませんが全体の彫がかなり良いように見えます。
この狛犬を作った一年後の昭和7年に白河市・愛宕神社の狛犬を彫っていますが、阿像は非常にこの熊野神社の狛犬と似ているように感じます。
![]() 2019.05.28
2019.05.28

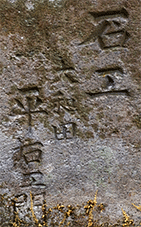
”石工 大和田 平右衛門”の名前が彫られていました。野田平業の彫った狛犬の台座の製造や取り付けを行った人だと推測されます。この石工・平右衛門の住所の”大和田”はこの熊野神社から約8km程西の白河市の地名です。因みに白河市大和田地区には白河市の石工・大高三二が彫った狛犬が奉納されている八幡神社があります。
この熊野神社の狛犬は33歳の野田平業の自信のようなものが感じられる石像です。
2019.05.28
 |
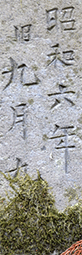 昭和6年の年号が彫られています。未だ昭和10年代の狛犬より顔の扁平な感じが残っているに見えます。野田平業の狛犬のページをご参照下さい。 昭和6年の年号が彫られています。未だ昭和10年代の狛犬より顔の扁平な感じが残っているに見えます。野田平業の狛犬のページをご参照下さい。 |
”正徳六年・丙申”(1716年)の文字が見られる石灯籠が狛犬の両側に奉納されていました。地震で一部が破損したようです。この神社の氏子の人達はかなり古い時代から一定の規模の集落を形成していたと思われます。県境の村の周辺では余り正徳の年号の石像を見る事はないと思われます。
2019.05.28
 |
|
| 関和神社住所:西白河郡泉崎村関和久 | |
|
|

隣り合う雲月寺と関和神社が鎮座するこの一帯は、静かな時間が流れる心休まる場所だと前回訪問の折にも感じました。左手に雲月寺の瓦を見ながら関和神社の狛犬を見させてもらいました。
2019.05.28
泉崎村・関和神社の阿像・明治20年(1887年)・石工名不明
 右に置かれた阿像の方にはボタンが彫られています。彫が頭抜けて精密でこの年代で、これだけの彫りの作品が見られるのは小松寅吉(布孝)作の狛犬ではと推定されているようです。明治26年・白河市・八雲神社の寅吉作と推定した狛犬と目の形や口の表情などの感じが似ているように見えます。
右に置かれた阿像の方にはボタンが彫られています。彫が頭抜けて精密でこの年代で、これだけの彫りの作品が見られるのは小松寅吉(布孝)作の狛犬ではと推定されているようです。明治26年・白河市・八雲神社の寅吉作と推定した狛犬と目の形や口の表情などの感じが似ているように見えます。
ただ、寅吉ほどの腕になると同じ石像は作らないので私には推定出来る材料がありません。
そうでなかったとしても、見応えのある狛犬です。
![]() 2019.05.28
2019.05.28

 左の吽像から阿像を写しています。経年による変色や若干の破損が見られますが、それを感じさせない動きのある狛犬に見えます。
左の吽像から阿像を写しています。経年による変色や若干の破損が見られますが、それを感じさせない動きのある狛犬に見えます。![]() 2019.05.28
2019.05.28
 左側に置かれた吽像と思われる狛犬です。子供が覗き込むように見上げています。
左側に置かれた吽像と思われる狛犬です。子供が覗き込むように見上げています。
個人的な印象としてはこの吽像の表情や動きが、私に寅吉の狛犬ではないかと思わせてくれます。わざと子供を無視して横を向いた表情が極めてリアルな生き物の感じを醸し出してくれているに見えます。
寅吉の作品でないとしても、見ていると時が知らぬ間に過ぎていく素晴らしい石像です。 ![]() 2019.05.28
2019.05.28
 |
 |
|
|
 この拝殿前に奉納された二つ目の文久三年の狛犬の石工名が知りたいと再訪しました。
この拝殿前に奉納された二つ目の文久三年の狛犬の石工名が知りたいと再訪しました。
白河近辺では江戸の狛犬は目にする機会が少なく、それは当時狛犬が彫れる腕の石工の数がかなり限られていたという事ではないかと思いました。数少ない江戸時代の狛犬はほぼ同一の石工が彫っていた可能性が高いのではと推定されます。
この狛犬もなかなか出来の良い手慣れた石工の手によ石像に見えます。造形に違和感を感じません。大きさはやや小型です。![]() 2019.05.28
2019.05.28
 右の吽像から左の阿像を写しています。震災の被害から免れたようで台座なども、製造時の江戸の石でないかもしれませんが古い時代のものが使用されている様に見えます。
右の吽像から左の阿像を写しています。震災の被害から免れたようで台座なども、製造時の江戸の石でないかもしれませんが古い時代のものが使用されている様に見えます。![]() 2019.05.28
2019.05.28
令和1年5月28日、関和神社の近くの熊野神社に出かけるついでにこの狛犬の石工名を探してみる事にしました。台座にはっきりと”双石(くらべいし) 石工 伊右エ門”の文字が彫られていました。
双石は現在の白河市にあり、関和神社からは約6.5kmの距離にあります。この石工は白河市・鹿島神社狛犬(慶応2年・1866年・石工・双石村、伊右衛門)を彫った人だと推定出来そうです。 双石(くらべいし)は11号線・石川街道沿いの地域で鹿島神社までは約3kmの距離になります。この泉崎村にある関和神社までは約7km程になります。
複数の狛犬を彫った江戸時代の石工が存在した事になります。明治時代になって、同じ双石の①社八幡神社(表郷八幡社山)②熊野神社(双石)を彫った深谷儀助とは何らかの繋がりがあるのか大変興味深い事です。
2019.05.28
 左に置かれた吽像です、大きな目が優し気な印象を醸し出しています。
左に置かれた吽像です、大きな目が優し気な印象を醸し出しています。
大きな目で参拝の人々を見つめる優し気な表情の親、その親の庇護を信じてしずかに足下に蹲る子供の姿が動きのある造形を生み出しいる様に感じました。
神社の御由来に掛かれた歴史を感じさせる狛犬に出会えました。![]() 2019.05.28
2019.05.28
 |
|
|
|
白河市・東蕪内・名知らずのお堂・狛犬大正12年(癸亥)1923年
 お堂に向かって左に置かれた阿像と思われる狛犬は通常のサイズの1/3程でかなり小型です。大正12年の年号は確認できたのですが石工の名前は見つける事が出来ませんでした。一般的な阿吽像の一と逆に置かれていると思われます。
お堂に向かって左に置かれた阿像と思われる狛犬は通常のサイズの1/3程でかなり小型です。大正12年の年号は確認できたのですが石工の名前は見つける事が出来ませんでした。一般的な阿吽像の一と逆に置かれていると思われます。
体のサイズには不釣り合いの大きな玉を収めています。顔は若干経年により破損したのか判然としません。![]() 2019.05.28
2019.05.28
 阿像から右に置かれた吽像を写しています。雑草に埋もれた野の狛犬です。残念ながらお堂の名前を示す扁額などが無いため名前が分かりませんでした。
阿像から右に置かれた吽像を写しています。雑草に埋もれた野の狛犬です。残念ながらお堂の名前を示す扁額などが無いため名前が分かりませんでした。 右に置かれた吽像も大きな玉を収めています。顔面の表情が経年で破損したのか判然としません。
右に置かれた吽像も大きな玉を収めています。顔面の表情が経年で破損したのか判然としません。
かなりユニークな意匠の狛犬です。![]() 2019.05.28
2019.05.28
境内にはかなり多くの石碑や石の社が奉納されています。 |
 |
 |
|
| 熊野神社住所:福島県白河市舟田熊野越 | |
|
|
 |
 |
|
|
今回は幾つかの目的を持って神社巡りを楽しんだのですが、野田平業の狛犬を訪ねる事は叶ったですが、もう一つの目論見である白河市の狛犬を見つける事が出来ませんでした。ただ、その途次、全く予期しなかった狛犬に出会う僥倖に遭遇した事は神社巡りのご利益であろうと思っています。その②以降は更に北へと狛犬を訪ねてみる事にします。
2019.05.28
| 2020年1月11日 |
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
|
Provided: Since Oct.10,2007 |
||

 開けた大地に続く石段の先に社が見えます、右手には薬師堂と推測される建物が見えます。穏やかな石仏が出迎えてくれました。名前が知れないこの神社には残念ながら狛犬は見あたりませんでした。
開けた大地に続く石段の先に社が見えます、右手には薬師堂と推測される建物が見えます。穏やかな石仏が出迎えてくれました。名前が知れないこの神社には残念ながら狛犬は見あたりませんでした。 経年でかなり摩耗した微笑ましい石像と、文久4年(1864年)甲子の年号が彫られた大勢至菩薩の石塔が見えます。
経年でかなり摩耗した微笑ましい石像と、文久4年(1864年)甲子の年号が彫られた大勢至菩薩の石塔が見えます。 熊野神社住所:西白河郡泉崎村北平山入山。集落の細い道を抜けて一旦県道75号線に出ました。やっとカーナビに道が表れて今度は問題なく山際を通る細い道の先に素晴らしい神社が現れました。
熊野神社住所:西白河郡泉崎村北平山入山。集落の細い道を抜けて一旦県道75号線に出ました。やっとカーナビに道が表れて今度は問題なく山際を通る細い道の先に素晴らしい神社が現れました。

 台座には大正12年(1923年)と干支の”癸亥”が刻まれています。
台座には大正12年(1923年)と干支の”癸亥”が刻まれています。 舟田山松雲寺 (白河市舟田寺西11)と道路を挟んで並んでいます。車は道路脇の駐車場と思われるスペースに停めさせて貰いました。東隣りには雨乞い山不動尊があり、この一帯は神と仏が集まっている場所のようです。古そうな鳥居と神社の石柱を見ると狛犬が奉納されているように感じましたが残念ながら、境内には素晴らしい見晴らしだけがありました。
舟田山松雲寺 (白河市舟田寺西11)と道路を挟んで並んでいます。車は道路脇の駐車場と思われるスペースに停めさせて貰いました。東隣りには雨乞い山不動尊があり、この一帯は神と仏が集まっている場所のようです。古そうな鳥居と神社の石柱を見ると狛犬が奉納されているように感じましたが残念ながら、境内には素晴らしい見晴らしだけがありました。