
矢板市・塩釜神社の狛犬・昭和9年(1934年)石工 菊地平二 *(禁)無断転載
狛犬を訪ねての冬休みの狛犬巡りの”№31・那須の狛犬そのⅠ”は① ② ③ ④ で2019年の神社と狛犬を訪ねる旅の終わりを迎えました。新年に入ってから、初詣の煩雑が過ぎた2020年1月2日・冬休みの狛犬巡り”№32・那須の狛犬そのⅡ”として更に那須から南に道を辿りました。① ② ③ ④ ⑤ ⑥ で13の神社を参拝しそれぞれの神社で独特の狛犬を訪ねました。
1月4日、味をしめて那須の狛犬Ⅲとして、Ⅱで訪ねた神社より北寄りの町を訪ねる事にしました。
2020.01.04
令和2年1月3日、好天の続く令和2年の新年、県境の村の庭の木に小鳥が訪れます。余り鳥を撮る事が無いのですがカメラのテストに窓越しにシャッターを押してみました。素早く枝から枝へと飛び移る姿を写すのは難しい事でした。やっと一枚だけ姿が分かるものが撮れました。鳥の名前は全く分かりません。
明日、1月4日は再度那須の神社を巡る事にしています。小鳥の訪問は吉兆の印かもしれません。
(Ⅰ)2019年12月30日:この厳寒の季節の楽しみに最適な那須周辺の神社巡りを気の向くままに楽しんでみようと思っています。多くが暮らす人々が神々を祀る為に建てた清冽な那須野が原の神社を詣でてその地に奉納された狛犬に出会うことは大きな楽しみです。もしかしたらその土地の神社を護る氏子の方々に出会うことが出来るかもしれません。そして那須野が原の多くの神社からは雪を戴いた山の姿が目の前に広がっています。那須の狛犬巡りはⅠ(2019年12月30日)・Ⅱ(2020年1月2日)・Ⅲ(2020年1月4日)と3日間続きました。
(Ⅳ):暮らす街への帰路、前回の旅で日本の懐かしい景色に出会った久慈川流域の東白川郡を通り袋田の滝を見ながら茨城県大子町の社を訪ねました。
街を出てからの走行距離は合計1,100km、気づかないうちにかなりの距離を走っていたようです。
2020.01.04
2019年12月・2020年1月冬季休暇の狛犬巡り一覧 |
||||
| Ⅰ(№31) | 12月30日①~④・大田原市 | ①大田原神社⇒②上奥沢・温泉神社⇒②大豆田・温泉神社⇒③佐良土・温泉神社⇒③佐良土・法輪寺⇒④飯繩山神社⇒④稲沢・温泉神社 | ||
| Ⅱ(№32) | 1月2日 | ①宇都宮市・三祖神社⇒②刈沼町・星宮神社 ⇒②智賀都神社⇒②金井神社⇒③神明宮⇒③出雲神社⇒④那須烏山市福岡・星宮神社⇒ ④那須烏山市鴻野山・星宮神社⇒⑤高根沢町伏久・星宮神社⇒ ⑤さくら市狹間田・神社名不明⇒⑥さくら市狹間田・星宮神社⇒⑥さくら市柿木澤・星宮神社⇒⑥さくら市・今宮神社 | ||
| Ⅲ(№33) | 1月4日 | ①那須塩原市箒根神社⇒①那須塩原市八坂神社⇒②矢板市・塩竈神社⇒②矢板市・剣神社⇒③矢板市・木幡神社⇒③さくら市(以下全てさくら市)・鷲宮神社⇒④松島・星宮神社⇒④箱森新田・今宮神社⇒⑤人丸神社⇒⑤八幡宮⇒⑥馬馬・今宮神社⇒⑥長久保・天神社⇒⑥蒲須坂・三嶋神社 | ||
№31・№32・№33の"冬休みの狛犬巡りの旅"で訪ねた神社は |
 |
|
| 塩釜神社住所:栃木県矢板市上町6。 | |
市街地から神社へ入る道も問題なく車が通れて境内に大きな駐車場がありました。 |
|
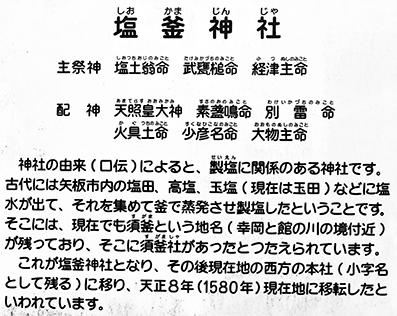
入口の神社の説明板です。しばしば目にする塩土翁命のが祭神のお一人と書かれています。境内には参拝の人が居るので、その人々が写る恐れがあるので写真は出来る限り遠慮しました。
![]() 2020.01.04
2020.01.04
 |
 |
|
|
 |
 |
| 拝殿の左奥には稲荷神社が奉られています。 |
|
 若干大型の落ち着いた風貌の狛犬が奉納されていました。右に置かれた玉取りの意匠の吽像と思われます。一般的な阿吽像の位置が逆に置かれているようです。
若干大型の落ち着いた風貌の狛犬が奉納されていました。右に置かれた玉取りの意匠の吽像と思われます。一般的な阿吽像の位置が逆に置かれているようです。
狛犬の表情もそれぞれに特徴がありますが、この石像は見上げる人を穏やかな気持ちにさせるものを感じました。
![]() 2020.01.04
2020.01.04


![]()
右に置かれた吽像から左の阿像を写しました。石像の状態がかなり良好で彫りも当時の状態が残っているように見えました。台座には年号と石工名が彫られています。”那須郡黒田原 石工 菊地平二”の名前を見て黒田原神社に奉納された二つの狛犬を彫った職人だと懐かしく思い出しました。この黒田原神社の拝殿前の狛犬も、この矢板の塩釜神社の狛犬と同じく阿吽像の位置が逆に置かれています。興味深く見させて貰いました。![]() 2020.01.04
2020.01.04
 左に置かれた子取りの意匠の阿像は吽像より更に優し気な印象です。どちらかと言うと子供の狛犬の方が目付きがきつくやんやな感じがします。
左に置かれた子取りの意匠の阿像は吽像より更に優し気な印象です。どちらかと言うと子供の狛犬の方が目付きがきつくやんやな感じがします。
![]() 2020.01.04
2020.01.04
 塩釜神社から向かっている次の剣神社は直ぐ近くです。剣神社の方向に見える秀麗な山は、神社近くに立つ芭蕉句碑に出てくる高原山ではないかと思われます。驚きに出会う期待が膨らんできます。
塩釜神社から向かっている次の剣神社は直ぐ近くです。剣神社の方向に見える秀麗な山は、神社近くに立つ芭蕉句碑に出てくる高原山ではないかと思われます。驚きに出会う期待が膨らんできます。 |
|
| 剣神社住所:矢板市幸岡939。 | |
|
|

 小山の上に鎮座する心地よい拝殿の前に迫力ある狛犬が奉納されていました。参拝をさせて貰ってからゆっくりと見させて貰う事にします。
小山の上に鎮座する心地よい拝殿の前に迫力ある狛犬が奉納されていました。参拝をさせて貰ってからゆっくりと見させて貰う事にします。![]() 2020.01.04
2020.01.04
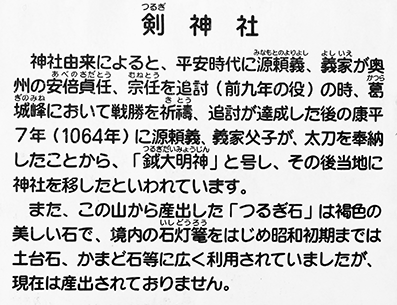 私には大変珍しい武張った神社名に大いに興味を惹かれました。神社の伝承は奥州街道沿いの町でしばしば見分する類似の話を思い出させるものです。
私には大変珍しい武張った神社名に大いに興味を惹かれました。神社の伝承は奥州街道沿いの町でしばしば見分する類似の話を思い出させるものです。
石材との関連はなる程と面白く読ませてもらいました。![]() 2020.01.04
2020.01.04
 右に置かれた阿像、かなり迫力を感じる石像です。牙状の歯をむき出して鋭い目で訪れる者を見つめていました。
右に置かれた阿像、かなり迫力を感じる石像です。牙状の歯をむき出して鋭い目で訪れる者を見つめていました。
玉取りの玉には模様の彫りが施されています。![]() 2020.01.04
2020.01.04
 阿像の後ろから吽像を写しています。玉には模様の彫りを施してありますが、後姿からみる後方の彫りの線はあっさりしている様に見えます。背中の表情からもその存在感を感じさせる石像に思えました。
阿像の後ろから吽像を写しています。玉には模様の彫りを施してありますが、後姿からみる後方の彫りの線はあっさりしている様に見えます。背中の表情からもその存在感を感じさせる石像に思えました。
![]() 2020.01.04
2020.01.04
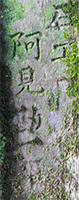
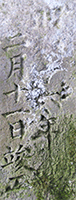
![]()
![]() 台座には年号・石工名・目的などが彫られた文字が見られます。”支那事変”や”紀元2600年記念”の文字と併せると年代の一部欠落した部分は、十らしき文字が見える事、その下に六の文字が見られる事なども併せて昭和16年と推定出来そうです。
台座には年号・石工名・目的などが彫られた文字が見られます。”支那事変”や”紀元2600年記念”の文字と併せると年代の一部欠落した部分は、十らしき文字が見える事、その下に六の文字が見られる事なども併せて昭和16年と推定出来そうです。![]() 2020.01.04
2020.01.04
 左に置かれた吽像も目をしっかりと見開いて見る者の目を捉えてているようです。彫りはそれ程繊細には見えませんが石像の持つ圧力を感じさせます。
左に置かれた吽像も目をしっかりと見開いて見る者の目を捉えてているようです。彫りはそれ程繊細には見えませんが石像の持つ圧力を感じさせます。
薄暗い境内でははっきりしませんでしたが、落ち着いて画像でも確認するともしかすると子取りの意匠ではないかと思えてきました。そうだとすると子供は”見ざる”の動作をしているかもしれません、手で目を覆っているようにも見えてきます(見間違いの恐れもありますが)。もしそうだとしたら随分と洒落た意匠に思えます。
![]() 2020.01.04
2020.01.04

 狛犬の載る台座には牡丹の花が彫られているようです。台座と狛犬のバランスが美しい様子なので写真を撮りました。
狛犬の載る台座には牡丹の花が彫られているようです。台座と狛犬のバランスが美しい様子なので写真を撮りました。 静かな美しい境内に居た事で随分と心が落ち着いたようです。再度拝殿で一礼して参道の石段を下る事にします。
静かな美しい境内に居た事で随分と心が落ち着いたようです。再度拝殿で一礼して参道の石段を下る事にします。 写真左奥に神社野鳥居が見えますが、集落の中を抜ける道まで戻ってきました。神社への曲がり角に標識がたっています。私は塩釜神社から剣神社にやって来ました。
写真左奥に神社野鳥居が見えますが、集落の中を抜ける道まで戻ってきました。神社への曲がり角に標識がたっています。私は塩釜神社から剣神社にやって来ました。
標識に書かれた100m程先の芭蕉の句碑に向かうことにします。進行方向には東北道が見えます。![]() 2020.01.04
2020.01.04
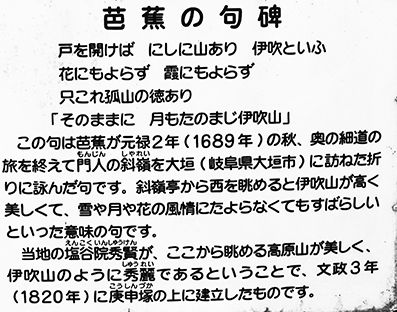 道路の膨らんだ場所に車を止めて句碑を観させて貰いました。元禄2年の陽暦5月16日に江戸・深川を出発した46歳の芭蕉の奥の細道の過酷な旅は約5ケ月、行程約2400キロにわたりました。
道路の膨らんだ場所に車を止めて句碑を観させて貰いました。元禄2年の陽暦5月16日に江戸・深川を出発した46歳の芭蕉の奥の細道の過酷な旅は約5ケ月、行程約2400キロにわたりました。
陽暦10月21日には旅の終わりの大垣に着いたようです。その折りの大垣滞在中の事と思われます。江戸時代、既に日本ではこのような営みが各地で行われていた事(神社に奉納される和算の扁額等と共に)を知る事は大きな喜びです。![]() 2020.01.04
2020.01.04
 高原山と思われる秀麗な山を望む盛土の山の上に江戸時代の石塔が立っています。
高原山と思われる秀麗な山を望む盛土の山の上に江戸時代の石塔が立っています。
”そのままに月もたのまじ伊吹山”の碑文がかなり薄れていました。
![]() 2020.01.04
2020.01.04
 思いもかけず芭蕉の句碑に出会うことが出来ました。素晴らしい神社だけでも大きな満足感を感じていましたが、更にオマケが付いたのです。
思いもかけず芭蕉の句碑に出会うことが出来ました。素晴らしい神社だけでも大きな満足感を感じていましたが、更にオマケが付いたのです。
次の神社に向かって、再度の幸運を願いながら車を走らせました。それにしても、1月2日に続き今日も絶好の初詣日和です。![]() 2020.01.04
2020.01.04
| 本日カウント数- | 昨日カウント数-
|
|
Provided: Since Oct.10,2007 |
||

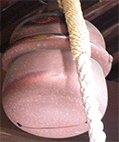 かなり大きな神社で、私の訪ねた神社では珍しく、土曜日でもあるせいか初詣の人がかなり訪れていました。
かなり大きな神社で、私の訪ねた神社では珍しく、土曜日でもあるせいか初詣の人がかなり訪れていました。
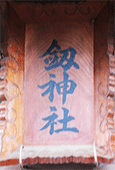 塩竈神社から田畑の中の道を進んでいくと集落の中に鳥居が見えました。近くに県境の村への行き来に使用する東北道が通っていたのは驚きです。田圃の中の細い道の先にある鳥居の前のスペースに車を止めさえてもらいました。多分この神社も農繁期には参拝を遠慮した方が良いように感じました。
塩竈神社から田畑の中の道を進んでいくと集落の中に鳥居が見えました。近くに県境の村への行き来に使用する東北道が通っていたのは驚きです。田圃の中の細い道の先にある鳥居の前のスペースに車を止めさえてもらいました。多分この神社も農繁期には参拝を遠慮した方が良いように感じました。